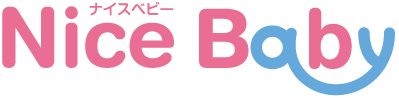ベビー用品
ベビーカー派なら持つべき!レインカバーはマルチに使える神アイテム♪
雨の日の赤ちゃんとのお出かけは抱っこ紐?ベビーカー?ベビーカーならレインカバーは必要なのかな?と疑問をお持ちの方。 実はこのレインカバー、雨の日以外でも役立つシーンがたくさんあるとっても便利なアイテムなんですよ! 赤ちゃん連れの雨の日の外出はできるだけ控えたいところですが、外出せざるを得ないこともありますよね。状況によってはベビーカーを使いたいことも出てくると思います。特にベビーカーの利用頻度が高いご家庭なら、レインカバーは持っておくと安心! 雨の日の活躍はもちろんですが、花粉やほこりの多い日、風が強かったり寒さが厳しい日、また、感染予防の対策としても、実は一年を通して活用することができるのです。 そこで今回は、レインカバーの活用方法と商品選びのポイントについて解説します。また、一般的なレインカバー保持率を把握するために、先輩ママパパへアンケート調査も行いました。 こちらの記事を読んでいただければ、レインカバーの利便性がきっと理解できると思います。上手に活用すればお子さまとのお出かけがもっと快適になるはずです。是非最後まで読んでくださいね。 1. 先輩ママパパに聞いた!ベビーカー用レインカバーは持っていて損なし まずは、一般的なベビーカー用レインカバーの使用状況を知るために、ベビーカーをお持ちの先輩ママパパにアンケート調査を実施しました。 最も多い回答が「必要」の59%、半数以上の方がレインカバーの必要性を強く感じているということがわかりました。「あれば便利」と回答した方が29%、使用頻度は少なかったものの持っていて助かった、という意見が多く聞かれました。 使用できる日が限られているにも関わらず、なぜこんなにも多くの方がレインカバーを利用し、必要性を感じているのでしょうか。 次の章では、いつ・どんなときにあると便利なのか、レインカバーの役割について解説していきます。 2. 雨除けだけじゃない!1年を通して活躍するレインカバーの役割 レインカバーは雨が降った日にしか使用しないものだと思っている方も多いことでしょう。冒頭でもお伝えしましたが、実はレインカバーは1年を通して、様々なシチュエーションで活躍するアイテムなのです。 雨の日はお出かけしないし必要ない、と思っている方も、これからお伝えする3つの使い方を知れば「必要かも?!」と思うかもしれませんよ。それでは詳しく見ていきましょう! 2-1. マスクができない赤ちゃんも外からのウイルス感染対策できる 感染症が流行している時期の外出は控えたいものですが、どうしても外出しなければならない場面もあることでしょう。大人はマスクで対策できますが、小さな赤ちゃんはどうでしょうか。 顔の半分以上を覆う布(マスク)は呼吸がしにくく、まだ意思表示ができない時期の使用は、窒息の恐れがあり、赤ちゃんのマスク使用は危険です。 とはいえ、何もしないのも不安。 そんなときは、レインカバーを使って外気から赤ちゃんを守ってあげましょう。手を伸ばして、周りの物に触れることを防ぐこともできます。 ▼ 赤ちゃんのマスクについて詳しくはこちら記事で マスクのできない赤ちゃんを守る方法 2-2. 風を防いで防寒対策になる 冬場のお出かけには赤ちゃんの風よけや寒さ対策としても大活躍。 特に風が冷たい日は、赤ちゃんにブランケットをかけていたとしても冷えが心配になりますよね。風でブランケットがペラペラめくれてしまうことも。 そんな時にレインカバーを被せてあげると赤ちゃんが冷たい外気にさらされることがなく、寒さを和らげることができます。 2-3. ホコリや虫・花粉から赤ちゃんを守る 外には赤ちゃんにとって危険がいっぱい。...
必見!驚くほどコンパクトに折りたためるベビーカー最新モデル11選【2022年】
この記事に辿り着いたママパパは、ベビーカーの大きさが気になっていて、通常サイズよりも小さくてコンパクトに折りたためるベビーカーをお探しではありませんか? 子育てにおいて本当に重宝するベビーカーですが、たたんでも結構な大きさがあって、意外と日常生活で邪魔になってしまうケースも多いですよね。 例えば、普段毎日のようにベビーカーを使うような方だと、玄関にそのまま置きっぱなしになってしまって導線の邪魔になったり。 他にも、車で買い物に行ったときにトランクがベビーカーで占有されていて荷物が載せられないなんてことも。 このようにベビーカーの大きさにお悩みの方に、できるだけコンパクトに折りたためるベビーカーを厳選してご紹介します。 コンパクトにたためるベビーカーは収納に優れていることは勿論ですが、たたんだ時に見た目もすっきりしていてオシャレな物が多いんですよ。 ベビーカーは決して安い買い物ではないのでちゃんとご自身の希望に合ったものを選びたいですよね。 今回は国産メーカー、海外メーカーからコンパクトに折りたためる様々なベビーカーをピックアップしました。 よりサイズ感が分かりやすくなるように、たたんだ状態のベビーカーと身長160cmのママのシルエットを並べて比較対象としています。 コンパクトに折りたためるベビーカーの特徴が分かり、ご自身にぴったりのベビーカーが選択できれば幸いです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. こんなに小さく折りたためる!おすすめA型・B型ベビーカー 生後1ヵ月から使えるA型ベビーカーと、生後6ヵ月くらいから使えるB型ベビーカーに分けて、コンパクトに折りたためるおすすめベビーカーをご紹介します。 1-1. コンパクトに折りたためるA型ベビーカー厳選5点 【Silver Cross(シルバークロス)】JET2020 Special Edition 折りたたむとコンパクトなスーツケースのようになる Jet2020は、人間工学に基づいた新しいシートは赤ちゃんの快適性をさらに高め、前輪の幅がより広く、サスペンションも改善し最高の乗り心地を実現。耐荷重もシート25kg、バスケット5kgまで可能です。超軽量でコンパクトなベビーカー。折りたたんで付属のカバーを取り付ければ小さなスーツケースのように動かすことができます。 対象月齢 新生児~25㎏(7歳頃まで) 本体重量 6.2kg サイズ 開:幅48×奥行84×高さ102cm 閉:幅31×奥行24×高さ58cm 価格 [購入]52,800円 | >...
ベビースケールは必要な時期だけレンタル!母乳量を量って不安を解消
ベビースケールは、赤ちゃん成長記録や授乳量が数値でわかる便利な赤ちゃんの体重計です。 ママたちが初めてベビースケールを使うのは、おそらく産院の授乳指導の時が多いのではないかと思います。授乳前後で赤ちゃんを計測して、どのくらい母乳を飲んだのかを確認します。まだ母乳のあまり出ない時期には、母乳がどのくらい出ているのかも目安になり安心ですね。 「退院後に母乳量の確認はどうしたらいい?」 「ベビースケールなしでどうやって追加するミルクの量を決めるの?」 「自宅でもベビースケールが使いたいけど、何がいいの?」 産院では指導があるので安心ですが、退院後の授乳の不安が頭をよぎるママも多いはず。 ベビースケールの必要性は人によって異なります。母乳量の違い、育児方法の違いなどにより、必須だった方と必要なかった方とに分かれます。 では、ご自身が必要なのか不要なのか。 それは、産前では答えが出ません。産後の授乳状態で判断していくしかありません。 唯一言えることは、不安を感じるのであれば、持つべきアイテムであるという事です。 そしてベビースケールは購入ではなく絶対にレンタルすべきという事です。 本記事では、ベビースケールがご自身に必要か判断するための材料として、使用する意味や先輩ママの体験談などを紹介していきます。実際に活用する際の商品選びのポイントとレンタル方法についても併せて解説していきます。 不安いっぱいの母乳育児が、少しでもスムーズにそして楽にスタートできるよう、新米ママのお役に立てたら嬉しく思います。是非最後まで読んでくださいね。 1. 母乳育児に不安を感じるならベビースケールを使おう ベビースケールは誰もが必要となるアイテムではありませんが、その必要性の感じ方は人それぞれ。また母乳育児の進め方によっても要不要、選ぶスケールが変わってきます。 もし、あなたが退院後の授乳に不安を感じているようであれば、ベビースケールは使ってください。母乳を与えることができるのは唯一赤ちゃんのママだけ。ママが安心して授乳できる環境が何よりも大切だからです。 この章では、まずベビースケールを使う意味について知っていただきたいと思います。必要性を感じるシーンの解説から順を追ってみていきましょう。 1-1. ベビースケールの必要性を感じるシーン ベビースケールの必要性を感じるシーンはいくつかあります。使用する目的で選ぶアイテムや使用期間も変わってきます。以下3つのシーンがご自身に該当するようであれば、スケールの導入を検討していきましょう。 1-1-1. 赤ちゃんの飲んだ母乳量を測定したい時 母乳量が少なくミルクを追加する場合、母乳をあげる前と後で赤ちゃんの体重を計測することで母乳量がわかり、追加するミルクの量を調整することができます。 特に、産後間もない時は母乳量が少なく追加でミルクも飲ませることが多いと思います。どの程度ミルクを飲ませるのかママ一人での判断は難しいので、最初のうちは計測して産院の指示に従った量を飲ませると安心ですね。 1-1-2. 母乳量が体感できなくて不安な場合 母乳量が足りているかは、徐々にママの体感と赤ちゃんの様子でわかるようになってきます。母乳量が少ない場合、なかなか体感できないという方も多くいます。それを不安に感じるようであれば、赤ちゃんの体重を計測して母乳量を目で確かめるといいでしょう。 1-1-3. 赤ちゃんの成長記録を残したい場合 生後すぐの小さくて細い体も、1ヵ月を過ぎるといつの間にかぷっくりとして、その成長の早さに驚かされるものです。 毎日決まった時間に赤ちゃんの体重を計測して記録を残してみるのもベビースケールの楽しい使い方のひとつ。スケールに赤ちゃんを乗せたまま写真を撮って記録すれば、日々の成長が可愛い姿と共に残り、素敵な思い出となることでしょう。...
対面式ベビーカーは絶対に使うべき!子育て経験から私が断言する理由
ベビーカーを準備するにあたり、両対面式と背面式どちらにするか悩んでいませんか? 「そもそも両対面式・背面式は何が違うの?」と疑問を持っている人もいると思います。 両対面式とは、赤ちゃんと向かい合って走行する「対面走行」と、赤ちゃんが進行方向を向いて走行する「背面走行」、どちらもできるベビーカーのことです。 一般的に対面走行ができるベビーカーは「両対面式」としてA型ベビーカーに分類され、背面走行のみできるベビーカーは「背面式」としてB型ベビーカーに分類されることが多いです。 両対面式のベビーカーは対面と背面を切り替える機能を持っているので、その分背面式と比べ高額になる傾向があります。 高価だからこそ購入には慎重になりますよね。 そうなるとやっぱり「そんなに高いお金を払ってまで、対面式ベビーカーにする必要は本当にあるの?」と疑問に感じてしまうもの。 でも、3人の子育て経験を持つ私は、「対面式の機能は絶対にあった方がいい!」と断言します。 それは、「この時期しか味わえない貴重な時間を、赤ちゃんと一緒に楽しむことができる。」ということが最大のメリットだと思うからです。 対面機能は赤ちゃんの月齢が浅い時期に使うことがほとんどです。 寂しい話にはなりますが、子どもは日々成長し、気付けば親の顔より外の景色を見ていた方が楽しくなってくるんです。実際私がそうでした。 赤ちゃんと顔を合わせての散歩は、肌を触れていなくてもスキンシップが取れ、赤ちゃんとの絆をより深めることができる一つの方法であると思います。 この時期にしかできないからこそ、貴重で大切なことだと感じています。 他にも両対面式ベビーカーは、 赤ちゃんの様子がいつでも見えて安心できる。 赤ちゃんもママパパの顔が見えるから安心できる。 外出中、赤ちゃんとのコミュニケーションがとりやすい。 日差しや風の向きに合わせて切り替えができる。 人混みやお店の中などで、いたずら防止ができる。 成長に合わせて背面に切り替えられるため、1台のベビーカーを長く使うことができる。 など様々なメリットがあります。 今回は、両対面式ベビーカーを使ったことのある100人の先輩ママパパに、エピソードや感想をアンケート形式で調査しました。 対面走行の良かったことや逆に困ったことなど詳しく聞き込みした情報もお伝えします。 きっと両対面式ベビーカーの必要性が分かるはずです。 ぜひ、ベビーカー選びのお役に立ててください。 1. 半数以上の先輩ママパパが対面機能の必要性を実感! こちらは、両対面式ベビーカーを使ったことのあるママパパ100人に聞いたアンケート結果です。 実に6割近くの人が対面機能は必要と回答しています。 どんなときに必要だと感じた? 「赤ちゃんの顔を見て、常に様子を確認できて良かった。」...
付け外し簡単な抱っこ紐おすすめ12選!失敗しない選び方のポイント
付け外しが簡単にできる抱っこ紐をお探しでしょうか? 抱っこ紐の使用頻度が下がって簡易的なタイプがほしい、外出時にベビーカーと併用するために着脱が楽なものがほしい、できるだけシンプルな構造の抱っこ紐がほしい... 必要性を感じた理由は違っても、簡単な抱っこ紐を探している方にこの記事を読んで頂いてることと思います。 抱っこ紐には、大人気エルゴベビーのような長期で使えるキャリータイプ、スリングやベビーラップといった布で赤ちゃんを包み込むタイプなど、機能もデザインも異なるさまざまな種類があります。 着脱方法は抱っこ紐の構造によりその簡易性に違いが見られますが、主な特徴として以下の2つに分類することができそうです。 ◎ 単機能タイプ:ひとりで簡単に付け外しができる ◎ 多機能タイプ:複雑な構造で抱き方の切り替えに時間がかかる 多機能で何パターンもの抱っこに対応できるタイプは、往々にして構造が複雑な傾向にあります。 第一の難関としては取扱説明書。使用前の読解の段階でぐったりしてしまうこともあります。慣れてしまえば「難しくない=簡単」と言えそうですが、抱っこする人が変わる時、赤ちゃんが大きくなってきた時、抱き方を変える時など、その都度調整し正しく抱っこ出来ているか確認する必要も出てきます。付け外しが簡単とは言い難いのが正直なところです。 そこで今回は『付け外しがとにかく簡単な抱っこ紐』に注目し、単機能で簡単に使える抱っこ紐について様々な角度から解説していきたいと思います。 抱っこ紐選びをスムーズに進めるための事前に注意すべきポイントを解説、対象月齢別で厳選した簡単抱っこ紐10選を紹介します。 さらに、実際比べて見てから購入を決めたい方へ、お得にレンタルできるナイスベビーのサービスについても紹介しますので、購入前の検討に是非活用してください。目的に合ったベストな抱っこ紐選びの参考に、是非最後まで読んでくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 簡単な抱っこ紐を選ぶ時、注意すべき3つのこと 簡単に使える抱っこ紐は、スピーディにストレスなく赤ちゃんを抱っこできる手段として、忙しい育児にはとても便利なアイテムです。 簡単抱っこ紐を選ぶ際、「安いから」「簡単そうだから」だけで安易に購入すると、サイズが合わなかったなど、うまく使えなかった、ということにもなりかねません。安くても使えなければ無駄な出費となってしまいます。 そんな事態に陥らないために、購入前に注意すべき3つのポイントについて解説していきますので、購入時の参考にしてください。それでは早速見ていきましょう! 1-1. サイズを確認!対象月齢が合っているかチェックすること 多機能なキャリータイプの多くは3~4歳頃まで長く使えるものが多いですが、単機能の簡単抱っこ紐の多くは、使用月齢が限定されている場合が多くあります。新生児期に特化したタイプ、腰がすわってから使えるコンパクトタイプなど、赤ちゃんの体重や成長度合に合った商品であるか必ず確認するようにしましょう。 1-2. パパママ共有?家でつかう?使用シーンをイメージすること 体格差のあるママとパパが共有できるものがいいのか、サイズ固定の抱っこ紐でいいのか、使用者が誰なのかによっても選ぶアイテムは変わってきます。また、家で使うか外出時に使うかによっても、使い勝手が異なることも。 大切なことは、どんな時のために必要なのか、目的を明確にすること。 例えば、 ◎パパとママ共有で必要とする場合は、サイズ調節ができるタイプ ◎お出かけで必要とする場合は、折りたためるコンパクトタイプ ◎乗せ降ろしが頻繁の場合は、装着が簡単なスリングタイプや台座だけのヒップシート など、主に使用する目的をイメージしておくことが大切です。 1-3. 安全のため!取扱説明書はしっかり読むこと...
A型とB型ベビーカーは使い始め時期が違う!AB兼用、バギーも解説
店頭やネットショッピングではいろんな種類のベビーカーが並んでいます。 かっこいいデザインからカラフルでかわいいものまで、見ているだけでワクワクしますよね。 でも、はじめてベビーカーを選ぶうえで必ず出てくるのが「A型B型ってなに??」という疑問。 さらに「AB兼用」や「バギータイプ」などいろんな種類が出てきて、どのタイプを選べばいいのか迷ってしまいます。 そこで今回は、はじめての人でもすぐに分かるように、ベビーカーの種類とその特徴を解説します。 また、先輩ママパパから聞いた実体験をもとに、A型・B型ベビーカーを選ぶうえで「必ず知っておくべきこと」と「絶対にあったほうが良い機能」をお伝えします。 これさえ知っておけばベビーカー選びを間違えることはありません。 はじめてベビーカーを選ぶ人は絶対に押さえておきましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. A型とB型ベビーカーは使い始めの月齢が違う 現在日本のベビーカーはSG基準により、A型とB型の2種類に分類されています。 よく耳にする「AB兼用」はA型に、「バギータイプ」はB型に含まれます。 まず、A型とB型ベビーカーの最も大きな違いは、「背もたれの角度の違い」です。 背もたれの角度が違うから、それぞれ使い始めの月齢が違うのです。 1-1. A型ベビーカーはしっかりリクライニング【生後1ヵ月~】 A型ベビーカーは背もたれをしっかりと倒すことができるので、生後1ヵ月からすぐに使い始めることができます。 SG基準ではリクライニング150°以上が条件となっていますが、170°以上倒せるベビーカーが主流です。 フラットに近い状態なら生後1ヵ月の赤ちゃんでも安心して乗せることができますよね。 ※SG基準では適用月齢が4ヵ月からのタイプもA型に含まれます。その場合は背もたれの角度が最も倒した状態で130°以上になることが条件になります。 最近では、衝撃を吸収するクッションが採用されていたり、車輪部分に振動を抑えるエアサスペンションが搭載されるなど、月齢の浅い赤ちゃんを守るための機能が充実しています。 また、多くのA型ベビーカーは、赤ちゃんと向き合った状態にすることができます。 対面と背面を切り替えできる「両対面式」の機能を持ったベビーカーが多いことも特徴です。 しかし、機能が多い分、車体が重たくなってしまうことや、価格が高くなってしまうことがデメリットです。 1-2. B型ベビーカーはコンパクトで軽量【生後7ヵ月~】 B型ベビーカーは軽くてコンパクトなことが最大の特徴です。 赤ちゃんが成長して少しずつお出かけが増えてくると、ベビーカーを使うことも多くなってきます。 そうなるとやっぱり軽くて持ち運びしやすいということは大きなメリットになりますよね。 B型ベビーカーの条件として、リクライニング機能が必須ではないため、生後7ヵ月まで使うことはできません。その分、月齢の浅い赤ちゃんのための機能は除かれていて、A型と比べ価格が安めになっています。 また、赤ちゃんと対面になる機能は付いていないので、対面式を希望する場合はA型ベビーカーを選ぶ必要があります。 1-3. AB型ベビーカーは軽量化されたA型ベビーカー...
両方あったら絶対に助かる!抱っこ紐とベビーカーどちらも必要な理由
「赤ちゃんとのお出かけって、抱っこ紐が必要?ベビーカーが必要?」 出産準備を進めながら、こんなことを疑問を持ち始めるママパパ、多いことと思います。 どちらも子育てにはヘビーユースしそうなイメージの抱っこ紐とベビーカー。お出かけアイテムとしてデザインやブランドにもこだわり、ファッション性も重視したいですよね。 こだわればその分出費がかさむのは当然。失敗のないよう慎重に商品選定をしたいところですが、出産準備を進める中で「そもそも両方使うの?」という疑問も沸き起こってくるのではないでしょうか。 実際に「どちらが必要?」「両方用意した方が良い?」というご相談はナイスベビーへ多くいただくお問い合わせの一つです。 どちらも子育てにはとても便利なアイテムですが、その必要性は生活スタイルや周囲の環境によっても大きくことなるため、出産準備の段階で判断するのは難しいと思います。 産後すぐに必要になるアイテムではないため、産前には準備せずに、産後の生活の状況に合わせてアイテムを選んでいくことをおすすめします。 その際に是非参考にしていただきたいのが先輩ママパパの意見! 今回ナイスベビーラボでは、先輩ママパパ150人に「抱っこ紐とベビーカーはどちらが必要なのか?」アンケートを実施しました。抱っこ紐とベビーカーの所有率、あってよかった、困ったなどのリアルな体験談を紹介していきます。 この記事を読んでいただければ、抱っこ紐とベビーカー導入についての悩みがクリアになっていきますので、是非、最後までお付き合いくださいね。 1. 先輩ママパパ150人に聞いた抱っこ紐とベビーカーどっちが必要? 一般的な使用状況を知るために先輩ママパパ150人に赤ちゃんとのお出かけに「抱っこ紐とベビーカーどちらが必要か」アンケート調査を行いました。 結果はその半数が「どちらも必要」と回答! それぞれ優れたポイントが異なるため、行き先に合わせて使い分けるのがよいとの意見が多く見られました。 【ベビーカー】 荷物が多い時や長時間の外出にとても便利。移動中でも赤ちゃんのお昼寝タイムをしっかり確保することができます。交通手段や行先によっては邪魔になってしまうこともあるため、目的によって要不要の検討が必要です。 【抱っこ紐】 人混みや電車など公共交通機関を利用する時に便利。特に小さなうちはママにぴったりと密着して距離が近いので、赤ちゃんにもママにも何かと安心。成長するに従って長時間の抱っこは体の負担も大きくなり、ヨチヨチ歩きが始まると抱っこと降ろすの繰り返しがストレスに感じることも。短時間使用におすすめのアイテムです。 抱っこ紐 ベビーカー メリット コンパクト 赤ちゃんとの距離が近い ママパパの体への負担が少ない 荷物置きとしても使用できる デメリット ママパパの体への負担が大きい 行先によって使えない事もある どちらにも上記のようなメリットデメリットがあります。それを踏まえて、半数が両方使っていたという理由はどこにあるのか、この後の章で実際に体験したシチュエーションを見ていきましょう。 2. 両方持っていて良かった!無くて困った!【体験談】...
抱っこ紐は使い分ける!レンタル活用術と購入すべきタイプの見分け方
ママのファッションの一部にもなる抱っこ紐。初めての抱っこ紐選び、あれこれ悩みますよね。 【抱っこ紐】という言葉ひとつでまとめてしまうにはあまりにも多種多様。商品選びの基準は、人気のブランドであったり、長く使えるものが候補に上がってくると思います。 「みんなが使っているから」 「人気があるから」 という理由だけでアイテム選びをしていませんか? でも、ちょっと待ってください! せっかく『抱っこ紐 レンタル』に着目したスルドイあなたには、かしこい抱っこ紐選びの道を選んでほしい! 抱っこ紐に多種多様なものがあるのは、赤ちゃんによって、ママによって、月齢によって、使用目的によって、使い勝手のいいものが異なってくるからなのです。 抱っこ紐はどれでも同じと思ったら大間違い! 流行りに流されて購入してしまうと無駄な出費となる可能性も大!ご自身の生活状況に合わせた商品選びが大切です。 では、かしこい抱っこ紐選びの道とは何でしょうか? それは、無駄のない快適な抱っこ紐ライフを目指すこと。 それには、抱っこ紐の「購入」と「レンタル」をうまく組み合わせていくこと大きなポイントとなります。一言でいえば、レンタルを上手に活用していくことなのです。 そこで本記事では、抱っこ紐を購入orレンタルの見極め方、得するレンタルの活用術について解説していきます。また、レンタル未経験の方の多くが抱くレンタルに対する不安を解消するために、レンタルサービスの全貌も公開していきます。 これであなたも、無駄のない楽で快適、安心な抱っこ紐ライフの道を進むことができますよ! 是非最後までお付き合いくださいね。 1. 抱っこ紐にはレンタルすべきタイプがある! ベビー用品「購入 or レンタル」の定義 使用頻度が高い・長期間使用するもの 購入 短期間だけの使用だけど必要なもの レンタル 子育てアイテムを購入するかレンタルするか選定の目安は、上記のように考えていくと導入方法を選択しやすくなります。 これで言えば、抱っこ紐は前者の「購入」に値しますね。そうです。正に購入向きのアイテム... なのですが! 実はそうとも言い切れないがあるのです。 ここであなたに知ってもらいたいのは、抱っこ紐には『購入すべきタイプ』『レンタルすべきタイプ』この2タイプがあるということ。...
ママも汗っかきな赤ちゃんも一年中快適!メッシュ素材抱っこ紐10選
メッシュタイプの抱っこ紐をお探しでしょうか? はじめて抱っこ紐を検討中の方も、二本目の抱っこ紐をお探しの方も、一年中快適に過ごせる抱っこ紐を選びたいですよね! 抱っこ紐は、季節や赤ちゃんの月齢によって使い分ける方が多く、実際、買い直したりセカンド用として買い足しをしたという声をよく聞きます。 メッシュタイプの抱っこ紐を探している方なら「メッシュ」「クール」「エアー」といった涼しげなキーワードを用いた商品名が人気商品に多いこと、もうお気づきですよね? それは、汗ばむシーンは夏だけではない!一年を通して多々あるからなのです。 暖房の効いた屋内で上着を着たままでいると、じわっと汗ばんでくることがよくあります。大人が暑いならその時点で汗っかきの赤ちゃんは汗だくです。 夏は、涼しいメッシュ素材が必須ですが、冬でも通気性のよいメッシュ素材を使えば快適に清潔を保つことができます。素材を意識することは、抱っこ紐選びの重要なポイントですね。 そこで今回は抱っこ紐の「メッシュ素材」に注目!通気性に優れたメッシュ素材の抱っこ紐の魅力を徹底解剖していきます。シーズン別で活躍する人気の抱っこ紐をpickup、メンテナンスについても知っておくべきポイントを紹介します。 赤ちゃんとの抱っこライフを楽しく快適になるために、この記事がお役立ていただければうれしいです! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. メッシュ素材の抱っこ紐が夏も冬も大活躍する理由 メッシュ素材といえば、夏場に涼しく過ごすための素材というイメージが強いと思います。しかし、新陳代謝が活発な赤ちゃんは、冬でもたくさん汗をかいているため、メッシュ素材の抱っこ紐は、季節を問わず一年中、大活躍するアイテムなのです。 各メーカーから発売される抱っこ紐の中でも、最近では特にメッシュタイプが人気が高いようです。 では、まずはじめにメッシュ素材の抱っこ紐の特徴と大人気の理由について解説していきます! 1-1. 一年中快適に過ごせる通気性の良い素材! 赤ちゃんは大人より体温が高く、とても汗っかきです。夏はもちろんのこと、冬の暖かな室内でも汗ばんでいることが多々あります。汗疹になったり、熱がこもってのぼせてしまったり、汗が冷えて風邪を引いてしまったり、汗ばむことで体調不良を起こしてしまうこともよくあります。 そんな時、通気性に優れているメッシュ素材なら、熱や湿気を逃がし、夏でも冬でも快適に過ごすことができます。日本ではメッシュ素材でつくられた抱っこ紐が四季を通して大活躍します。 メッシュ素材といっても一概にひとくくりにできず、商品により生地の厚みやメッシュの範囲が異なることも知っておいてほしいポイント。 抱っこ紐の一部分だけメッシュなのか、抱っこ紐の布地全体がメッシュなのかによって通気性も異なりますので、使用頻度や地域、ライフスタイルによって、選ぶ際には気を付けてみてくださいね。 1-2. 汚れたらすぐに洗える!速乾性のある素材だから安心! メッシュタイプの抱っこ紐は、洗濯機での洗濯が可能なものがほとんどです。汗をかいたり、ミルクの吐き戻しで丸洗いしたい場面も出てきます。 冬でも半日もあれば乾くので、洗い替えの用意がなくても安心です。また、ポリエステルの布地は、しわができにくく耐久性もあるのものメリットです。 1-3. 軽くてコンパクトになる!メッシュ素材なら軽さも魅力! メッシュ素材とコットン素材と比べると、同じシリーズでもメッシュタイプの抱っこ紐は軽いつくりになっています。持ち運んだり、使わない時を考えると、多少なりともコンパクトで軽量であれば扱いやすくなります。 2. シーズン別!メッシュ素材の抱っこ紐10選! 前章でメッシュタイプの抱っこ紐の人気の理由は、お分かりいただけたと思います。その万能なメッシュ素材の抱っこ紐には沢山の種類があり、適応月齢も抱っこの仕方も異なります。自分に合った抱っこ紐が選べるように、使用シーズン別に厳選したおすすめの商品をpickupしました! 今、すでに抱っこ紐をもっていて、買い足しする場合は、異なる種類の抱っこ紐を選んで使い分けるのがおすすめです。 2-1. 初めて迎える夏はコレ!新生児タイプの抱っこ紐 ベビーキャリアMINI Air【ベビービョルン】...
抱っこは交通違反!抱っこ紐で自転車に乗る時に知っておくべき注意点
お子さまの送迎や買い物、子育て世代の日常に大活躍する自転車。これなしでは日々の生活が成り立たないという方も多いのではないでしょうか。 3人乗りできる子供乗せ自転車や専用シートが設置できる自転車で一定の基準をクリアしていれば、3人乗りが認められています。前後にお子さんを乗せて運転している姿は街中でもよく見かける光景ですね。そんな中、一人は幼児座席に乗せて、赤ちゃんはおんぶをしたまま走行している方を見かけたことはありませんか?筆者の私は、その光景をはじめて見たとき衝撃を受け、大丈夫なのだろうか?と心配になったことを覚えています。 お子さまがまだ小さかったり、荷物が多かったり、幼児用座席を使えないシチュエーションも想定ができます。そんな時、抱っこ紐を使っておんぶや抱っこをしたままの自転車走行は可能なのでしょうか? 法律では、「おんぶ」であれば抱っこ紐を使用しての同乗が認められています。「抱っこ」しながらの走行は交通違反となり、罰則が科せられます。大変危険な行為ですので絶対にやらないようにしてください! おんぶしながらの自転車走行については賛否両論ありますが、「車を持っていない」「周囲にバスや電車がない」「保育園が遠くて上の子の送迎で必要」「ベビーカーを嫌がる」など生活環境によっても子育ての在り方は様々。 法律で認められてはいますが、ルールを守った上で安全走行が確保できることを前提に、ご自身でしっかりと判断することが大切です。 本記事では、法律で定められいるルールと抱っこ紐を使用して自転車に乗る時の注意事項について詳しく解説していきます。 安心・安全な走行を実現するために、ぜひ、さいごまでお付き合いください。 1. 「抱っこ」は交通違反!「おんぶ」は交通違反ではない 抱っこ紐を使用しながら同乗が認めれている場合 16歳以上の者が6歳未満の幼児を確実に紐などで「おんぶ」している 16歳以上の者が6歳未満の幼児を「幼児用座席」にひとり乗車させ、もうひとりを紐などで確実に背負っている(子供ふたりの場合) そもそもの疑問として「おんぶ・抱っこ」をしながら自転車に乗っても違反にはならないのだろうか、という点。 本章の冒頭にもあるように、抱っこは交通違反、おんぶは法律で認められています。 基本的に、自転車でのふたり乗りは法律で禁止されていますが、例外として『16歳以上の者が6歳未満の幼児を確実に紐などで背負っている場合』は同乗を認められています。自転車の種類は問わず、この条件であればおんぶでの自転車走行は認められています。 ここで大切なのが、背負っている(おんぶ)場合に限り認められているということ。つまり「抱っこ」の場合は同乗が認められておらず交通違反に値します。 やむを得ず、自転車に抱っこ紐で同乗させたい場合は必ず「おんぶ」をすることが原則です。必ず守りましょう。 1-1. 前抱っこが危険な理由 抱っこの危険性 おんぶよりも赤ちゃんとの間に隙間ができやすい 足元など視界が妨げられる バランスが取りにくい 赤ちゃんが視界に入り、運転に集中できない 抱っこの方が赤ちゃんの様子がわかり、何かあった時に素早く対応できて安心なのでは?と疑問に思う方もいるかもしれません。実際に抱っこしたまま走行している方を見かけることもあります。 しかし、抱っこでの自転車走行には上記に記載したような様々な危険性が考えられます。 例え事故が起こらなかったとしても、抱っこで自転車に乗った場合は、2万円以下の罰金または過料を科せられます。 おんぶの場合は、前傾姿勢になった運転者の背中にぴったりと密着した状態になります。足元がしっかりと見えて、バランスも取りやすくなるため、抱っこに比べると事故のリスクを軽減することができるのです。 とは言え、おんぶの場合も必ず赤ちゃんの安全を守れるというものではありません。何より大切なのは、安心・安全な走行を心がけること。しっかりと交通ルールを守りましょう。 1-2. お住まい地域の道路交通法施行細則をチェック 基本は、冒頭でお伝えしたように「おんぶ」であれば自転車の同乗が認められています。しかし、道路交通法は地域によって規定が少し変わっている場合や変更されることもあります。...
夏に快適なメッシュ抱っこ紐10選!選び方のポイントと暑さ対策体験談
陽射しが照り注ぐまるで夏のような日。 いつものように抱っこ紐で買い物に出かけた時、ふと真夏への不安が頭をよぎりませんか? 「今これだけ暑いのに、この抱っこ紐で真夏はどうなるの?」「真夏の抱っこ、暑さ対策はみんなどうしてるの?」 その抱っこ紐、暑すぎですよね?! 真夏日は外出を控えるのが賢明ではありますが、予防接種や家族の用事、ましてやワンオペのママや車を持たないご家庭では、赤ちゃんを抱っこして外出せざるを得ない状況も多々あることと思います。 では、抱っこ紐で夏場をのりきる方法にはどんな手段があるのでしょうか? まず、重要なのは抱っこ紐選び。既にお持ちの抱っこ紐が暑すぎると感じる方は、夏用を用意することをおすすめします。これから抱っこ紐の導入をされる方は、一年を通して快適に使えるものを選ぶなど、機能性に注目してみましょう。 ここでは、どんな機能の抱っこ紐だったら暑さをしのげるか、夏用抱っこ紐の選び方のポイントを解説、通気性に優れたおすすめ抱っこ紐をタイプ別に紹介していきます。また、夏を経験した先輩ママに聞いた、夏場の暑さ対策も合わせて紹介しますので、是非参考にして下さい。 夏の赤ちゃんとのお出かけが少しでも快適なるよう、この記事が役に立てたら嬉しく思います。是非最後までお付き合いくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 夏用抱っこ紐選びで知っておきたい3つのポイント 夏場の外出、日が高いうちに出かけるのは、赤ちゃんにもママにも負担が大きくなります。時間帯を調整できるのであれば、できるだけ涼しい時間帯を選ぶことも重要です。とはいっても、通院や上の子の都合などでどうしても赤ちゃんを連れていかなければならない時はありますよね。 そんな夏場の外出に使う抱っこ紐は、蒸れを防止する通気性のよいもの、吸汗・速乾性のある素材、着脱のしやすさなど機能性に注目して選ぶことが重要です。まずは、夏用の抱っこ紐選びのポイントを3つ観点から解説していきます。このポイントをしっかり押さえれば、夏場の抱っこはかなり快適になりますので、是非参考にしてくださいね。 1-1. 通気性の良いメッシュ素材で蒸れを防ぐ 夏用として、通気性の高い素材を選ぶと快適度もぐっとアップします。特に、汗っかきの赤ちゃんにとっても抱っこするママパパにとってもメッシュ素材ならベタつきを感じにくく、サラッとした清涼感を保つことができます。 夏場だけでなく、実は汗ばむことは一年を通して多々あります。暖房の効いた屋内で厚着をしているといつの間にか汗びっしょりになっていることも。通気性がよくムレにくい素材を使っているかどうかも、抱っこ紐選びの大事なポイントです。 1-2. 速乾性のある素材でいつも清潔を保つ 夏日のお出かけから帰ってきた時に、抱っこ紐が汗で湿っているときがあります。自分と赤ちゃんの汗、よだれやミルクの吐き戻しなど、見えない汚れも付いてきます。 そんな時、洗濯機で丸洗いできる抱っこ紐なら気軽に洗うこともできて安心。いつも清潔を保つことができます。また、速乾性にも注目!お手入れのしやすさも重要なポイントです。 1-3. 抱っこの着脱が楽なタイプ 装着が面倒というのは抱っこ紐を使用する上で多く聞かれる悩みです。ひとりでは脱着しづらかったり、時間がかかったりする抱っこ紐はそれだけでストレスになります。汗ばむ夏場に、着脱に時間がかかってしまうのはママにも赤ちゃんにも大きな負担になってしまうことも。 誰でも簡単に装着でき、体格差を想定したサイズ調整のしやすい抱っこ紐を選ぶ、また、思い切ってママ用とパパ用を用意するなど、使い勝手のよいもの、ご家庭に合ったよい方法を選びましょう。 2. 【タイプ別】使い勝手のいい夏用抱っこ紐厳選10選! 筆者おすすめの夏に浸かってほしい抱っこ紐を、キャリータイプとスリングなどのタイプ別に紹介します。各商品の特長も解説していきますので、商品選びの参考にしてくださいね。 2-1. 夏もメッシュ素材で快適!万能キャリータイプ ベビーキャリアMINI Air【ベビービョルン】 ベビーキャリーミニ 81tDPcPgE5L._AC_SL1500_ 81cj4gJ1oxL._AC_SL1500_...
三輪ベビーカーは驚くほどスムーズに走る!絶対に見てほしい検証動画
三輪ベビーカーは、四輪ベビーカーと比べてスタイリッシュなデザインが多く、見るたびに羨ましく思う人も多いかと思います。 三輪ベビーカーを押しているママやパパの姿を見かけると、赤ちゃんとの時間を優雅に過ごしている印象があって、子育て楽しそうだなぁと明るい気持ちになります。 数年前まではあまり見かけなかった三輪タイプのベビーカーですが、最近街中で見かける機会が増えたなと感じます。しかし、主流はまだまだ四輪ベビーカーです。 思わず目を引くベビーカーにも関わらず、なぜ三輪ベビーカーを使う人があまり多くないのでしょうか? 見た目から憧れを抱く三輪ベビーカーですが、「値段が高い」「重い」「デカい」というイメージが大きく、コンパクトで軽量な四輪ベビーカーが使いやすいとはじめから思い込んでしまう人が多いのです。そのため、ベビーカー購入検討の時点で三輪ベビーカーは早々に除外されてしまいます。 確かに、日本の住環境、生活環境を考えると場所によっては四輪ベビーカーが使いやすいと思います。 しかし、『軽いもの=使いやすい』というイメージは間違っていることをここで断言します。 軽量タイプの四輪ベビーカーは、タイヤが小型で構造も簡素化され、走行性能よりも軽量化を重視されているために、実は、それが「使いにくさにつながる」原因でもあります。 四輪ベビーカーを使用した経験のある方からは、 「道の段差が越えにくい、つまずく」 「タイヤが溝にハマりやすい」 「移動中の走行音がうるさい」 といった感想をよく聞きます。 筆者も初めての育児の時にA型四輪ベビーカーを使用していたので同じことを思いました。 『段差が越えにくい』というのも5~6㎝の段差ではなく、2~3㎝のほんのわずかな段差です。 「あーもう、なんでこんな段差で引っ掛かるの。」と思ったことは何度もあります。 一番困ったのはベビーカーで横断歩道を渡る時でした。 歩道に乗り上げる際、段差でつまずき「信号が赤になる!どうしよう!」とヒヤヒヤしました。せっかくの楽しい外出が、移動中の障害によって帰宅するころにはストレスいっぱいでぐったり。 軽量化が重視されているために不便を感じることもあるのが現実です。私はそう思いました。 対して、三輪ベビーカーは構造にもこだわった大型のゴムタイヤを採用し、走行性能が重視されています。 四輪ベビーカーでは引っ掛かってしまう2~3cmほどの段差も三輪ベビーカーなら軽々乗り越えることができますし、ガタガタ道でもスムーズにスイスイ進むことができます。 三輪ベビーカーの『重さ』にはちゃんと理由があるのです。 四輪ベビーカーの『軽量』という魅力が強い分、三輪ベビーカーの良さは見落とされてしまっているように感じます。 「値段が高い」「重い」「デカい」とマイナーイメージが強く、敬遠されがちな三輪ベビーカーですが、ここでは三輪ベビーカーの良さを最大限にアピールさせていただきます! 三輪ベビーカーは機能が充実しているのはもちろんですが、おしゃれで多種多様なモデルがあることも魅力の一つ。豊富なデザインからベビーカーを選ぶ楽しみも増え、ますます赤ちゃんとの外出が待ち遠しくなること間違いなしです。 皆様のベビーカー選びの参考になればと思います。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 三輪ベビーカーが段差や悪路に強い4つの理由 三輪ベビーカーの最大の魅力は、なんと言っても走行性・操作性が優れていることです。 四輪ベビーカーでは押しづらいこんなジャリ道やデコボコ道でもスイスイ進むことができます。...