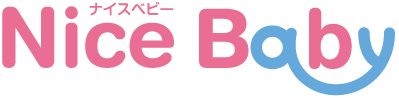ベビー用品
エルゴ抱っこ紐を徹底解説!新生児から使える秘密と賢い使い分け方法
抱っこ紐の購入検討で、ほとんどの人の候補に上がると言っても過言ではないエルゴベビー。街中で見かける抱っこ紐のエルゴ率はかなり高いですよね。 高評価のポイントは「機能性が高い」ということ。立体縫製で正しい自然な座り姿勢を保ち、赤ちゃんのカラダへの負担を軽減。厚みのある肩ベルトやしっかりとした腰サポートベルトで、赤ちゃんの重さによるママパパの体の負担を軽減させることができます。また、長期間に渡り使用できるという点も人気の理由のひとつです。 エルゴと言ってイメージされるのは、よく見かけるがっちりした腰ベルトの多機能型タイプだと思いますが、「新生児から使えるのかな?」と疑問を持たれる方も多いかもしれません。 エルゴの数種類ある抱っこ紐は、どれも新生児期から使用することができます。 みなさんご存知の多機能タイプの他に、実は、新生児期に特化したタイプがあるのことをご存じでしょうか? 2020年4月より販売された、その名も「エンブレース」。エルゴ抱っこ紐のスタンダードな多機能型タイプより、認知度こそまだ低いですが、使用したママたちからは「特化してるだけあると納得!」と絶賛の声があがる満足度の高い、今、注目の抱っこ紐なのです。 ここでは、エルゴ抱っこ紐の新生児期の使用に着目し「多機能タイプ」と「エンブレース」の特徴について、それぞれのメリット・デメリットを含めて詳しく解説していきます。後半ではおすすめのエルゴ抱っこ紐の買い替えパターンや知ってトクする情報も紹介していきます。 こちらの記事をお読み頂ければ、エルゴ抱っこ紐の機能や上手な使い方をしっかりとマスターすることができます。新生児期でも不安なく抱っこ紐を使用するために、失敗のない商品選びを実現するために、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。 1. 不動の人気!エルゴの抱っこ紐は全3種類 商品 アダプト&オムニ360 エンブレース 月齢 新生児~4歳頃 新生児~12カ月頃 体重 3.2~20kg 3.2~11.3kg メリット ・新生児期から長期間使用できる ・両肩と腰でしっかりサポート、体への負担を軽減 ・新生児特化型で安心の密着抱っこ ・着脱が簡単 デメリット ・新生児にはサイズが大きい場合あり ・価格が高い ・着脱が複雑 ・12カ月頃までしか使用できない エルゴベビー抱っこ紐は全3種類。 エルゴの抱っこ紐と言えば、街中でよく見かけるがっちりとした多機能タイプの「アダプト、オムニ360」を思い浮かべる方がほとんどだと思います。...
新生児期の外出に最適!ママパパが安心して使える抱っこ紐厳選8選!
新生児期の小さい赤ちゃんの抱っこ紐をお探しでしょうか? 「抱っこ紐は新生児も使えるの?」「新生児期から安心して使える抱っこ紐は?」 赤ちゃんを迎えるために抱っこ紐選びを始めたママパパが、ふと抱く疑問かもしれません。抱っこ紐は育児の必須アイテムと言えますが、新生児用から使えるものとなると本当に必要か悩みますよね。 一般的に生後1ヵ月頃までは、家の中で赤ちゃんのお世話をします。1ヵ月検診で外出許可が出るまでは、ほとんど外出することはないため、お出かけ目的としての抱っこ紐の必要性は低いと考えます。しかし、抱っこ紐の使用は外出のみではありません。それぞれの家庭環境によって、新生児期の抱っこ紐が必要なケースもでてきます。 例えば、 ●家の中で寝かしつけに使いたい場合 ●1ヵ月健診で病院に行く場合 ●家族のお世話や送迎で一緒に外出する場合 など。 新生児期の抱っこ紐の使用は、寝かしつけや家事の際など、家の中で上手に活用するととても便利なアイテムです。ただし、首の座らない赤ちゃんを安心して抱っこできる機能が備わっていることが大切。最近では、各メーカーから首座り前の赤ちゃんを安全に抱っこするために作られた機能的な商品が多く販売されています。 そこで今回は、二児の子育て経験を踏まえて、筆者の私が今注目の新生児から使える抱っこ紐を紹介していきます。安全に安心して使えることを第一におすすめの8商品を厳選しました。 購入する際は、ご自身の使用用途に合うアイテムを選ぶこと、そして使用前は取扱説明書や動画をよく確認して何度も練習をしてから赤ちゃんを抱っこすることを忘れずに! あっという間に過ぎ去ってしまう新生児期。小さい赤ちゃんのにおいやぬくもりを感じるスキンシップは期間限定の特別な時間です。是非ご家族で大切に過ごしていただきたいと思います。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 新生児から安心して使える抱っこ紐4つの種類と特徴 はじめに、新生児対応抱っこ紐の主な4種類とそれぞれの特徴について解説します。 小さな赤ちゃんの抱っこを安全に、安心して使えるさまざまな抱っこ紐が各メーカーから販売されています。 たくさんのママパパの声を聞いて研究を重ね開発された、どれも機能性に優れた素晴らしい商品です。タイプとしては主に4種類に分かれます。機能もデザインも全く異なりますので、まずは、種類ごとの特徴の違いを知って、ご自身の生活スタイルにはどのタイプが合うのか、抱っこ紐選びのヒントにしてください。 1-1. 両肩ホールドで両手が空くベビーラップ ベビーラップとは、幅の広い長さのある布をぐるぐる巻き付けて使用します。その特長は、自由度が高く様々な抱っこスタイルが実現できることと、使う人の体格を選ばないこと。ただし、使いこなすにはかなり練習が必要なため、使いたくても二の足を踏む方も多いようです。そこで最近人気なのが、Tシャツを着るようにかぶるタイプのベビーラップ。サイズバリエーションも豊富で体格に合わせて選ぶことでできます。Tシャツのようでありながら、長さの調整もできる折衷タイプなども登場し注目を集めています。 使い方は異なるものの、ベビーラップの最大のメリットは胸元で赤ちゃんをしっかりとホールドできること。両肩と背中で赤ちゃんの体重を分散するため、長時間抱っこをしていても疲れにくい構造です。また、柔らかな布が赤ちゃんにも産後間もないママの体にも負担をかけずに優しくフィットする使いやすさも人気の理由です。 1-2. 柔らかい布で密着抱っこできるベビースリングタイプ ママパパと赤ちゃんの体がぴったりフィットしやすく肌に優しい布でできたベビースリングは、生後2週間頃からの新生児抱っこにおすすめです。うまく上手に扱えるまでは、何度も練習しましょう。安全に使うコツを掴んだら、抱き上げたり抱きおろしたりするときも短時間に抱っこができます。様々な抱っこバリエーションも実現できるので、成長に合わせて抱き方を変えて使うことができます。Wリング調節のタイプならママとパパ兼用で長い期間使うことも可能です。 スリングは片方の肩にかけてたすき状で使うものがほとんどです。毎回同じ方の肩ばかりでは肩を痛めてしまうこともあるので、毎回違う方の肩にかけるようにしましょう。 1-3. ヘッドサポートが安心できるベビーキャリータイプ 首のすわらない赤ちゃんの頭や首を支えてくれるサポートがついているベビーキャリーは、ママと赤ちゃんの距離が近くなるように設計された抱っこ紐です。腰ベルトの高さや肩ベルトを体に合わせて調節して正しく装着すれば、体にかかる重さが分散されて、抱っこの時間が長いときなどに重宝します。長く使える縦抱きのベビーキャリータイプは、ママとパパで兼用しやすいため人気が高い抱っこ紐。1つ持っているととても便利です。 3歳頃まで長く使えるタイプの場合、新生児期には大きすぎる傾向がありますが、最近では、新生児期に特化した機能のキャリータイプも登場し注目を集めています。新生児の小さな体でもぴったりフィットし、抜群の密着感を得ることができ、構造もシンプルで着脱しやすい点も魅力です。 1-4. 横抱きできる多機能ベビーキャリータイプ 抱き方は、「対面」「前向き」「おんぶ」「横抱き」の4種類対応している多機能な抱っこ紐は、一つあれば、長く使えて便利な抱っこ紐です。特に、横抱きで安定した姿勢を保つことができるサポートクッションシートがついているので、初めてでも安心して抱っこすることができます。 用途によって使い分けられるメリットも多いですが、横抱きのセッティングに時間がかかることがあるため事前に練習しましょう。特に、新生児期に横抱き使用が数回だけという方にはおすすめです。 2. 筆者厳選!新生児から使えるおすすめの抱っこ紐8選!...
上の子のお世話が忙しい!二人目新生児から使える抱っこ紐4つの条件
第二子、三子の出産準備は、一人目の時とは少し状況が異なってきます。既にベビー用品は色々とあるものの、2人の子育てを同時進行させるために必要なものも出てきます。 「抱っこ紐」もそのうちのひとつ。 お子さんのいるご家庭なら必ず一つは持っていることと思いますが、第一子の時に準備した抱っこ紐は、長期間使える多機能タイプが多いのではないでしょうか。絶賛使用中の方も多いですよね。多機能タイプはとても便利でひとつは持っておきたいですが、大きくなっても使える分、新生児は向かないことも多いのがネック。新生児から使用可能と記載はあっても、実際には大きすぎたり、着脱に不便だったり...。 一人目の時は多少大きくても使っていた経験があっても、二人目三人目となると状況は変わってきます。上の子のお世話をしながら新生児を抱っこする場合、ママの意識は赤ちゃんだけに集中させることは不可能。むしろ、上の子に気がいってしまうことが多々あります。その状況で安定感のない抱っこ紐で新生児を抱っこするのはとっても危険。上の子のお世話をしながらでも安心して使える、新生児に特化した機能を持つ抱っこ紐が必要不可欠です。 実は筆者の私も、上の子が1歳8ヵ月の時に第二子を出産しました。1歳8ヵ月というと一番目の離せない手のかかる頃。首の座らない赤ちゃんを抱っこしている時も、常に上の子の動きを監視している状態でした。赤ちゃんのお世話しながら家事をこなし、上の子の遊び相手もしつつ、予防接種や健診の通院、日常の買い物など2人連れての外出、一日は24時間では足りないくらい目まぐるしく毎日が過ぎていきました。 そんな日々で活躍したのが、新生児をしっかりホールドできる抱っこ紐でした。私はベビースリングを使用していたのですが、常に赤ちゃんが胸元にピタッとくっついているのでとても安心できました。上の子に気がいってしまっても赤ちゃんに不安を感じることもなく、家の中でも外出時でも大活躍しました。 その頃は、新生児特化型の抱っこ紐はバリエーションがなくスリングが人気でしたが、今は、各メーカーから新生児機能にフォーカスした優秀な抱っこ紐がたくさん開発されています。「これ使いたかったー!」と言わずにはいられない魅力的な抱っこ紐ばかりです。 そこで今回は、上の子のお世話をしながら、という絶対的な条件を前提に、新生児に安心して使える抱っこ紐を、私の経験を踏まえ厳選した抱っこ紐を紹介したいと思います。 第二子、三子の新生児期に使う抱っこ紐の条件、先輩ママたちの体験談なども合わせて紹介していきますので、抱っこ紐選びの参考にしてくださいね。 息つく暇もない毎日のママに、少しでも負担が軽減できて、そして安心できる子育て環境づくりに、この記事が役立てていただければ嬉しいです。是非最後までお付き合いください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 上の子のお世話と両立!新生児用抱っこ紐4つの条件 家事と育児を両立させるためにも、首のすわらない赤ちゃんと一緒に安全に移動できる抱っこ紐は必須です。荷物をもって上の子と手をつないで、赤ちゃんを抱っこするシチュエーションが多々ある生活では、小さな赤ちゃんを優しくしっかりとホールドでき、安定感のある抱っこ紐がおすすめ。 この章では、上の子のお世話に手がかかる忙しいママに選んでほしい抱っこ紐の4つの条件を解説していきます。 1-1. ママパパの両手がフリーになる抱っこ紐 一人目の赤ちゃんの時より、新生児期から外に行く機会が増えることが予想されます。とにかく両手が少しでもフリーにできる抱っこ紐がおすすめです。上の子の保育園や幼稚園の送り迎えも、赤ちゃんが一緒でも身軽に動けて便利です。手をつながないといけない上の子がいる場合、荷物をもったりお財布を出し入れしたりする時も片手では大変です。同時にあれやこれやと大忙しのママパパには両手が空くことは最重要です。 1-2. 抱っこ紐の装着が簡単にできる 首のすわらない赤ちゃんを抱っこする時はちょっとドキドキしますよね。 脱着に手間のかかる抱っこ紐は、新生児に使用するには何かと不安が大きいもの。首の座らない赤ちゃんを不安定な状態で抱くのは危険性が高く、また、装着時には上の子の手を離すことにもなるため、安全の確保のためにはスピーディーな脱着は必須です。できるだけ簡単に付けはずしのできる抱っこ紐を選びましょう。 1-3. しっかり密着!安定感のある姿勢でホールドできる 木にしがみつくコアラのようにしっかり密着する抱っこ姿勢なら、ホールド感は抜群です。姿勢が崩れにくい安定した抱っこは、赤ちゃんがすぐに寝てくれる効果も。横抱きのように、支えとして片腕が必要な抱っこ紐だと、上の子のとっさの動きに反応することができないことも考えられます。安定した密着感がある抱っこ紐であることも重要な要素です。 1-4. 抱っこ紐の持ち運びが楽にできるコンパクトタイプ コンパクトになってバックに入れられる大きさのものなら、使わない時にかさばらず便利です。二人三人分の荷物を持たなければならない事を考えると、コンパクトになる抱っこ紐は必須条件です。最近では、抱っこ紐を収納するための専用バッグ付属の便利な商品も多く出ています。 2. 4つの条件を満たした抱っこ紐はコレ!新生児用抱っこ紐おすすめ4選! 前章で解説した4つの条件をクリアし、新生児期の小さい赤ちゃんがぴったりママパパにくっついてフィット感を重視したベビー専用の抱っこ紐を厳選して紹介します!着け心地や感動ポイントは、それぞれ高評価の商品ラインナップとなっています。一人目に使っていた抱っこ紐とは、異なるタイプで使い分けを楽しんでみて下さいね。では、早速チェックしていきましょう。 2-1. 口コミ高評価!ぐっすり抱っこ紐【コニー】 使用月齢 新生児~36ヵ月(体重20kgまで) 素材 【オリジナル】ポリエステル62%・コットン33%・ポリウレタン5%...
『子育て本音トーク vol.10』使ってみた!ベビーチェア・授乳チェア編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第10弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第10弾は「ベビーチェア・授乳チェア」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「今回はベビーチェア・授乳チェア編です。ベビーチェア4種類と授乳チェア2種を使っていただきました。」 ととママ「ベビーチェアはお気に入りの1つを今でも引き続き使ってますよ!」 あゆなママ「お子さんはよく食べますか?」 ととママ「うちの子たちはみんなよく食べます!下の子も自分で食べるようになったし、ベビーチェアは大活躍です。」 あゆなママ「お食事も作り甲斐がありそうですね~(笑)実際にまだ使われてるチェアもあるそうなので、このあと詳しく聞かせてくださいね!」 ととママ「「はい!授乳チェアもとってもよかったので、そのことも色々とお伝えしますね。」 あゆなママ「是非是非!今回もリアルな体験談たっぷりと聞かせて下さいね!」 1. 授乳チェア2種類を使ってみた! 全てのサイズが授乳ポジションのために設計されてる あゆなママ「では、まずは授乳チェアからお話を伺っていきますね。一般的に授乳チェアは外出先の授乳室もあるもの、というイメージですよね。」 ととママ「そうですよね。実は今回使ったエンジェルチェアは、一番上の子が生まれた頃から私、知ってました。授乳室で座り心地や授乳のしやすさは体感していて、授乳室で見かけると「あった!」って感じで嬉しかったのを覚えてます。」 あゆなママ「授乳室の王道チェアですよね。授乳チェアだとクッションいらないし、妙に授乳しやすいって、日本中のママが感じてることかもしれませんね~。」 ととママ「何で授乳が楽なんだろう?って思ってるママ!それは、エンジェルチェアだからですよ!(笑)」 あゆなママ「その魔法の椅子が家で使えるって、どうですか?」 ととママ「サイコーでした!本当に良かった!授乳室で体感したママ達、是非、レンタルしてください!」 あゆなママ「普通の椅子だと、この楽さは体感できないじゃないですか。その違いって何だと思います?」 ととママ「全てのサイズが授乳ポジションのために設計されてる。椅子の高さ、ひじ掛け、深く座れて背もたれの感じも。全てが授乳に完璧!」 あゆなママ「授乳姿勢で不調を訴えるママも多いですよね。」 ととママ「不調になる前に絶対使ってほしい!腰、腕、首、肩、全てが楽!授乳はエンジェルチェアじゃないとダメ!というくらいになってましたよ、私。」 あゆなママ「授乳以外で使ってましたか?」 ととママ「寝かしつけた後にエンジェルチェアで休憩してました。ひじ掛けもあるし、一人でのんびり座るのにもすごく良かったです。」 あゆなママ「サイズがちょっと大きいかな?とも感じるのですが、実際家の中に置くとどうでしたか?」 ととママ「さほど違和感はなかったですよ。リビングの隅に置いてたんですが、むしろ、授乳専用の空間ができてよかったです。上の子たちにもママ専用の場所という認識があって、聖域的な(笑)」 あゆなママ「産後は使うべきママグッズでしょうか?」 ととママ「一押しです!授乳終わるまでの期間は家にあるとすごくいいと思います。授乳はしてなけど、今でもほしいくらい(笑)とにかく座り心地がいいんですよ。」 あゆなママ「エンジェルチェアの詳しい記事も公開されているので、下にリンクはっておきましょう。みなさん、是非読んでくださいね!」 ▼...
『子育て本音トーク vol.9』使ってみた!おもちゃ編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第9弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第9弾は「おもちゃル」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 たばち「今回はおもちゃ編です。全部で5種類を使って頂きましたが、赤ちゃん用とお兄ちゃんたち用でレンタルされたそうですね。」 ととママ「そうなんです。赤ちゃん用でレンタルしたのに、上の子たちが遊んでたりもしてましたけど(笑)」 たばち「お子さんたちがみんな楽しめるって素敵ですね!お子さんたちの楽しめたポイントやママとして役立ったことなども色々聞かせていただきたいと思います。」 ととママ「おもちゃに対する興味から子供の成長も見ることができて、おもちゃなんだけどそれだけじゃないと感じたこともあるので、商品と一緒にお話していきますね!」 たばち「それは楽しみです!これからおもちゃ導入を検討してるママ達にもいいお話をお伝えできそうですね!」 1. プレイジムを使ってみた! 子供が自ら考えて遊ぶようになっていました たばち「では、まず最初はプレイジムからお話を伺っていきますね。使っていただいたのは、『はらぺこあおむし アクティビティプレイジム』と『ジミニー・ムーブ&プレイ』の2つでしたね。」 ととママ「上の子たちに使ってたベッドメリーは持っているので、プレイジムを使ってみたかったんですよ。気分転換に遊ばせてあげらるし、前からいいな~と思ってました。」 たばち「いつ頃から使い始めたのですか?」 ととママ「生後1ヵ月頃から1歳頃まで。最初は、はらぺこあおむしを使って、そのあとはジミニーを使いました。」 たばち「どんなタイミングで使っていましたか?」 ととママ「赤ちゃんの機嫌がいい時に、プレイマットにゴロンとさせて遊ばせてました。生後1ヵ月の頃は無反応だったんですけど、2ヵ月頃から音に反応したりキョロキョロするようになってきて、自ら興味を持ちだしたのは3ヵ月頃だったかな。」 たばち「ちょっとの間で赤ちゃんの反応も変わって、成長が見られるのっていいですね!」 ととママ「カラフルだし、動いたり音が鳴ったり、子供には刺激になってすごくよかったと思います。」 たばち「おむつ替えやマットだけで遊ばせるなどでも使いましたか?」 ととママ「おむつ替えの時は便利でした!寝かせるとじっとしてなくておむつ替えが大変になってきた頃は、プレイマットの上だとおもちゃがあるので、上を向いたままの体勢でいてくれるんですよ(笑) たばち「それは効果抜群ですね!目の前に楽しそうなものがあればうつ伏せになったりしないですよね(笑)」 ととママ「あと、上の子たちが一緒に寝転んで遊んでたり、子供たち同士で工夫して遊んでくれてました。」 たばち「お兄ちゃん達も楽しめるなら一石二鳥!ママとしては大助かりですね!」 ととママ「ジミニーは真ん中のおもちゃが音楽が鳴るのでとても気に入ってました。自分で引っ張って音を鳴らすとか、子供が自ら考えて遊ぶようになっていました。」 たばち「単純におもちゃが付いてるマットなだけじゃなくて、学び要素のある知育玩具なんですね。」 2. ジャンパルーを使ってみた! ぴょんぴょんジャンプしてすごかったですよ たばち「こちらのジャンパルーですが、ナイスベビーではレンタルの予約待ちになることもよくある人気商品です。」 ととママ「人気ですよね~。だって見るからに楽しそう!私のように使ってみたいって思うママは多いと思いますよ。」...
最大の魅力は寝かしつけ!新生児におすすめしたいベビースリング7選!
この記事をご覧の方は、小さい赤ちゃんにも使えるベビースリングをお探しでしょうか。 生まれてすぐの赤ちゃんの体重は3000g前後。とっても小さくてふにゃふにゃの体を抱っこする時は、本当に気を使いますよね。慣れない抱っこをし続けると手首や腕、肩にも負荷がかかり、けんしょう炎や肩こりなどの不調を訴えるママも多くいます。 実は、筆者本人もその経験者のひとり。 生後2週間ほど経ったころ、どうあやしても夜泣きが止まらず3時間以上も続いたことがありました。その時は、腕だけで抱っこして、部屋の中をゆらゆらぐるぐる。よし、寝た!と思い布団におろすと目をばちっと開く、の繰り返し。そして、またゆらゆらぐるぐる・・・。もう腕はパンパンで、どうしたらいいかわからないまま、ただただ時間だけが過ぎていく感覚。体力の限界に達したとき、赤ちゃんと一緒に号泣したのは一生忘れない思い出です(笑) ちょうどそのころ、ベビースリングを紹介しているテレビ番組をみて、藁にもすがる思いで購入しました。はじめて扱うベビースリングは、何度も動画を見て使い方を繰り返し練習。いざ、使ってみると片腕は自由になり体は楽、赤ちゃんが自分の胸にピッタリくっついているせいか、あっという間に寝かしつけにも成功!それから抱っこの時は、ベビースリングをメインで使うようになりました。 特に、授乳回数の多い新生児の時、ベビースリングの布が目隠しにもなって、外出先でもバレずに授乳をすることができたのはとても便利でした。この時期に、ベビースリングに出会えて本当に良かったと思っています! ここでは、筆者の体験をもとに、新生児期に使うベビースリングの魅力と成長時期に応じた抱っこパターンについて詳しく解説していきます。 また、育児スタイルにあわせて選べるように、パパと共有できる兼用タイプと自分サイズの専用タイプに分けて、おすすめ商品を厳選して紹介します。 ベビースリングをうまく活用すれば、必ず赤ちゃんとの生活がグッとラクに楽しくなっていきます。肌と肌を密着できる抱っこは、期間限定の本当に尊いひとときです。たくさん抱っこしてあげましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 新生児期のベビースリング3つの魅力! ベビースリングは、幅の広い布でハンモックのような形で赤ちゃんを包み込むように抱っこします。一般的に生後2週間頃から使うことができます。ママパパと赤ちゃんの密着度が高く、成長に合わせた抱き方のバリエーションも豊富。洗濯しやすくてコンパクトにたためるから、持ち運びにも便利です。まずはじめに、ベビースリングの魅力について解説していきますね。 1-1. ママパパの片腕がフリーになる! 授乳の回数や抱っこで寝かしつけすることが多い新生児期は、慣れない抱っこでけんしょう炎になってしまうという話もよく聞く話です。特に、首のすわっていない赤ちゃんの抱っこには気を遣うので、腕だけでなく腰や肩にも負荷がかかります。 ベビースリングがあれば、ママパパの片手を自由にすることができるので、簡単な家事や飲食することもできます。ママパパの食事の時間に赤ちゃんがぐずり始めてしまった時、サッと抱っこできるのもベビースリングの魅力です。 1-2. おなかの中にいたころのCカーブで入眠しやすい! 赤ちゃんの身体の成長とともに、背骨のCカーブは、大人と同じ二足歩行ができるころに、S字カーブに変形していきます。ママのおなかの中にいたころと同じCカーブが入眠しやすいリラックスできる姿勢です。ベビースリングの中は、赤ちゃんにとって1番安心できる居心地のいい場所に感じているようです。 1-3. 寝かしつけ後の布団への誘導がスムーズ! 赤ちゃんをベビースリング抱っこで寝かしつけした後、赤ちゃんの「背中スイッチ」を押さずに布団におろしてあげることができます。ベビースリングの中に赤ちゃんが入ったままの状態で布団に寝かせ、ベビースリングからママパパが体をスルーッと抜けば、そのまま寝入ってくれることも多いです。ぐずるようなら、ぐっすり寝入るまで赤ちゃんのおなかに手を添えてあげて、タオルケットなどをかけてあげるのもおすすめです。はじめはうまくいかないこともありますが、繰り返していくうちにスムーズにお布団でねんねさせることができるようになりますよ。 あわせて読みたい! 背中スイッチ攻略法!効果絶大な先輩ママの対策事例とグッズ活用術! 授乳や抱っこでスヤスヤ腕の中で眠る赤ちゃん。ようやく寝かしつけに成功して布団の上に寝かせた途端、起きて泣き出してしまう。まるで背中に起動ボタンが付いているかのように、布団に置くと起きてしまうこの現... ナイスベビーラボ 2. 成長に応じたベビースリングの抱き方6つのバリエーション 抱っこひもは、メーカーやブランドによって抱き方の種類が異なるため、必ず対象月齢を確認し、成長段階にあったもの選ぶようにしましょう。購入商品の取扱説明書をしっかり読んで、抱っこしてくださいね。筆者体験談も合わせて解説していきます。 2-1. 基本抱き(新生児~) ママと向かい合わせになり、顔を見合わすことができる「基本抱き」は新生児にピッタリな抱き方です。首のすわらないころは、必ず手を添え姿勢や顔色を確認しながら使用しましょう。赤ちゃんのおでこにキスできる高さをキープして、赤ちゃんの膝をおしりより高くするのがポイントです。 筆者体験談 はじめての子育て、赤ちゃんの新生児期に慣れない抱っこでけんしょう炎を発症。ベビースリングの本を購入し、とにかく腕が楽になれば、との思いで「基本抱き」を何度も何度も練習しました。ベビースリングの構造を理解してから、実際に赤ちゃんを抱っこして寝かしつけを始めました。すると、赤ちゃんが肌に密着して安心できるからか驚くほどすぐに寝入ってくれたので、腕も身体もとてもラクに!けんしょう炎も治って楽しく抱っこができるようになりました。 2-2. 寄り添い抱き(首がすわったころ~3歳くらいまで)...
スマホで自在に操作!凄すぎると話題のバウンサーママルー人気の理由
ベッドに寝かせた途端に泣き出す、背中スイッチが敏感な赤ちゃん。寝かしつけや家事の時に赤ちゃんが心地よくいてくれる場所として、バウンサーはとても重宝するアイテムです。 そのバウンサーの中で、今話題となっているのが電動タイプのバウンサー『ママルー』。最先端のテクノロジーを駆使した多機能搭載で、赤ちゃんをしっかりとあやしてくれるママパパの心強いサポーターです。優れた機能と共に注目されているのが、おしゃれなビジュアル!SNSでもたくさんの素敵な写真が投稿されていることからも、その話題性の高さがうかがえます。 機能よし!見た目よし!そんな『ママルー』の人気の秘密に迫るべく、隅から隅までしっかりと調査しました。機能紹介と合わせて実際に触ってみて気がついた点、リアルな口コミ情報、ママルーに寄せられるよくある質問、ママルーをお得に使える裏技まで、ママルーの魅力を余すところなく解説します! これを読めば全てがわかるママルー解説の完全版です!ママルーが気になっているママパパは最後まで是非読み進めてくださいね。その魅力がしっかりとわかるはずです! それでは早速みていきましょう! 1. 最強のベビーシッター「ママルー」とは ママたちの間で絶大な人気を誇る電動バウンサー「ママルー」 日本では芸能人が愛用したことによって一躍有名になりました。一般的に電動バウンサーは一定リズムで前後に揺れる機能のものがほとんど。ママルーの大きな特長として、ゆっくりと上下左右に弾みながら揺れる独特のリズムがあります。まるでママパパがあやしているかのような揺れを実現したことで、赤ちゃんはより深くリラックスできる効果があるとされています。 1-1. アメリカ発「4moms」が開発した電動バウンサー アメリカのピッツバーグ発ベビー用品にイノベーションを起こす「4moms」。 電動で揺れるベビーベッドや、注水と排水を自動化した電動ベビーバスなど、テクノロジー対応のベビー用品を開発しています。その中の代表的なアイテムが「ママルー」。デザイン性と実用性を兼ね備えたセレブ御用達アイテムです。 1-2. アメリカの病院約300以上で使用される信頼性 ママルーは抱っこされているような振動で赤ちゃんを落ち着かせてくれる電動のゆりかごのようなもの。新生児から使用できることもあり、発祥地アメリカでは、約300以上もの病院で使用されるほどの信頼性の高い優れたアイテムなのです。 2. ここが凄い!ママルー4.0の機能 ここでは、最新モデル「ママルー4.0」の優れた機能を紹介します。他の電動バウンサーにはないママルーならではの機能を8つのポイントにまとめて解説していきます。 2-1. ママのあやす動作を再現した5つのモーション 車の動き、8の字を描く 木の動き、横を高く真ん中を低く 波の動き、大きな円を描く 左右にゆらゆら カンガルーの動き 最大の特徴は、ママパパがあやしているかのような自然な動きを再現した5つのモーション。 デザイナーや医師、看護師など各分野の専門家の監修の元、実際にママパパにセンサーを付けて赤ちゃんをあやすときの動きを計測しました。そのような研究を重ねてつくられたのが現在の5つの動き。赤ちゃんはママルーで心地よくリラックスすることができます。 2-2. スマートフォンで遠隔操作ができる ママルーの特徴のひとつに「スマホで遠隔操作」ができる点が挙げられます。専用のアプリをiPhoneなどの対応機種から無料ダウンロードするだけで使用可能。動作・内蔵音の選択・音量の操作が可能なので、ちょっとキッチンに離れていてぐずった時でも、すぐママルーを操作できるからママは楽に家事が続けられますね。 2-3. 赤ちゃんを落ち着かす胎内音と4つのメロディ ママの胎内音 扇風機の音 雨音 波の音...
密着できて幸せ!ベビースリングおすすめ13選!正しく使うポイント解説
ベビースリングは、新生児から2~3歳の幼児まで手軽に使用できる抱っこひもとして人気の育児アイテム。布1枚で、赤ちゃんをすっぽり覆ってしっかりホールドします。日差しをさえぎったり、授乳の目隠しにしたり、使い方次第で幅広い用途で活躍します。また、コンパクトに折りたためるので持ち運びにもとっても便利!セカンド抱っこ紐としても人気のアイテムです。 筆者自身、第一子の生後1ヵ月のころ、慣れない抱っこでけんしょう炎になり、授乳や寝かしつけに限界を感じ始めていました。そんな時、ベビースリングを紹介していたテレビ番組でその魅力を知ることとなり、迷わず購入し使い始めるようになりました。 購入後は正しい抱っこの仕方の動画を何度もみて練習し、使い方を覚えました。基本抱きをマスターしたら、腰抱きにしたり、前向き抱っこにしたり、自由に抱っこができて、家の外でも中でも大活躍の手放せないアイテムとなっていきました。 ベビースリングの使い方は、コツさえつかんでしまえば簡単!はじめはうまくいかなくて、赤ちゃんが泣いてしまうかもしれませんが、慣れてしまえば大丈夫!ベビースリング販売店のYouTube動画などを活用すると、すんなりと抱っこできるようになりますよ。 ここでは、ベビースリングのタイプや素材、対象月齢などの選び方のポイントを紹介しています。さらに、ベビースリングを使う時に注意しなければならない点についても詳しく解説していますので参考にしてくださいね。誰が使うのか、どんなシーンで使うのかなどシチュエーションをイメージすると商品選びはスムーズになりますので、この記事を読みながら是非イメージもしてみてくださいね。 ママの心音が聞こえる空間は赤ちゃんにとって1番安心できる居心地のいい場所。包み込むスリングの中は、まるで大好きなママのおなかにいるよう。ママにとっても赤ちゃんにとっても、かけがえのない抱っこの幸せな時間をさらに楽しんでくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. タイプ別おすすめポイント!自分に合うスリングを選ぼう! べビースリングは、抱き方のバリエーションをマスターすれば、これ一つで便利に長く活躍してくれるアイテムです。 リングタイプやバックルタイプなど種類がいくつかありますので、それぞれの特徴を知って自分に合うスリングのタイプを選んでいきましょう。 ママ一人で使うのか、パパと共有するか、コンパクトになるものがいいかなど、使用シーンをイメージするとアイテム選びがスムーズになりますよ。では、早速みていきましょう! 1-1. コツをマスターすればどこでも楽々抱っこできる!『リングタイプ』 ☆こんな人におすすめ☆ ● ママとパパ一緒に共有したい ● 授乳ケープの代用としても使いたい ● コンパクトになるものがいい ● ファッションとしてベビースリングを取り入れたい 最も基本的なタイプ。端にリングがついた『リングスリング』は、ふたつのリングで1枚布の長さを調節して大きさや密着感を調整して使用します。使いこなすには、練習は必須!販売店の動画を見ながら抱っこの練習をしましょう。 筆者一押しは、こちらのリングタイプです。垂れ下がるテール部分が、授乳ケープ代わりになったり、エアコンの効いた室内でもサッと覆えるので、外出先や移動中にも大変便利です! 1-2. サイズ調節簡単!ママパパ一緒に使える『バックルタイプ』 ☆こんな人におすすめ☆ ● 簡単にサイズ調節できるものがいい ● 着脱が楽にできるものがいい ●...
育児が断然楽になった!移動式ベビーベッドは短期間でも使う価値あり
「ベビーベッドを使いたいけれど、置く場所どうしよう?置いたら邪魔になりそう…。」 「用意してもあまり使わなかったらコスパ悪いよね。」 ベビーベッドをこれから準備しようとしている方はこんな悩みに直面しているのではないでしょうか? 正直にお話をすると、筆者の私も1人目出産の時は同じことを考えていました。 「ベビーベッドって部屋に置いたら邪魔だし、短期間だったら我慢すれば何とかなる!」と思っていたのが事実です。 「あると便利だろうけど、なくてもなんとかなりそう。」そう考えたことが一番の決め手となり、ベビーベッドは使わずに育児を行うことにしました。 案の定、床でお世話は当たり前。 初めての育児で毎日必死な上、無理な体勢でのお世話を繰り返し、体への負担が知らず知らずたまっていたようです。 気付いた時にはすでに遅く、産後6ヵ月に人生初の『ぎっくり腰』を発症。散々な目にあいました。 あの時のことは、もうこりごり。とても後悔しています。 2人目からは考えを改めベビーベッドを使うことにし、大正解!! 身体への負担が軽減され、こんなにも違うのかと驚きました。 子供が増えることで、ますます体に負担がかかるのかと思いきやベビーベッドのおかげもあり、楽に育児をすることができました。もちろんぎっくり腰もなしです。 しかし『ベビーベッドを使うことで部屋が狭くなる』というのも事実。 そんな悩みを解消してくれるのが今回ご紹介する「移動式ベビーベッド」です! 私は、この「移動式ベビーベッド」を使って2人目、3人目と快適な育児を行うことができました。 赤ちゃんを安全な場所で寝かせてあげたい。 安心して育児をしたい。 ベビーベッドは使いたいけれど設置スペースが限られている。 自分の体に負担なく楽しく育児がしたい。 そんな方におすすめのベビーベッドです。 この記事を読み終わった後は、あなたにとって理想的なベビーベッドを選ぶことができるようになります。 これから始まる赤ちゃんとの生活がHAPPYになること間違いなしです! ぜひ参考にしていただければと思います。 1. 産後の育児が断然楽になる!コンパクトな移動式ベビーベッドをおすすめする3つの理由 ベビーベッドに寝るのは赤ちゃんだけれど、お世話をするのはママやパパ。 特にママは、出産という大きな仕事を終えて、体はヘトヘト。でも休む暇はありません。 少しでも育児が楽になれば、ママの体への負担は軽減します。 だからこそ、さまざまな種類がある中でコンパクトでなおかつ移動ができるタイプのベビーベッドをおすすめします。 第一章では、おすすめポイントを3つご紹介します。...
マットレスは必須!年間500台のベビーベッドを届けてわかったこと
これから生まれてくる赤ちゃんの為にベストな環境で寝かせてあげたい。 そのためには何を準備しなければならないのだろう? まずはじめに、頭に思い浮かぶものは寝具のベビーベッドとベビー布団ですよね。 ベビーベッドとベビー布団だけ用意すれば十分と考える方がほとんどだと思います。 でも、普段ママパパがベッドで寝る時は、快適に寝るためにマットレスを利用していますよね。 そう考えると快適な睡眠環境作るには「赤ちゃんにもマットレスは必要なのだろうか?」と疑問に感じませんか? お答えします。 ベビーベッドを使う際、マットレスは赤ちゃんにとって欠かせないアイテムです。 実は筆者の私は、以前までナイスベビーの配送スタッフとしてお客様宅にベビーベッドをお届けしていました。そのなかで実際に現場で見たものをお伝えします。 稀なケースではありますがレンタル品のベビーベッドや布団セットを引き取る際、ベビーベッドの床板の裏側や敷布団などにカビが付いて返却されることがありました。 おそらくその原因は、敷布団を長い間ベビーベッドに敷きっぱなしで使用されていたか、もしくは加湿器等で過度な湿度によりお部屋の環境が悪くなってカビが発生したものと思われます。そういうケースの方は、たいがいベビーベッドだけの利用でマットレスを利用しないお客様でした。 知らずにそうした悪い環境のもとで赤ちゃんを寝かせていた思うと少し怖いですよね。 そうならないためにも今回私は配送経験をもとに、赤ちゃんにとってベストな睡眠環境をつくる為に、マットレスの必要性を解説します。 この記事を読んでいただけた後、実際にマットレスの特性がよくわかり「赤ちゃんを寝かせる為にはやっぱり必要だね!」とママパパが判断していただければ幸いです。 1. ベビーベッドにマットレスが必要な理由 ベビーベッドを利用して赤ちゃんの睡眠環境作ろうと思う方の大半はベビー布団セットも準備します。ベビー布団セットがあれば敷布団も入っているしマットレスまでは必要ないでしょう…と思うママパパもいると思います。 実は、ベビー布団セットに入っている敷布団は薄くて使っているうちにヘタってしまい耐久性がなく、かつ通気性の悪いものがほとんどです。ここでは敷布団とは違うマットレスの特性を解説し、ベビーベッドにマットレスが必要だということをお伝えします。 1-1. 敷布団だけだと通気性が悪くカビ・ダニが発生する原因になってしまう! なぜ敷布団にカビやダニが発生してしまうの?と思いますよね。 その原因は、敷布団の通気性にあります。 主にベビー布団セットに入っている敷布団は、赤ちゃんの沈み込みを防ぐために硬めに作られています。 その敷布団の中の素材の多く固綿でできています。固綿の敷布団は通気性が悪いのです。 通気性が悪い敷布団だとカビ・ダニが発生してしまう! 一日の大半を寝て過ごす赤ちゃんは、寝ている間に大量の汗をかきます。一日の寝てる間におよそコップ2杯分(約400㎖)もの汗をかきます。その量は大人の約2倍にもなります。赤ちゃんがかいた汗は布団や敷布団にしみ込み、通気性の悪い敷布団だとなかなか乾きません。その状態で使い続けているとカビやダニが発生する条件を満たしてしまうのです。 “カビ・ダニの発生の条件は4つ” ① 湿気がある 赤ちゃんの汗等による湿気がこもる環境や加湿器による過度な湿度環境 ② 養分がある...
抱っこ紐ケープの選び方とおすすめ8選!代用できるモノも検証してみた
寒い季節の赤ちゃんとのお出かけ、防寒対策は万全ですか? 暑い季節の赤ちゃんとのお出かけ、紫外線予防や冷房対策は万全ですか? 抱っこ紐やベビーカーにブランケットをかけても、使いにくさを感じたり、何だか心持てない気もしたり。そんな時に一つ持っておくと便利な「抱っこ紐ケープ」。代用品でももちろん対策は可能ですが、抱っこ紐用に開発されたケープなだけに、便利で快適な機能がたっぷり盛り込まれていて、使ってみるとその違いは明らか!抱っこやベビーカーでの外出が多いご家庭では是非持っておきたいアイテムです。 そこで今回は、抱っこ紐ケープ選びで押さえてほしい4つのポイントについて解説、季節別のおすすめケープを紹介していきます。 さらに! 多くのママパパから声が寄せられている「抱っこ紐ケープは他のアイテムで代用できる説」を確かめるために、様々な代用品を使って検証してみました。検証してみてわかった専用ケープの利便性や代用品のメリット・デメリットを本音で評価していきます。 赤ちゃんとのお出かけをもっと快適にするための抱っこ紐ケープ選びに、この記事が参考になればうれしいです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 抱っこ紐ケープ選び4つのポイント 抱っこ紐ケープには、各メーカー独自の開発で工夫を凝らした高性能な商品がたくさん販売されています。ここでは、最適なケープ選びについて4つのポイントを解説していきます。デザイン・機能・素材など、商品の特長をしっかり見極めて、あなたのNO.1ケープを見つけてくださいね。 1-1. 季節に合わせた素材を選ぶ ケープを使う目的としてはまず防寒対策があげれらますが、夏も紫外線や冷房対策のために必要とされるシーンは多いものです。また、体温調節がまだ上手にできない赤ちゃんは風邪を引きやすいため、屋内外の寒暖差には十分に配慮してあげたいたもの。できれば季節ごとにケープを用意すると、お出かけもより快適に楽しむことができるでしょう。秋冬・春夏、季節ごとのおすすめ素材を紹介しますので、参考にしてください。 夏の紫外線や冬の寒さ、雨から赤ちゃんを守り、お出かけをより快適にしてくれる抱っこ紐用ケープ。メインで使用する季節に合わせて素材を選びましょう。 1-1-1. 秋・冬は防寒対策!フリースやダウン素材がおすすめ 暖かいフリース素材やダウン素材の抱っこ紐ケープなら、寒い外気からも赤ちゃんを守ってくれます。赤ちゃんの身体全体を覆えるような大きさのタイプを選ぶのもポイントとなります。足先が袋状でくるっとできればもっと安心、裏地の取り外しが可能なタイプなら温度の調整ができるので便利ですよ。 1-1-2. 春・夏はUV対策!通気性のよいメッシュ素材がおすすめ 暑い日のお出かけは、赤ちゃんの日焼けが心配です。肌の弱い赤ちゃんには、使用する日焼け止めの成分も気になるところですね。そんな方には、紫外線対策ができるUVカット対応のケープがおすすめ。室内の冷房対策や虫よけにもなります。通気性のよいメッシュ素材などであれば、暑い夏でも赤ちゃんにとって快適ですね。 1-2. 雨や雪の日も安心の撥水加工がおすすめ 夏でも冬でも雨や雪の対策は大切。撥水加工や防水加工が施されたケープがあれば、さっと羽織るだけで雨や雪を防げます。 表面は撥水加工、内地は赤ちゃんの肌にも優しいコットンを使用したものも多く販売しています。小さく収納できるタイプなら、急な雨に備えて携帯しておくと重宝します。 1-3. ベビーカーと兼用できるタイプがおすすめ 抱っこ紐とベビーカー、両方に使えるマルチタイプがおすすめです。抱っこ紐の使用頻度が減ってもベビーカーで使えれば長い期間での使用が可能。おくるみやバッグとしても使用できる超多機能タイプも多く販売されていますので、こちらも要チェックです! 1-4. 着脱のしやすいクリップタイプがおすすめ 屋内外の着脱やベビーカーへの付け替えなど、着け外しのシーンは多いため、1人でも簡単に取り付けられる商品が理想的です。留め具に採用されているタイプは、クリップタイプまたはスナップボタンタイプが大半を占めていますが、手軽さの面ではクリップタイプがおすすめです。クリップタイプなら、ベビーカーや洋服など、つまんで挟む部分さえあればどんなものに対しても留めやすいため、用途の幅も広がります。 2. 季節別おすすめ抱っこ紐ケープ8選! これまで抱っこ紐ケープ選びで「季節」は重要なポイントとお伝えしてきました。では、どのようなモノが人気なのでしょうか?ここではおすすめのケープを季節別にご紹介します。ぜひ商品選びの参考にしてみてくださいね! 2-1. 秋・冬におすすめ4選 足元が包まれているタイプは、赤ちゃんが動いでもズレにくく、しっかりと暖かさを保つことができます。抱っこでもベビーカーでもすっぽり包まれていれば安心ですね。寒さからしっかり守ってくれる素材、機能を兼ね備えたアイテムをピックアップしました。 【スウィートマミー】ダウンブランマフ8WAY 素材...
『子育て本音トーク vol.8』使ってみた!ベビーバス・ベビースケール編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第8弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第8弾は「ベビーバス・ベビースケール」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「今回はベビーバス・ベビースケール編です。この2つは生まれてすぐに使うアイテムですね。」 ととママ「ベビースケールは産院で授乳が始まると同時に使いますし、ベビーバスは退院後にまず必須になるベビー用品ですよね。」 あゆなママ「体験してもらったのはベビーバス4種、ベビースケール3種、あと、バスチェアもでしたね。今日は別にベビーバスをもう1つ用意したので、色々と話を聞かせていただきたいと思います。」 ととママ「はい。今回もリアルな体験談をお伝えしてきます!」 1. 育児日記で授乳量の目安を管理しました あゆなママ「本題に入る前に、今日は育児日記を持ってきてもらいましたので、見せていただいていいですか?」 ととママ「第1子の時のものなんですが、結構マメにつけていたので、今見るとびっくりします(笑)」 あゆなママ「わ~~~!これはスゴイ!ここまできちんと書いてる方っていないんじゃないかな。」 ととママ「産院でメーカーさんからもらったノベルティの日記帳なんですけど、産院での授乳の記録からつけはじめて、退院後もしばらく書いてましたね。」 あゆなママ「母乳が安定するまでは授乳量がわからないから、記録をつけておくと目安になりますよね。」 ととママ「授乳量、体重、沐浴の時間、自分の体重まで、スケジュールに書き込んでましたね。最初の子だけですけど(笑)」 2. ベビーバス4種類を使ってみた! お尻が滑らなくて安定感があるんです あゆなママ「それでは、本題に入りましょう!まずはベビーバス4種について、ズバリ!第1位は?!」 ととママ「迷いなく第1位はミッフィーワンツーバスです!」 あゆなママ「やっぱりそうでしたか~(笑)何が一番の魅力でしたか?」 ととママ「お尻部分のストッパーとヘッドサポートのリクライニング機能が便利でした。ストッパーがあるとお尻が滑らなくて安定感があるんです。赤ちゃんを支えるのも片手を添える程度でいいので、すごく楽に沐浴ができました。」 あゆなママ「コンパクトだからこれならキッチンのシンクでも使えますよね。」 ととママ「そうなんです!私はほとんどお風呂で使ってたんですが、シンクでやってみた時はいい感じでフィットしましたよ。」 あゆなママ「ヘッドサポートのリクライニング機能はどうでしたか?」 ととママ「お座りできるようになってからは、リクライニングを立ててバスチェアとしても使えたのですごく便利でした。」 コンパクトなサイズ感とお洒落なデザイン! あゆなママ「では次に、第2位は?」 ととママ「ストッケ フレキシバスです。コンパクトなサイズ感とお洒落なデザイン!プレゼントにもいいですよね。」 あゆなママ「畳んだ時のこのコンパクト感はナンバーワンですね。お手入れもしやすそうだし、たたんで片隅に置いておけるのはいいですよね。」 ととママ「お座りができるようになってから、お風呂でプールみたいな感じで使うのにもピッタリでした。」...