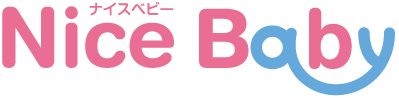ベビー用品
スペースを有効活用!折りたたみ式ベビーサークルの選び方5条件
この記事にたどり着いた方は、使いたい時だけ簡単に設置できるベビーサークルを見つけたい、使わない時はコンパクトに折りたためるベビーサークルがほしい、限られたスペースを有効的に使えるベビーサークルはないかな?など、折りたたみ式ベビーサークルの導入を検討されているところでしょうか。 ベビーサークルには様々な種類があり、リサーチしてみたけどあまりの数に一瞬ひるんでしまう方も多いかもしれません。必要な機能や構造を見抜いて自分に合ったものを選ぶのって大変ですよね。 『折りたたみ式ベビーサークル』は、必要な時だけ設置、使わない時はたたんで収納できるもので、傘のように開閉するタイプやパネルを蛇腹状にたためるタイプなどの種類があります。 『折りたたみ式ベビーサークル』の一番の魅力は、省スペースなこと! ベビーサークルに部屋を占領されてしまうことなく、スペースが有効活用でき、家族みんなが寛げるスペースづくりが叶います。「使いたい時だけ簡単にサッと出して、すぐ収納できる」そんなベビーサークルがあったら、忙しいママもスムーズに家事が進められますよね! そこで今回は、折りたたみ式サークルを選ぶ際にチェックしてもらいたい5つの条件を解説、その条件を満たした折りたたみ式ベビーサークルを厳選して紹介します。 また「折りたたみ式ベビーサークル」と「パネル組立式ベビーサークル」の違いも検証、どちらにするべきか迷われている方も必見です! この記事を最後まで読んでいただければ、納得のベビーサークルを手にすることができますので、是非参考にしてください。 ナイスベビーラボは、赤ちゃんんとの毎日がより楽しく豊かに過ごせるよう全力でお手伝いさせていただきます。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 折りたたみ式ベビーサークルを選ぶ5つの条件 部屋のスペースに余裕がない場合や移動させて使用したい場合は、折りたたみ式ベビーサークルがとても便利です。使わないときは折りたたんで部屋の隅に置いておき、必要なときだけすぐに組み立てて使えます。 コンパクトに折りたためれば収納場所に悩むこともなく、リビングスペースを広く保つことができれば、家事導線も確保できママもストレスフリーに。 また、赤ちゃんがサークルを嫌がる時でも、折りたたみ式ベビーサークルならタイミングを見て簡単にリトライが可能。ボールプールにしたり、お庭でひなたぼっこしたり、置き場所を自由に変えることができれば、赤ちゃんが気に入ってくれることだってあります。 数あるベビーサークルの中で、1つを見つけ出すのは大変ですが、ここで紹介する5つの条件を満たしたもであれば、きっと納得して自分に合った使い方ができます。それでは、早速チェックしていきましょう! 1-1. 簡単設置!ママ一人でも簡単にできること 折りたたみ式のベビーサークルは、女性でも簡単に設置できるものがおすすめです。広げてロックするだけの傘のようなつくりのタイプなら1分程で組立できるものもあります。頻繁に出し入れするなら、短時間で簡単にできるものを選びましょう。 1-2. メッシュタイプ!赤ちゃんの様子が見えること サークルの中の赤ちゃんの様子が確認しやすい素材を選んで下さい。中が透けて見えるメッシュタイプであれば、赤ちゃんの動きや表情も分かり、異変にもすぐに気づくこともできます。ベビーサークルは、あくまで補助グッズです。目を離した隙に起こる誤飲や転倒などの事故危険性を念頭に置き利用しましょう。 サークルの中の赤ちゃんの様子が確認しやすい素材を選んで下さい。中が透けて見えるメッシュタイプであれば、赤ちゃんの動きや表情も分かり、異変にもすぐに気づくこともできます。ベビーサークルは、あくまで補助グッズです。目を離した隙に起こる誤飲や転倒などの事故危険性を念頭に置き利用しましょう。 1-3. コンパクト!軽くて楽に持ち運べること サークル本体が軽量なら、簡単に持ち運ぶことができ掃除や部屋間の移動もスムーズです。 さらに、収納キャリーバッグ付きなら、しまっておく時や帰省や旅行にも重宝します!家族でキャンプやピクニックの時にも活躍してくれそうですね。 1-4. きれいを保てる!シートカバーが洗えること 洗濯機で洗えるシートカバーなら、赤ちゃんの過ごす空間をいつも清潔に保つことができます!よだれや食べこぼしや飲みこぼしもパパッときれいにできますね。日頃のメンテナンスが簡単なのは、忙しいママにはうれしいポイントです。 1-5. 安全な高さ!赤ちゃんが安全に過ごせること 抜け出し防止を目的として用意するなら、サークルの高さは床から60~70cm程度の高さのものを選びましょう。赤ちゃんが後追いをして、サークルから出てこようとするシーンは多く見られることです。サークルの中に、踏み台になるようなおもちゃがあると、柵を越えてしまうこともあるため注意!赤ちゃんが安全に過ごせる空間を作ってあげましょう。 2. 5条件を満たす折りたたみ式ベビーサークル3選! 前章で解説した折りたたみベビーサークル5つの条件をすべて満たした「おすすめのベビーサークル」を紹介します。折りたたみ式が必要なママパパにとって、これを選べば間違いない!といえる商品を厳選していますので、ぜひ検討して下さいね。 2-1. 洗えてたためる...
おしゃれママ必見!長く使える『ベビーサークルマット』のおすすめ4選!
最近SNSでの投稿も多く話題となっている『ベビーサークルマット』。トレンドに敏感なママたちは、気になっている方も多いのではないでしょうか。 ベビーサークルマットはやわらかいマットでできたベビーサークルで、形を変えて色々な用途で使用できる便利なマットです。 『ベビーサークルマット』人気の理由はこんなところにあります。 ●インテリアに映えるおしゃれなデザイン ●転んだりぶつかったりしても、怪我する心配がなく安全 ●足音を小さくする防音効果があるので安心 ●ベビーベッドの代わりやお昼寝用にも使えて便利 厚みがありクッション性の高いマットは多用途で使うことができます。赤ちゃん成長に合わせた柔軟な使い方ができるので、長期間の使用が叶う優れもの。 そしてなんと言ってもその魅力はおしゃれなデザイン!柔らかなベビーカラー、ポールやルーフでのデコレーションなど、SNSで話題になるのも納得のオシャレ度です。 木製やプラスチック製のベビーサークルに比べて、価格帯が高めな点が気になりますが、使用したレビューを見ると高評価なものばかり!赤ちゃんのケガに対する安全面はもちろん、汚れを落としやすく衛生面にも優れていて、ご近所への騒音も軽減できると、かなり満足度の高いアイテムなのです! 今回はこの人気上昇中『ベビーサークルマット』の魅力を余すところなく解説、おすすめの商品を厳選して紹介していきます。 また、ベビーサークルと合わせてフローリングの上に敷くマットが欲しいとお考えのママパパへ、赤ちゃんの安全面を考慮したおすすめのベビーマットも、先輩ママの口コミと合わせて紹介します! リビングを居心地のいい家族団らんできるスペースをつくって、毎日の赤ちゃんとの生活が楽しく快適になりますよう、この記事がお役に立てれば嬉しいです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 『ベビーサークルマット』とは? ベビーサークルといえば、赤ちゃんが動き出すハイハイの時期から用意するご家庭が多いと思いますが、マットタイプの場合、新生児期の赤ちゃんの居場所や簡易ベビーベッドとしても活用できるアイテムです。木枠やプラスチックに比べて軽量なので、ママ一人でも簡単に出し入れや移動ができる手軽さも人気のようです。それでは、『ベビーサークルマット』について解説いていきます。 1-1. お誕生から!成長に応じて形を変えて使用できる便利なマット! 『ベビーサークルマット』は、サークルとしてもフロアマットとしても活用できる長期使用を可能にした多機能タイプ。厚みのあるマットは、転んでも衝撃を吸収してくれるのでケガの心配もなく、マンションの場合、階下への足音も軽減できて安心ですね。サークルとして使用しなくなった後もリビングに敷いたり、お布団マットとしても使えます。赤ちゃんを寝かしつけしながらママも横になれるのは人気のポイントです!使用しない時は、簡単に折りたたんで収納できるのもメリットですね! 1-2. SNSで映える!抜群に可愛いベビールームが作れる! 可愛すぎる!育児が楽しくなる!とSNSで話題の『ベビーサークルマット』。お好みのセットをチョイスして、オリジナルのベビールームを作ることができます!赤ちゃんが大好きなモービルをつけてあげたり、ハウスフレームをつけてあげれば、赤ちゃんのお気に入りのベビースペースの出来上がり! 1-3. ベビーサークルとしての使用期間は短い! 『ベビーサークルマット』の場合、囲いの状態で使用できるのはつかまり立ちのころまでと短い期間のみの使用となります。しかし、木製やプラスチック製のベビーサークルは、基本的に、ママ一人で家事や用事を済ませたい時、一時的に目を離す間に赤ちゃんが安全に待機できる場所として活用することができます。 ベビーサークルはどう使いたいか、いつごろまで使いたいかなど、使用用途をはっきりさせておくことも、サークルを選ぶ上でとても重要です。 ベビーサークルとして使用できる月齢 ベビーサークルマット ★ 9ヶ月頃まで ★ 9ヶ月前後のつかまり立ちができるようになったら、サークルのサイドガードを越えてしまうことも。移動制限のためのベビーサークルとしての機能はしませんので、ママがそばで見守る必要があります。 木製・プラスチック製のベビーサークル...
チャイルドシートの種類が全てわかる!人気メーカー15社リスト付き!
車を日常的に使用されてるご家庭では、お子さまが生まれると早々に必要になるのがチャイルドシート。退院時からすぐに必要になる方、そろそろ外出もできる月齢になり準備を始めた方など、状況は様々ですが、はじめてのチャイルドシート選びで共通して持つ悩みは「種類が多すぎて何がいいのかわからない!」ということではないでしょうか? 筆者の私も同じ経験を持つ一人。豊富な種類の中からたった一つを選択しなければならない状況「もうこれでいいか!」と安易に決めてしまったことで「あっちの方が良かった><」「これじゃ使えない?!」と後悔した苦い思い出があります(笑) 価格帯の低い物であれば買い直しもできますが、チャイルドシートとなるとそう簡単にはいきません。何度も購入するなんて現実的ではありませんよね。ましてや、子供の安全を守る大切なベビー用品であれば安易に決めるのは絶対にNG!慎重に選ぶ必要があります。 では、どうしたらベストなチャイルドシートを選ぶことができるのでしょうか。 スムーズな商品選びを行うためには、まずチャイルドシートの種類とその特徴を理解し、ご自身の環境に合うタイプを知ることが重要。下記の3つのポイントを順に確認し、種類を洗い出していきましょう。 (1)お子さまの体型 (2)取り付け方法 (3)メーカー 今回は、チャイルドシートの種類を知り、商品選びで失敗しないための3つのポイントについて詳しく解説、おすすめのタイプ別商品ラインナップも合わせて紹介していきます。 初めてのチャイルドシート選びにタメになる情報満載ですので、ぜひ参考にしてみてください! 1. チャイルドシートの種類6タイプの特徴 チャイルドシートの種類は大きく分けて6タイプ。そのときの子供の体型によって使用できるものが異なります。どの時期にどのようなタイプが使用できるのか、それぞれの特徴とともに見ていきましょう。 1-1. 新生児~1才頃まで「乳児用:ベビーシート」 [対象体型]体重:13kg以下/身長:70cm以下 ・軽量 ・コンパクト ・赤ちゃんを寝かせたまま持ち運べる ・ロッキングチェアとして使用可能 ・ベビーチェアとして使用可能 ・使用期間が短い ・後ろ向き設置のみ対応 ベビーシートは、新生児~1歳頃まで使用できる新生児期に特化したチャイルドシートです。身長70cm以下、体重13kg以下、腰が据わるまでが使用時期の目安となります。 小さな赤ちゃんの体にピッタリと合う設計で新生児に必要な機能が備わっています。シートは赤ちゃんの背骨の形に合わせたやさしく包み込む安心のかたち。全身をしっかり守るクッションも備えられ、衝突安全性との兼ね合いも考慮された理想的なシート形状とされています。 最大の特徴は、軽量かつ持ち手が付いているので、走行中に寝てしまった赤ちゃんを起こさずに乗せたまま移動できること。 降車時の抱っこで赤ちゃんを起こしてしまうリスクを軽減させることができるのです。 さらにチャイルドシートとしての機能以外にもロッキングチェアとして、ベビーチェアとして、車外でも一時的な赤ちゃんの居場所として活躍の多機能型チャイルドシートです。 トラベルシステムってなに? ベビーシートを調べると「トラベルシステム」というワードが多く出てきます。 トラベルシステムとは、ベビーシートを専用のベビーカーに取り付けることによりベビーカー、チャイルドシート、ベビーキャリー、ロッキングチェアなど多用途で使用できるシステムのこと。ほとんどのベビーカーは生後1ヶ月からしか使用できませんが、このシステムを利用すれば新生児から使用できます。 ベビーシートを選ぶ際はトラベルシステムを使用するかどうかも検討してから選ぶとよいでしょう。...
赤ちゃんの安全とママの安心を両立!おすすめのベビーサークル8選!
生後半年頃から腰が据わり始め、お座り、そしてハイハイができるようになると、ゴロゴロ寝返りをしていた頃から赤ちゃんの生活は一転!活動範囲が一気に広がると、何もかもが刺激的で興味が止まらない時期に突入します。 ふとした瞬間に視界から消えたり、階段に手をかけて登ろうとしたり、ゴミ箱をひっくり返して散らかしたり、、、。後追いも始まるこの時期は、急激な成長に慌てることもあり、ママとしては喜んでばかりはいられない状況も多くなってきますよね。 ママ一人で家事や用事を済ませたい時、一時的に目を離す間に赤ちゃんが安全に待機できる場所が欲しい!という思いは、この時期のママ達みんなが持つ共通の願いかもしれませんね。 そんなママ達の願いを叶えてくれるのがベビーサークルです! ベビーサークルは四方が囲まれたタイプを思い浮かべる方が多いと思いますが、最近では、便利な機能を備えたベビーサークルが多く出てきています。パネルを増やして拡張できるタイプや簡単に折りたためるコンパクトタイプ、パーテーションからサークルに変化できるものなど選択肢も広く、ご家庭のライフスタイルやインテリアに合わせて選ぶことができます。 ここでは、ベビーサークルの種類を素材や機能別に解説、ナイスベビーラボが厳選したおすすめのベビーサークルを紹介していきます。さらに、サークル設置に悩むご家庭への提案として、購入前に考えておきたい収納・処分問題やレンタルの活用法についても解説します。 赤ちゃんの安全確保とママのサポート役として、ベビーサークルを上手に活用してくださいね! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. はじめにベビーサークルの種類を知ろう! ベビーサークルは、主に4タイプあり、素材や機能の違いによって使い勝手が異なります。 まずは、常に設置したままにするのか、使うたびに出し入れするかなど、使いたいシチュエーションを想定した上で機能を選んでいきましょう。べビーサークルは、リビングの中でも存在感が大きいので、好みにあう色味や素材を選べば、インテリアとしても毎日を可愛くコディネートできますよ。 それでは、4つのタイプの特徴を解説していきます。 1-1. 木製ベビーサークル 木製のベビーサークルは、インテリアと安全を両立するおしゃれなセーフティグッズです。フローリングと同系のナチュラルカラーなら、リビングの雰囲気に馴染みやすい点も◎。安定の人気を誇るサークルです。 しっかりとした作りで重さがあるので、頻繁に移動はしない方に向いています。また、犬や猫などペットのいるご家庭にも人気のタイプです。 1-2. プラスチック製ベビーサークル キュートなベビーカラーが映えるとおしゃれママたちの間で話題のプラスチックタイプ。SNSでもお洒落な写真の投稿が多いことからその人気ぶりもうかがえます。とにかくカラーバリエーションが豊富で、インテリアに合わせて好みのカラーを選ぶことができるのが魅力です! 木製に比べ軽量のため、ママ一人でも組立・設置ができ、気になった汚れは、さっと拭き取れるので取り扱いが簡単にできます。日常のメンテナンスが簡単なのは、忙しいママにはおすすめです。 1-3. メッシュタイプベビーサークル スペースを有効活用したいご家庭で人気なのが、メッシュタイプのベビーサークル(プレイヤード)です。 軽量なので、工具不要で組立できて移動が楽にできるのが特徴です。中には、折りたたみできるサークルや、カバーを丸洗いできるものもあります。床のシートが備わっているので、マットを準備する必要がないのもメリットです。メッシュタイプのものは赤ちゃんがぶつかっても怪我をする心配がなく、赤ちゃんの様子を確認しやすいので安心です。 1-4. マットタイプベビーサークル マットタイプのベビーサークルは、サークルとしてもフロアマットとしても活用できる多機能タイプ。厚みのあるマットは、転んでも衝撃を吸収してくれるのでケガの心配もなく、マンションの場合、階下への足音も軽減できて安心ですね。サークルとして使用しなくなった後もリビングに敷いたり、お布団マットとしても使えます。赤ちゃんを寝かしつけしながらママも横になれるのはいいですよね! ベビーベッドタイプ ベビーベッド兼プレイヤードとして使用できるタイプもあります。 ベビーベッドの標準サイズは、120×70cmの内寸です。サークルとして使うには狭く、赤ちゃんによって嫌がってしまうことも。拡張できるタイプのものであれば、ある程度長い期間使用することができます。 ▼ 詳しくはこちらの記事で ▼ >...
チャイルドシートレンタルのメリットとおすすめレンタルショップ3選
「チャイルドシートをレンタルしてみようかな?」とレンタルについての情報収集を始めた方へ、耳寄りの情報を紹介したいと思います! 購入する場合と違って、レンタルとなると商品の品質やサービスなど「レンタルって実際どうなのだろう?」と、気になる点は多いかもしれませんね。 事実、レンタルショップによって取り扱い商品やメンテナンス状況が異なるので、安いからという理由だけで選んでしまうと「思ってたのと違う」「こんなはずじゃなかったのに...」と後悔してしまうことも起こり得ます。レンタルする前に、まずはしっかりとリサーチをした上で利用することがとても大切です。 ここでは、失敗のないチャイルドシートレンタルの全貌を紹介! チャイルドシートをレンタルするメリットやショップ選びで抑えておくべきポイント、レンタルの流れについて解説していきます。また、知っていれば得する「知っトク情報」の掲載やナイスベビーの人気レンタルチャイルドシートも掲載、押さえておくべき情報満載ですので、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。 こちらの記事を読んで頂ければ、レンタルに対する不安を解消することができますので、参考にしてください。 1. チャイルドシートレンタル4つのメリット チャイルドシートはレンタル?購入?とお悩みの方が多いベビー用品のひとつです。 使用頻度が低い、カーシェアリングで自宅保管が必要、使用期間が短いタイプのチャイルドシートの利用など、シチュエーションによっては、購入よりもレンタルの方が俄然お得なことが多々あります。ここではチャイルドシートレンタルのメリットを紹介していきますので、レンタルor購入でお悩みの方、是非参考にしてください。 1-1. 必要な期間のみ借りられる レンタルのメリットと言えば、なんと言っても「必要な期間のみ借りられる」という点です。 チャイルドシートを使用する時期の子供はとても成長が早く、思いのほ早い時期にサイズアウトしてしまった><!ということはよくあります。特に新生児時期用タイプは、あっという間にきつくなってしまうためレンタルがおすすめ! そんな時、レンタルなら! 必要な期間のみ借りることができるので費用に無駄がありません。使い終わったらすぐに返却ができるので保管場所も必要がないのが嬉しいですね。 1-2. 処分する費用や手間がかからない!保管スペースもいらない! チャイルドシートは大型ベビー用品なので処分に困ることが多いです。処分は粗大ごみの扱いになりますので、費用は一般的に300~500円程。粗大ごみ処理券を購入したり、受付センターへ依頼する必要もあり手間がかかります。ご家庭で保管する場合も、場所をとるため保管スペースの確保も大変です。 そんな時、レンタルなら! 必要がなくなったタイミングで返却できるので使い終わっても邪魔になりません。 また、思い入れの詰まったベビー用品を中々捨てられないママは多いですが、レンタルはまた新たに必要とする子供の元に届きますので気持ちよく手放すことができますね! 1-3. 最新&高機能な商品を安く使える 最新商品や高機能な商品を購入するとなるとそれなりの費用が必要となります。自分に合ったタイプを見つけても費用によっては断念せざるを得ないケースも少なくありません。それでも利用頻度の高い場合は利便性や機能性にもこだわりたいというのが本音のところではないでしょうか。 そんな時、レンタルなら! レンタルは最新商品や高機能なタイプでも手軽に使用できて、デザインや搭載機能にこだわることが叶います。最新アイテムを取り揃えているショップは、定期的に商品の入れ替えをしているので品質への意識が高いと言えるので安心ですね。 1-4. 購入前にレンタルでお試しできる チャイルドシートは種類も豊富でなかなかこれ!といったモノを決められないものです。実際に使ってみないと、子供によって合う・合わないタイプもあり、買いなおしが簡単にできるものでもないため、商品選びも慎重になりますよね。 そんな時、レンタルなら! まずはレンタルで一度試してみる!という方法があります。レンタルショップによっては、1週間や2週間などの短期で利用できることもあり、お試しにぴったりなサービスも充実しているので購入より気軽に試してみることができます。商品選びでお悩みの方はまずレンタルで試して、納得の上で購入するのもオススメです。 2. レンタル向きの3つのシチュエーション 1章ではレンタルのメリットをお話ししましたが、まだまだレンタルには踏み切れない段階ですよね。ここではどのような時にレンタルが向いているのかシチュエーションをご紹介します。レンタルするかどうかの判断材料にぜひ読んでくださいね。 2-1. 新生児専用チャイルドシートの場合...
いつから始める出産準備まるわかり解説!妊娠月別準備スケジュール付
妊娠中期(5~7ヵ月)は心も体も安定し体も動かしやすくなる時期。お腹も徐々に大きくなるのと共に妊婦さんである実感もとても大きくなってくるころですね。 妊娠後期(8~10ヵ月)に入ると日に日にお腹も重たくなり、体の自由が効かないことも多くなります。産休に入り赤ちゃんを迎えるための色々な準備も忙しくなる時期です。 では、出産準備はいつ頃から始めるのがベストなのでしょう。 初めての出産であれば、準備をするとしても一体いつから何に手を付けていいのか、よくわからないですよね。 出産準備の開始時期に決まりはありませんが、まずは母体に無理のない範囲で進めることが大前提。産休に入ってからゆっくりと...と考える方も多いと思いますが、実はそれではちょっと遅いこともあります。 出産予定日はあくまでも予定の日。特に妊娠後期は急なトラブルも起こりやすい時期ですので、ギリギリで慌ててしまうことのないよう、余裕を持って準備することが大切です。 そこで今回は、出産準備の進め方を妊娠月に合わせて解説していきます。 準備品以外の生活で進めるべきことや、産後のために知っておきたい情報なども紹介します。便利な妊娠月別の準備スケジュール帳もダウンロードできますので、是非参考にしてくださいね。 1. 妊娠6~8ヵ月頃から徐々に始めたい出産準備 出産準備の開始時期として、ナイスベビーラボがおすすめしたい時期は妊娠6~8ヵ月頃。その理由としては、体調が安定し、現実的に動きやすい時期であることがあげられます。赤ちゃんの性別もわかるのでベビー用品選びのイメージもしやすいですね。 では、一般的にはいつ頃からスタートするのが多いのでしょうか?ナイスベビーラボで先輩ママにアンケート調査をしてみましたので、まずはその結果から見ていきましょう。 1-1. 出産準備はいつから?アンケート調査してみた! 1-2. 動きやすい時期にできることをスタートしよう アンケートでも一目瞭然。出産準備は妊娠7~8ヵ月でスタートした方が約半数を占めました。妊娠9ヵ月以降で準備を始める方が次に多い結果となり、産休に入ってから落ち着いて準備を進める方も多いようです。 妊娠7~8ヵ月は、妊婦生活にも慣れ体調も安定し、動きやすい時期。この頃が一番現実的に動ける時期ということなのでしょう。ナイスベビーラボが推奨する時期ともほぼ合致します。 9ヵ月以降になるとかなりお腹も大きくなり体の自由も効かなくなってきます。妊娠後期はママの体調にも変化が起こりやすいナーバスな時期。出産間近で買い物などで長時間外出するのはとてもリスキー、何が起こるかわかりません。 できればその前の動ける時期にやっておきたい準備がいくつかあります。出産準備は、少し早めの時期にやっておくべきこと、後期でもできることに分けて進めていくのがよいでしょう。具体的な準備の進め方についてこの後の章から順を追って解説していきますね。 2. 始める前に絶対に知ってほしい「出産準備の心得」 可愛いベビー用品を見ていると、あれもこれもほしくなったり、あったら便利かな?と使うのかわからないものまで買ってしまったり、これ、やりがちです。結局使わなかった、とか、肝心なことを準備していなかった、などの無駄や不足がないようにしたいものです。 ここでは出産準備を始めるにあたり知ってほしいことをまずは伝えたいと思います。 2-1. アイテムごとに異なる準備時期を知ろう 赤ちゃんを迎えるためには色々な準備品が必要となりますが、思いつくままに準備を進めてしまうのは絶対にNG!早すぎて邪魔になったり、後からもっといい物が見つかったり、遅すぎてほしいものが手に入らなかったりすることも考えられます。 例えば、外出時に使う抱っこ紐やベビーカーなど、育児には必須アイテムではありますが、実際、生まれて1ヵ月は外出を控えるために出番はありません。産前にはリサーチのみ、揃えるのは産後でも十分間に合います。 出産準備は急がずに、まずは、アイテムごとに準備すべき時期を知って、必要なものを徐々に揃えていきましょう。 2-2. 使わなかった...とならないために「必要最低限」が鉄則 ついつい買いすぎてしまいがちなベビー用品。可愛い赤ちゃんグッズはほしくなってしまうんですよね。わかります。ただ、揃えたわりには全然使わなかったという物も多くなってしまうので要注意。 産前に揃えるべきアイテムとしては、産後すぐに必要となるもの「必要最低限」を鉄則として準備していきましょう。 赤ちゃんによって使うものが異なってくることと、ママの状態によっても異なってきますので、産後の赤ちゃんとママの状態に合わせて揃えていくことをおすすめします。 出産準備リストについて、詳しくはこちらの記事で! >...
【先輩ママ体験談】ベビーサークルが必要な3つの理由と便利な使い方
赤ちゃんが一人遊びができるようになると、赤ちゃんの遊び場として部屋にキッズコーナーを作ってあげたいな~と思いますよね。大好きなおもちゃを置いて楽しく遊べてお昼寝もできる安全な空間があるって、いいですよね。 また、上にお子さんと遊ぶスペースを分けたい時や、ペットのいるご家庭では生活空間を仕切るために、サークルの導入を検討した始める方も多いことと思います。 ハイハイが始まった頃の赤ちゃんは、昨日までできなかったことが急にできるようになる時期。家事で少し目を離した時にドキッとするようなことも起こりがちです。そんな時期に是非使っていただきたいのがベビーサークルです。赤ちゃんの遊び場として、また、安全を確保するためのスペースとして活用できる便利なアイテムです。 ベビーサークルを使って「これがないと生活できない!」というママが続出するほど、使ってみると手放せなくなるようです。今回は実際にベビーサークルを利用した先輩ママの体験談をシチュエーション別に紹介、便利な使い方や必要な理由を3つの視点から解説していきます。また、ベビーゲートをサークルとしてアレンジしたり、レンタルの利用など賢い利用法も合わせて紹介します。 ベビーサークルに興味を持つママパパに役立つ情報満載でお届けしますので、是非最後までお使いください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. ベビーサークルが必要な3つの理由 サークルは赤ちゃんの安全を一時的に確保するために、是非使ってほしいおすすめの子育てアイテムのひとつ。ベビーサークルがあることで得られる日常の安心はとても大きいものです。具体的にはどんなことなのか3つの視点から解説していきます。安全面以外でも赤ちゃんが楽しく過ごせる、お気に入りのスペースを作ってあげることもできれば一石二鳥ですね! 1-1. 万が一の事故防止!赤ちゃんの安全を確保するため サークルが必要となる月齢は生後半年から1歳半頃で一番目が離せない時期です。家の中でもドキッとするシーンを何度か経験されている方も多いのではないでしょうか。実際に、この頃に家の中での事故が多発していることが、国民生活センターからも報告されおり、ご家庭内でも十分な注意が必要です。 赤ちゃんが安全に過ごせるスペースを確保し、周りの危険物から守るためにも、ベビーサークルを上手に活用しましょう。 【事例】転倒しテーブルの脚に頭をぶつけ硬膜外血腫 ソファにつかまりながら伝い歩きをしていたところ、つまずいて転倒し、左側頭部を金属パイプ製のテーブルの脚にぶつけた。左側頭部付近に柔らかい腫瘤(しゅりゅう)があったが受診しなかった。翌日の夜、痙攣(けいれん)があり、受診すると、硬膜外血腫があり入院。(2012年4月発生 11カ月、女児、中等症) 【事例】ボタン電池が食道にとどまり手術で摘出 テレビのリモコンで遊んでいた。その後、リモコンのボタン電池がないことに気づいた。食道第一狭窄(きょうさく)部にボタン電池があり、3時間かけて摘出した。(2012年11月発生 1歳5カ月、男児、中等症) 【事例】テーブルの上の電気ポットを倒しやけど テーブル(高さ80cm位)に電気ポットがあり、児が手を伸ばして倒れ、左上半身に熱湯がかかってしまった。目撃者なし。左腕、左全胸部、腹部水疱(すいほう)破れあり、全身の8-9%の熱傷。(2011年5月発生 1歳1カ月、男児、中等症) ※引用:国民生活センター「発達をみながら注意したい0・1・2歳児の事故―医療機関ネットワーク情報から―」 1-2. 家事を効率よく!ママの時間を確保するため 赤ちゃんをずっとおんぶしながら家事をこなしているママ、すごく多いですよね。おんぶするしかないですよね >< おんぶしながらだと、はかどらないことも沢山あるし、おんぶしながらできないこともたくさんあります。例えば、アイロンがけ、揚げ物をするとき、重たいものを運ぶ、お風呂のカビ取りなど...。 そもそも、ずっとおんぶしてるなんてしんどすぎませんか?! おんぶの「ながら家事」からママを解放するため、是非ベビーサークルを使ってください!赤ちゃんが一人でいられるお気に入りスペース、そして、安全なスペースを作ることで、忙しいママの時間をより有効的なものにしていきましょう! 1-3. ずっとおんぶは辛い!ママの身体の負担やストレスを軽減するため 産後の気になる体の不調として「腰痛」「肩・首の痛み」「不眠」などがあげられます。妊娠から出産までの体の負担、育児中の抱っこやおんぶも要因のひとつと言われています。家事中から寝かしつけまで、ずっとおんぶしたままでは心身ともにとてつもない負担となります。 赤ちゃんがお昼寝した時には、ママだって休んでください。ママも入れる大きなサークルなら赤ちゃんと一緒に入ってしまいましょう。もし、ママが寝入ってしまっても、サークルの中なら赤ちゃんが一人で危険な場所に行ってしまうこともなく安心。 ベビーサークルがあれば、ママの身体の負担を軽減してくれて、赤ちゃんと癒しの時間を作ることだってできますよ。 2. 先輩ママの体験談!べビーサークルを有効活用できる6つのシチュエーション ベビーサークルを使用していたママたちに、どんな風に使っていたのか、どんな時に便利だなと感じたのかなど、感想を聞きました。ベビーサークルが有効活用できるシチュエーションを6つに分けて体験談を紹介していきます。 2-1. 一時的に待っていてほしいとき...
『子育て本音トーク vol.4』使ってみた!ベビーカー編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第4弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第4弾は「ベビーカー」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「今回はベビーカー編です!使ってもらったのは、3輪タイプ、4輪タイプをそれぞれ3種類ずつ、 全部で6種類でしたね。 」 ととママ「はい。いろいろ試してみました!」 あゆなママ「 普段の生活は車移動がメインですよね。ベビーカーはどのくらいの頻度で使ってますか?」 ととママ「車がメインなんですが、ベビーカーもそこそこ使ってます。 週に3~4日位かな。 3人目なので外に遊びに行く確率も高い(笑) 」 あゆなママ「そうなりますよね(笑)では、使ってもらったベビーカーの感想とそのあたりのシチュエーションなんかも色々と聞かせてもらいたいと思います。 」 1. ベビーカーが活躍するシーンを教えて! 寝てしまった時のことを考えるとお出かけにベビーカーは必須! あゆなママ「 ベビーカーでのお出かけはどんなところに行きますか?」 ととママ「 日常的に使うのは夕方の犬の散歩で。お兄ちゃん達が犬を連れて、私はベビーカーを押して一緒に歩いてます。」 あゆなママ「お買い物に行く時は使いますか?」 ととママ「近所に買い物に行く時は使いますよ。あと、大型のショッピングモールに行く時は、抱っこ!ってなると大変なので絶対に持って行きます。」 あゆなママ「大きな公園だったりピクニックだったり、外で使うことはありましたか?」 ととママ「たくさん使いました!生後2ヵ月頃に河川敷のこいのぼりを見に行きました。まだ首が座る前だったのでA型ベビーカーが役に立ちました!もう少し大きくなってからはアウトドアで、海や川にも行ったし、大きい公園に遊びに行った時も。」 あゆなママ「広いところを歩き回る時や寝る場所が確保できない外ではベビーカーは必須ですよね。」 ととママ「そうなんですよ。寝てしまった時のことを考えるとお出かけに ベビーカーは必須。車で出かける時でも必ずベビーカーも積んでいきます。」 2. 3輪タイプのベビーカーを使ってみた! 3輪タイプの共通する特長はバツグンの操作性!...
知らないと損!チャイルドシートの賢いレンタル方法とショップ13選!
レンタカーやカーシェアリングの普及により、車を必要な時だけ生活に取り入れ上手に活用する方が増えています。お子さまのいるご家庭では、車の利用にチャイルドシートは必須アイテム。帰省時や旅行など短い期間だけチャイルドシートが必要となるシーンも多いことでしょう。 とはいえ、日常的に使うものではない上に、費用や保管場所、お子さまの成長によるサイズの問題など、購入に踏み切ることは難しいのが現実ですよね。 そんな時、便利に利用したいのがレンタルサービス。 チャイルドシートのレンタルと言えば、レンタルショップやレンタカー会社のサービスというイメージをお持ちでしょうか?実は、それだけではありません!あまり知られていませんが、自治体や交通安全協会でも貸し出しサービスを行っているのです。地域によっては無料貸し出しをしてくれたり、補助が出たり、条件が合えばかなり手厚いサポートを受けられることがあります。チャイルドシートをレンタルで利用するなら、絶対に知っておくべきサービス!得すること間違いありません! そこで今回は、全国の知って得するチャイルドシートレンタルサービスについて徹底的に大調査! 地方自治体の貸し出し支援や交通安全協会のレンタルサービスについての全国の情報をまとめました。また、全国配送に対応しているレンタルショップ13社を比較、価格・利用期間・品揃えについても調査してみました。 レンタルの地域、期間、予算など、ご自身の条件と合わせて、これから紹介するサービスの中からベストなものを選んでくださいね。お得な情報をしっかりとキャッチして、チャイルドシートは賢くレンタルしましょう! 1. チャイルドシートをレンタルする4つの方法 チャイルドシートをレンタルする主な方法として「レンタルショップ」「自治体」「交通安全協会」「レンタカー会社」で実施しているサービスを利用する4つがあげられます。 サービスを受けるには諸条件もあるため、自分はどのサービスを受けられるのか知った上で利用方法を選択していきましょう。それでは各サービスについて詳しく解説していきます。 1-1. はじめてでも安心!万全サポートのレンタルショップ チャイルドシートのレンタルといえば、まずレンタルショップを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。レンタルショップは豊富な品揃えと品質の高さ、価格帯も幅広く選択肢の多いことがポイントです。レンタルショップによっては、2日間や2週間などの短期間の利用も可能、料金も利用期間によって変わるので費用に無駄がありません。 全国に店舗を持つショップであれば実店舗での受け取りも可能であったり、オンラインショップや電話注文で希望の場所まで配送してもらえる手軽さは、忙しいママにとっては嬉しい限りのサービスです。 また、レンタルショップでは、知識豊富な専門スタッフに商品選びやレンタルのあれこれを相談することができます。故障や汚してしまったときのサポートもしっかりとしているので安心ですね。 1-2. 地方自治体の貸出し支援 地方自治体の中には子育て支援の一環としてチャイルドシートの貸し出しを行っている所があります。 購入補助や無料貸し出しなど場所によって条件は様々ですが、ここでは「無料貸し出し」「レンタル料金補助」2点のサービスに絞って全国の自治体を調査しました。使用条件や利用期間などは自治体によって異なるため、直接お問い合わせください。 お住いの地域で行われている制度を上手に利用してチャイルドシートをお得に使用しましょう! チャイルドシートレンタルサービス全国自治体一覧 北海道 士別市 無料貸し出し 健康福祉部こども・子育て応援課子育て支援係 電話:0165-26-7759 > 詳細へ 青森県 五所川原市 無料貸し出し 環境対策課生活安全係 電話:0173-35-2111 >...
赤ちゃんの居場所を安全な空間に!おすすめベビーゲート厳選8選!
この記事に辿り着いたのは、きっと 「赤ちゃんがハイハイを始めて目が離せなくなってきた!」 「階段を登ろうとする姿を目撃した!」 など、危険エリアへのベビーゲート設置の必要性を感じ探し始めたところ、おすすめの商品情報を探しているところでしょうか。 この頃の赤ちゃんは、ふと目を離したスキにびっくりするような所にいたり、触ってほしくないところから何度引き離しても行ってしまったり、ドキッとすることが日々増えてきますよね。 私も第一子の時、ハイハイと後追いが始まった頃にベビーゲートの必要性を強く感じ、キッチンへの侵入を防ぐためにゲートを購入した経験があります。設置した後は日常生活の安心感がグッと高まったことを思い出します。 当時はベビーゲートの種類も限定されていて選択肢が少なかったこともあり、それほど悩まずに購入に至りましたが、ここ数年の間にベビーゲートが多様化され、商品選びが困難を極めているのも事実。 実際にナイスベビーで取り扱うベビーゲートはなんと20種類以上! 住宅事情に合わせたサイズ展開や素材、デザインにもこだわった充実のラインナップですが「種類がたくさんあって選べるのはいいけど、選び方が難しい...」と、お客さまからの相談も多くいただいています。 そこで今回は、私が次に買うなら絶対にこれ!という商品をpick up!設置場所別とシチュエーション別におすすめ商品を紹介していきます。また、商品選びの前に必ず知っておいてほしいベビーゲートの種類と固定方法も解説しますので参考にしてください。さらに、ベビーゲートを購入ではなくレンタルがおすすめなシチュエーションについても紹介、レンタルの方がぐっとお得になるシーンもありますので、こちらも必見情報です! 今からベビーゲート選びを始めるママパパに、是非知ってもらいたい情報を一気に集結!関連情報や商品情報も惜しみなく紹介しています。生活空間に合うベビーゲート選びのヒントが必ずココで見つかるはずですので、是非最後までお付き合いくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 購入前に知ってほしい!3つの固定方法とゲートの種類 「購入後に取り付けできないことに気が付いた!」というのは、ゲート購入時によく聞く話。設置場所の構造や商品のサイズが合わなかった、ゲートのタイプによっては生活環境に不向きだった…など、事前のリサーチ不足で起こり得る失敗談です。 そんなことにならないためにも、ここではゲートの種類や固定方法について解説していきます。 設置場所に合うゲートを選ぶためにもまずは知っていただきたいポイントですので、しっかりと確認してくださいね。 1-1. ベビーゲートの固定方法3タイプ ベビーゲートには主に、3つの固定方法があり、それぞれに固定の強度や設置方法が異なります。下記では3タイプの特徴を解説しますので、まずはどのような種類があるか見ていきましょう。 1-1-1. 突っ張り棒のしくみで壁や柱に設置する「突っ張りタイプ」 一般的に広く知られている「突っ張りタイプ」の固定方法。設置方法も簡単なのでママ一人でも取り付けが可能です。 ただし、家の造りによって壁の中が丈夫でなかったり、柱に段差があったりなど設置できない事あります。購入前には設置場所をしっかりと採寸し、ゲートの設置状条件を確かるようにしましょう。 あわせて読みたい! 突っ張り式ベビーゲートおすすめ5選!購入前に確認すべき3つのこと ベビーゲート(ベビーフェンス)は、赤ちゃんを危険から守る必須アイテムです。赤ちゃんのハイハイが始まるころ、キッチンや階段、水回りなどの危険な場所へ移動してしまうのを心配して、購入を検討されるママパ... ナイスベビーラボ 1-1-2. ステップ台に赤ちゃんが乗ることで固定される「置くだけタイプ」 ここ数年で目覚ましい進化を遂げ登場し、注目されているのが「置くだけタイプ」のベビーゲート。面倒な設置も不要で簡単に置くだけ、扉付きで出入りもラク、素材もサイズもバリエーションも豊富で、様々な間取りに対応しています。手軽さ以外にも壁面や柱に傷がつくリスクがない点も人気の理由です。 あわせて読みたい! 設置場所で選ぶ!置くだけベビーゲートが人気のワケと買う前の注意点...
『子育て本音トーク vol. 3』使ってみた!チャイルドシート編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第3弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第3弾は「チャイルドシート」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「今回はチャイルドシート編ですが、使ってもらったのはキャリータイプ、回転式タイプでしたね。座席固定タイプは上のお子さんの時に使っていたということですので、それについても一緒にお話を聞かせてもらいたいと思います。日常的な移動手段は車ですか?」 ととママ「ほぼ車移動です。保育園の送迎は車で、買い物なども車で行くことが多いですね。」 たばち「乗ってる車はなんですか?」 ととママ「ホンダのステップワゴンです。」 あゆなママ「お子さんの座席は決まってますか?」 ととママ「赤ちゃんは二列目シートに、お兄ちゃん二人は三列目シートに座ってます。」 あゆなママ「なるほど。では、ここから実際に使ったチャイルドシートについて聞いていきますね!」 1. キャリータイプとベビーカーをドッキングさせてみた! 赤ちゃんもスヤスヤ寝たまま移動できて安心! たばち「キャリータイプは3種類を使っていただきましが、まずはその話から聞かせてください。」 ととママ「最初は退院時に、レーマーベビーセーフSHR2をベビーカーのB-AGILEにドッキングさせて使いました。部屋までチャイルドシートとベビーカーを持ってきてもらって、赤ちゃんを乗せたらベビーカーを押して病院から車まで移動しました。」 あゆなママ「使い心地はどうでしたか?」 ととママ「すごく安心でした。生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこして歩く不安はないし、赤ちゃんもスヤスヤ寝たまま移動できる!」 たばち「理想的な使い方ですよね~。赤ちゃんは寝たまま車に乗ることができるんですよね。」 ととママ「看護師さんや先生にも、それいいね!って、みなさんに言われました(笑)」 あゆなママ「その他のシーンで同じように使いました?」 ととママ「1ヵ月検診の時もこのスタイルで車から病院まで楽々移動しました。そのあとは、犬の散歩の時にもよく使ってましたよ。」 1台5役!トラベルシステムならチャイルドシートやベビーカーにも! 2. ベビーキャリーとして3タイプを比較してみた! どれもベースの取り付けは簡単。ママ一人でも十分可能な作業ですよ! あゆなママ「使ってもらった3タイプはどんな違いがありましたか?」 ととママ「レイマーのSHR2はベビーカーに乗せて使ったので、ベビーキャリーとしてだけではあまり使わなかったのですが、赤ちゃんが乗ると結構重たいので、片手でひょいって感じではなかったですね。若干安定感に欠けるというか、赤ちゃんが乗っていると持ちにくい感じもありました。」 たばち「ピパとジョイー アイレベルはどうでしたか?」 ととママ「ピパはすごく持ちやすいんですよ!ハンドル部分のグリップが持ちやすいさの秘密だと思う。重さは変わらなくてもSHR2より軽く感じるくらい!持った時の安定感がありました。幌が大きいのもすごくよかったです。」 あゆなママ「ホントだ!持ち比べてみると、重さの感じ方も違いますね。確かに持ちやすい!」 ととママ「アイレベルは何といってもこのクッションがいい!頭までしっかりと包み込んでくれて安心感がすごい。ベビーキャリーとして持ち歩く時の安心感という面では、アイレベルが一番かな。」...
マキシコシ製タイタンプロの魅力に迫る!次世代の安全性能と快適機能
1968年に育児用品先進国オランダで誕生したマキシコシは、ヨーロッパで売上シェアNo.1を誇るチャイルドシートブランドです。 最新の安全基準である「R129」に対応したi-size(アイサイズ)を初めて商品化するなど、先進の技術を取り入れた最上級の安全性能がマキシコシの特長となっています。 新安全基準R129/i-Size(アイサイズ)について詳しく見る 今回はロングユースな前向きチャイルドシート「マキシコシTitan Pro(タイタン プロ)」をご紹介していきます。高水準の安全性能に快適性と使いやすさを追求したタイタンプロを詳しく見てみましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています ここがスゴイ!マキシコシ タイタンプロ 1. 生後9ヶ月~12歳頃までの長い期間を1台でサポートできる タイタンプロはインナークッションとヘッドレストを調整することで、生後9ヶ月~12歳頃までのお子様にフィットするロングユースなチャイルドシートです。 これ1台で長い期間をサポートすることができます。途中で買い換えの必要がないことはとても大きいですよね。 ロングユースとはいえ幼児期には、優しく包み込むインナークッションとエアクッションを内蔵したヘッドレストで、小さな体にも安全性と快適性の高い状態を保つことができます。 ロングユースの利便性とマキシコシによる先進の安全性能を併せ持った、これまでにないチャイルドシートです。 2. 誰でも正確にしっかり取り付けできるISOFIX&トップテザー固定対応 タイタンプロはISOFIXとトップテザー固定で簡単にかつ確実に取り付けができます。 従来のシートベルト固定タイプでは「腰ベルトの締め付け不足」や「座席ベルトの通し方間違い」など、全体の※約6割がミスユースとの調査結果も出ています。 ※チャイルドシート使用状況全国調査2017(警察庁 / JAF) ISOFIX固定ならコツや腕力など個人差による取り付け状態の違いがなく、誰がやっても同じように正確な取り付けができます。 3. 頭をしっかりガード!エアクッション内蔵ヘッドレスト タイタンプロのヘッドレストはエアクッションによる衝撃保護機能「AirProtect®」を内蔵しています。触ると弾力性があり空気による膨らみを感じます。このエアクッションが側面の衝撃に対して頭部をしっかりとガードしてくれます。 また、ヘッドレスト裏上部のハンドルを押すことで、簡単に高さ調整をすることができます。肩ベルトと連動して動くこともポイント。成長に合わせてワンタッチで高さを変えられます。 4. 幼児期の小さな身体をやさしく包むインナークッション こちらはチャイルドシートモード時に幼児期(生後9か月~3歳頃)の小さな身体をやさしく包むインナークッションです。 まだ腰がすわったばかりの不安定な身体にフィットして支えます。厚みがあり、クッション性が高いのでとても座り心地が良さそうです。 安全性と快適性を備えたタイタンプロの特徴と言えますね。 5. 次世代の衝撃保護技術「G-CELL」で側面衝突の衝撃から守る こちらは本体側面に搭載された新開発の衝撃保護素材「G-CELL(ジーセル)」。...