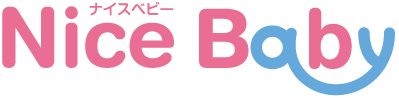ベビー用品
授乳タイムがもっと快適に!一押し授乳クッション17選【2022年】
授乳は産後すぐからスタートするママの最重要任務。 一日の授乳回数は、生後間もない頃で10回前後、3ヵ月頃でも8回前後が平均と言われています。 産後の疲れが癒えぬまま、夜中の授乳で睡眠時間は削られ、赤ちゃんを腕で支え続けて一日中何度も授乳するのは本当に大変なこと。肩や首の凝り、腰痛、腱鞘炎などの不調、心身ともにヘトヘトになるのも当然です。 そんな中でも、腕の中で母乳を飲むわが子を見つめるのは、母冥利に尽きる愛おしく幸せなひと時。できるだけゆったりリラックスした状態で過ごしたいですよね。 この幸せな時間をもっと有意義なものにしてくれるのが『授乳クッション』 授乳クッションは、赤ちゃんをしっかり支え、ママの腕をやさしくサポートしてくれるアイテムです。これがあるとないとでは、授乳時の楽さが全く違います。 筆者の私が授乳クッションのすごさを知ったのは、初めての授乳の時でした。慣れない授乳で悪戦苦闘していると、助産師さんが授乳クッションを勧めてくれました。使ってみると、こんなにも違うのかと驚いたことを思い出します。 退院後すぐに購入した授乳クッションは、ぺちゃんこになるまで使い倒しました。 そこで今回は、授乳クッションをおすすめする理由と選び方のポイントを解説、2022年版おすすめ授乳クッションを紹介します。 授乳クッションには、専用タイプと抱き枕兼用タイプがありますが、今回は授乳のための機能性を重視して授乳クッション専用タイプのみを厳選しました。抱き枕兼用タイプはまた別の記事で紹介していきたいと思います。 ママの負担を少しでも減らすことができれば、赤ちゃんとの生活がもっとHAPPYになること間違いありません。 快適な授乳タイムの実現に、この記事を読んでお気に入りの授乳クッションを見つけてくださいね! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 授乳クッションを使ってほしい理由 初めての授乳はどんなママにも難しいものです。何度も繰り返していくうちに、赤ちゃんとも息が合い上手な授乳ができるようになります。 授乳中は、赤ちゃんとママ、両方の姿勢に気をつける必要があり、無理な授乳姿勢を続けていると... ・ママの首や肩、腰に負担がかかる ・赤ちゃんが母乳を上手に飲めなくなる ・ママのストレス増加が母乳量が減少につながる など、良いことは一つもありません! 授乳初期、赤ちゃんが上手に飲めるようになるまで、ママは猫背で赤ちゃんの顔をのぞきこみがち。この姿勢が腰痛や肩こりを引き起こしやすくなります。 そんな時、授乳クッションを使いましょう。赤ちゃんの支えはクッションに任せて、ママはそっと手を添えるだけ。赤ちゃんは自然とママの胸元で落ち着いて母乳を飲むことができ、ママは胸を張りながらも腕や肩に力を入れずリラックスできます。 母乳育児に関わらず、ミルク育児の場合も授乳クッションの使用をおすすめします。授乳クッションを使い、哺乳瓶を持つ手を固定をすると、ミルクをあげやすくなりますよ。 快適な授乳時間を過ごすために、ぜひ授乳クッションを一つ用意してくださいね。 2. 授乳クッション選びで重視したい3つのポイント 最近の授乳クッションは、お洒落なものから機能的なものまで種類が豊富です。 数ある中からどれを選んだらよいかわからない!という方に、重視してもらいたい3つのポイントについて解説します。 2-1. 厚みのあるクッション 赤ちゃんが母乳を飲みやすい位置は、ちょうどママの胸が赤ちゃんの顔のあたりにくるくらい。厚みのあるクッションを選ぶと赤ちゃんが胸まで届きやすくなるので、快適な授乳姿勢をキープしやすくなります。 多くのママは、厚みが【15㎝以上】あると使いやすいようです。選ぶ際の目安にしてみてくださいね。...
絶対レンタルすべきベビー用品ベスト5!借りるor買うの正しい選択
ベビー用品は使う期間が限らているから、全てを買い揃えるのではなく、商品によっては必要なときに必要な期間だけ「レンタル」するということが賢い選択です。 短期間しか使わないものはレンタルすることで費用を抑えることができますし、使い終わったあとすぐに返すことができます。 とくに大型のベビー用品は使わなくなると場所を取るので、返却できることは大きなメリットになりますよ。 「レンタルで済むものはレンタルで済ませる。」 これがベビー用品のプロであるナイスベビーが提案する賢い子育て術です。 では、レンタルにした方が良いベビー用品とは何でしょうか? 数多くあるベビー用品の中で、レンタルすべきものを正しく判断することがとても重要です。 とは言え、これだけたくさんあるベビー用品の中で何をレンタルすべきか?どうやって判断するのか?答えは簡単には出せませんよね。それが初めての出産準備であればなおのこと。 でも安心してください。 そんなお悩みにお答えすべく、今回はベビー用品レンタル専門店のナイスベビーが「絶対にレンタルにすべきベビー用品ベスト5」を発表します! 年間1万件以上、ベビー用品レンタルをご利用いただいているナイスベビーが、お客様の声や満足度調査から導き出した独自のベスト5をご紹介します。 これを見れば、レンタルすべきものを迷わずに正しく判断できるようになります。 ぜひ参考にしてみてください。 1. 絶対レンタルにすべきベビー用品ベスト5 数あるベビー用品の中で、「これだけは絶対レンタルにした方が良い!」というアイテムをランキング形式でご紹介します。その明確な理由とあわせて見ていきましょう。 1-1. 第1位「ベビーベッド」 レンタルすべきベビー用品第1位は何と言っても「ベビーベッド」。 ベビーベッドは使用期間が限られていて、最も大きい標準サイズであっても実際には1歳くらいまでしか使わないケースが多いです。 使い終わったあとは分解して収納しておくか処分することになりますが、ここで問題になるのがその大きさです。 とくに標準サイズのベビーベッドは分解してもかなりの大きさがあります。 ナイスベビーのお客様も搬入時に「こんなに大きいの?」と驚かれることが本当に多いです。 次の子のためにしまっておくにも、それまでの間ずっと大きな収納スペースを専有してしまうことは問題ですよね。 廃棄処分するにしても、粗大ゴミとして費用がかかります。例えば自治体に依頼する場合には、各自治体によって1,000~1,800円ほどかかってしまいます。 でも、レンタルなら使い終わったベビーベッドをすぐに返すことができます。 これがベビーベッドをレンタルすべき最大の理由です。 「使い終わったあとどうしよう…。」と心配する必要がありません。 もちろん、必要な期間だけレンタルすることで費用もぐんと抑えることができます。 使う期間が限られた大型のベビー用品はレンタルのメリットがとても大きいですよ! ベビーベッドのレンタルを詳しく見る 1-2. 第2位「電動ハイローチェア」...
これを読めば完璧!ベビーカーの全てがわかる種類・機能・選び方解説
初めてのベビーカー選び、販売店で見かける国内有名メーカーやネットで見た海外メーカーのおしゃれなデザイン、価格もまちまちで何を基準で選ぶべきか難しいですよね。 ベビーカー選びを始めたみなさんが最初に持つ疑問は「ベビーカーの種類」について、かもしれません。 ベビーカーの種類は、日本国内ベビーカーの中では、大きく分けて2種類に分けられます。赤ちゃんの月齢と成長度合いによって使い始めの時期を二分化して「A型」「B型」と分類しています。 まずはこの2種類についてきちんと理解をした上で、ライフスタイルや使用開始時期を考慮しつつ、ベビーカーの選定を進めていくのがスムーズな流れです。 そこで今回は、ベビーカーの基礎知識「A型・B型」について解説、その後、ベビーカーそれぞれが持つ機能の特徴について、また、生活環境によって異なる選び方も解説していきます。 ベビーカーの機能を理解した上で、ご自身のライフスタイルと照らし合わせると、自ずと必要な機能が見えてきます。最後まで読み進めていただければ、ベビーカー選びがぐっと現実的なものに近づいてくるはずです。 記事の最後には、絶対得するレンタルの活用術とナイスベビーのお得な情報もご紹介しますのでお見逃しなく! これから始まる赤ちゃんとの生活をより快適にしてくれるベビーカーを選んで、お出かけをラクに楽しく過ごして下さいね! 1. ベビーカー「A型」「B型」の定義 国内メーカーのベビーカーには、「A型」「B型」の2種類があります。この基準は、商品の安全性を保証する制度「SG基準*」に基づいて、ベビーカーを二つに分類しています。 それでは、「A型」「B型」それぞれの定義と特徴について解説していきます。 *「SG基準」SGはSafe Goods (安全な製品)の頭文字を合わせたもの。一般財団法人製品安全協会が商品の安全を保証するために定めた基準 A型とB型ベビーカーは使い始め時期が違う!AB兼用、バギーも解説 店頭やネットショッピングではいろんな種類のベビーカーが並んでいます。かっこいいデザインからカラフルでかわいいものまで、見ているだけでワクワクしますよね。でも、はじめてベビーカーを選ぶうえで必ず出て... ナイスベビーラボ A型 B型 対象月齢 1ヵ月または3、4ヵ月から最大48ヵ月 7ヵ月から最大48ヵ月 座面と背もたれの角度 150度以上4ヵ月以上のものは130度以上 100度以上 使用時期目安 首または腰がすわる前から使用可 腰がすわってから使用可 姿勢 寝かせた状態で使用可...
チャイルドシートの助手席への設置は危険!エアバッグが事故原因に!
小さなお子様がいる家庭では、チャイルドシートの着用が義務化されていることはご存知の方も多いと思います。実際に2000年から6歳未満の幼児を車に乗せる際はチャイルドシートが義務となっています。 しかし、チャイルドシートを車に取付ける位置については特に規定がありません。 助手席にチャイルドシートを取付けても違法ではないのです。 ですが、多くのメーカーは取扱説明書に取付位置について助手席をNGとし後部座席にするよう記載されています。 では、なぜ助手席に取付けることはダメなのでしょうか? 多くの方はその理由を知らずに、取扱説明書やNG表記などを目にして後部座席に取付けているのだと思われます。 後部座席のチャイルドシートに子供を乗せていると、毎回嫌がって機嫌が悪くなってしまったり、移動途中にギャン泣きしてしまうなんてことが日常茶飯事。 いっそのこと助手席に設置すればママ・パパの顔が見えて安心して泣かなくなるかなぁ…と思ってしまいますよね。 でも、チャイルドシートは助手席に取付けるべきではない理由があるのです。 今回は、その理由をしっかりと解説していきます。 また、何らかの理由で仕方なく助手席に取付けしなければならない場合の注意事項も合わせてお伝えします。 何よりも子供の安全を守ることが第一ですから、利便性ではなく、より安全でリスクの少ないチャイルドシートの取付けを心がけることが大切です。 ぜひ最後までお付き合い下さいね。 1. 助手席にチャイルドシートを取付けるべきではない理由 冒頭でも述べましたが、チャイルドシートの取付位置の規定は特にありません。 助手席にチャイルドシートを設置しても違法ではないのです。 では、なぜチャイルドシートのメーカーや車のメーカーが助手席のチャイルドシート取付けをNGにしているのでしょうか? ここではその理由を解説します。 1-1. 最大の理由はエアバッグの挟まれてしまう危険性があるから 助手席にチャイルドシートを取付けできない理由がエアバッグにあります。 昨今、車の安全性が高まっており、ほとんどの乗用車に運転席と助手席にエアバッグが搭載されています。 エアバッグは助手席に乗車する「大人の人」を想定して作られているので、チャイルドシートを設置した状態でエアバッグが作動してしまうと想定外の事態に陥ってしまうのです。 万が一衝突事故を起こしてしまいエアバックが作動すると、エアバッグの膨張でチャイルドシートと助手席の間に子供が挟まれて潰されてしまいます。 そのような事態を防ぐために、助手席にエアバッグが搭載されている車のほとんどは、チャイルドシートを助手席に設置しないよう取扱説明書等に警告が記されています。 事前にご自身の車の注意事項をしっかりと確認しましょう。 1-2. 子供を助手席に乗せると運転が散漫になるから 助手席のチャイルドシートに子供を乗せた場合、ついつい横にいる子供の行動が気になってしまいます。 子供はママやパパが視界に入るので安心するかもしれませんが、運転している本人は声をかけられれば、気になって運転に集中ができなくなってしまいますよね。 そんな状態で運転を続けると、大きな事故に繋がってしまうかもしれません。事故は起きてからでは遅いのです。 運転が注意散漫になってしまうことも、助手席にチャイルドシートを取付けるべきではない大きな理由になります。...
新生児の添い寝におすすめのベビーベッドはこれ!狭い寝室にも置ける!
出産準備でとても大切なのは、赤ちゃんの居場所の確保。 就寝スペース、日中の居場所、特に新生児期はほとんどの時間を寝て過ごす赤ちゃんには快適な睡眠環境を整えてあげる必要があります。 添い寝を検討されている場合、就寝スタイルがベッドであれば、赤ちゃんにも専用のベビーベッドを用意しましょう。 「寝室にはベビーベッドを置くスペースがないっ!」 というご家庭も多いと思いますが、超小型サイズで添い寝できるベビーベッドがあること、ご存知ですか? ご夫婦のベッドの横にちょっとしたスペースがあれば置く事ができるコンパクトなベビーベッド。それだけではなく、日中は気軽にリビングに移動できて、いつでもどこでも赤ちゃんの居場所を確保することができるのです。 今回は、添い寝することを目的に開発されたベビーベッド「With(ウィズ)」について、そのこだわりや使い勝手の良さなど、隅々まで紹介していきます。 新生児期からの添い寝ができるベビーベッド選びに悩んでいる方は、迷わずウィズを選んでください、と言えるほど、おすすめできるベビーベッドです。 本記事の後半では、ウィズ以外の添い寝できるベビーベッドもいくつか紹介しますので、是非最後までお付き合いくださいね。 1. 添い寝のための超小型ベビーベッドWith(ウィズ) 超小型タイプベビーベッド『With(ウィズ)』は、内寸サイズ80cm×50cmで新生児期にぴったりのベビーベッドです。 一般的な標準サイズと呼ばれるベビーベッドの内寸が120cm×70cmなのでかなりコンパクトな造りだということがわかります。イメージとしては下記の写真を参考にしてください。 ベビーベッドは上の写真のように大きさの違いの他に、高さの違い「ロータイプ」「ハイタイプ」でも種類が分かれます。一般的に添い寝ができるベビーベッドは「ロータイプ」です。 With(ウィズ)は、細かな高さ調整ができたり、収納やお世話のしやすさなども、全て添い寝目線で設計されています。他のベビーベッドと大きく差別化されるポイントが多々ありますので、この後その特長について詳しく解説していきます。 1-1. 添い寝できるベビーベッド=ロータイプ 前述の通り、ベビーベッドにはサイズの違い、高さの違いがあります。 サイズは置き場所のスペースから選び、高さは使い勝手や生活スタイルから選ぶイメージです。 基本的に添い寝ができるのは「ロータイプ」のベビーベッド。添い寝スタイルとしてベビーベッドを寝室で使う場合は、必然的にロータイプを選ぶことになります。 「ハイタイプ」はベッドの柵を一番下まで降ろしても、柵の高さがあるために下記の写真のようになり、添い寝ができません。ロータイプであれば柵も低くく添い寝ができるという仕組みです。 1-2. 添い寝のしやすさを徹底的に追求した画期的構造 With(ウィズ)の最大の特長は添い寝のしやすさ。 これまでの添い寝できるベビーベッドは、スライドして下げた柵の厚みの分、大人用ベッドとの間に隙間ができてしまう構造でした。ウィズは、一方の柵を外すことができるため、大人用ベッドと隙間なくピタッとくっつけることができ、また、高さも9段階に調整できるので、大人用ベッドと高さを合わせやすく、とことん、添い寝にこだわった設計なのです。 1-3. お世話のしやすさと抜群の使い勝手の良さ 添い寝ベッドとして使っている時でも、全ての柵が開くので、どの方向からもお世話することができます。 ベッド下の収納スペースも十分なスペースがあり、扉も3方向から開閉が可能。どこからも収納物の出し入れができてとても便利です。 高さは最大50cmまで上げることができるので、リビングでの使用時も楽にお世話することができます。 1-4. 狭い家でもこれ一つ!リビングと寝室を自由に行き来 スペースの問題でベビーベッドの利用に二の足を踏んでいるご家庭でも、超小型サイズなら好きな場所で使うことが叶います。 例えば、六畳の寝室にシングルベッドを2つ置いている場合でもベビーベッドの設置が可能。下記の写真でイメージしてください。 また、夜は寝室で、昼間はリビングでも使いたい場合、お部屋間を行き来させることができます。キャスター付きの小さなベビーベッドならではの使い方です。もう少し大きくなれば、リビングはバウンサーなどを使用するのもよいですが、新生児期はベビーベッドで寝かせてあげるのがベスト。赤ちゃんにとってもご家族にとっても安心ですね。...
コレ1台で長く使える!AB型タイプ多機能ベビーカーおすすめ12選
コレ1台で長く使える「AB型」ベビーカー 一般的に、A型のファーストベビーカーを使って、お子様の成長に合わせB型ベビーカーに乗り換えるのがよくあるパターン。この2タイプの機能を兼ね備えたのが「AB型」ベビーカーです。買い替えなしでこの1台でずっと使えるなんて、夢のようなベビーカーですね。 よく耳にする「AB型」「AB型兼用」というキーワード。実は、2003年頃に流行ったの新型ベビーカーのことを指します。現在のSG基準では「AB型」は存在しません。 えっ!?でもAB型って見かけるけど、どういうこと? と思いますよね。 そのころから誕生したAB型は「A型」に吸収されたため、分類されなくなっているのです。 しかし、当時のAB型ブームの名残りが強く、今でもあえて「AB型」と表記する販売店も数多くあるため、よく見かける、耳にするという現象が起こるのです。 その理由としては【多機能で長く使えるベビーカー=AB型】のイメージが強いからだと推測できます。 ここでは、まずはじめに「AB型」とはどんなタイプかを解説し、多機能で長く使えるAB型タイプのベビーカーを、ナイスべビーラボ独自の見解で厳選したおすすめ商品を紹介していきます。 筆者もAB型兼用タイプを長く使った一人です。筆者の体験談も後半で紹介させていただきますね。 最高の1台を見つけて、これから始まる赤ちゃんとのベビーカーライフを楽しんでくださいね! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 「AB型」ベビーカーは日本独自の呼称 AB型は、2003年当時「高性能の新B型ベビーカー」として誕生しました。正式な区分や基準はなく、A型とB型を合体した万能ベビーカーとして『AB型』と呼ばれるようになり、一般的にも広く知られるようになりました。 『AB型』は、2004年のSG基準改定時に「A型」の区分に吸収されたため、正式には『AB型』という区分は存在しません。 国内メーカーのA型は、軽量化されてよりコンパクトなタイプを作り出していることもあり、今のA型の主流は、いわゆるAB型と呼ばれるタイプが大半を占める状況にもなっています。 基本的に、A型・B型というのはSG基準で定められた日本独自の区分です。 海外製のベビーカーは、わかりやすいように「A型タイプ」「B型タイプ」という形に国内では分類されて紹介しています。販売店によっては「AB型タイプ」とも分類することがあります。 最近ではベビーカーを選びやすいように、型タイプで分類する他に「多機能両対面タイプ」「軽量・両対面タイプ」「3輪タイプ」「軽量背面タイプ」など、機能別でカテゴリ分けをしているメーカーも増えてきました。 生活環境や主な移動手段、家族構成が様々あるように、それに対応できるべビーカーの種類が沢山あることが分かります。赤ちゃん連れのお出かけが快適になるように、自分に合うベビーカーを選んで行きましょう。 [参考]一般財団法人製品安全協会:SG基準「ベビーカー」 2. 【AB型タイプ】おすすめのベビーカー12選! 「長く使えるベビーカーがほしい=AB型」 この定義を前提に、ナイスべビーラボ独自の見解でおすすめベビーカーを厳選してみました。 【AB型タイプ】PICK UP条件 生後1ヵ月~36ヵ月まで使える 振動吸収機能が付いている しっかりリクライニングする 背面式・フレーム剛性がある...
抱っこ紐パパが格好いい!ママとシェアする男女兼用型おすすめ12選
ここ数年で、抱っこ紐姿のパパをよく見かけるようになりました。パパの抱っこ紐は当たり前の時代ですね。 抱っこ紐の高性能化により体格差があってもシェアできる商品が多数できたこと、ユニセックスでお洒落なデザインやパパ向けの商品が開発されたことなど、抱っこ紐はパパが抵抗なく使えるモノになりました。 初めての抱っこ紐選びにあたって、夫婦でシェアできるよう男女兼用タイプを探している方、とても多いと思います。でも、体格差を考えると本当にどちらも快適に使えるのか、それぞれ専用の抱っこ紐を用意した方がいいのか、疑問も浮かび上がってきますよね。 それ以前に、パパが抱っこ紐を使うことに抵抗を感じていて、パパ抱っこに期待できない...と悩みを抱えるママもいます。 そこで今回は、パパと抱っこ紐について色々と解説をしてきたいと思います。 パパが抱っこすることで得られるメリット、パパも使える便利な男女兼用タイプおすすめ抱っこ紐の紹介、お試しでのレンタル活用法についても触れていきます。 満足度の高い抱っこ紐選びのために、是非ご夫婦で読んでいただけると嬉しいです。 抱っこ紐を使いこなして、ワンランク上の素敵なパパに! ▼ 男女兼用おすすめの抱っこ紐を早く見たい!という方は第4章をご覧ください 第4章『ワンランク上のパパになるオススメ抱っこ紐12選』 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. パパの抱っこはいいことがいっぱい! パパが赤ちゃんを抱っこ紐をして歩くこと、これまで「抱っこ紐=ママの担当」からママが解放され負担がなくなることはもちろんですが、それ以外にもたくさんのイイコトがあります。どんなメリットがあるのか、一緒にみていきましょう! 1-1. 「ママがいい~~!」にならないために お買い物中のママ待ちにパパに抱っこされてギャン泣き、パパに抱っこされてるのにママの方に行きたがる、「ママがいい~~><」は、よく出会う光景です。 一緒にいる時間も長く、抱っこもいつもママだったら、こうなりますよね。 それでも、早い段階からパパに抱っこされるスタイルが確立されていれば、パパでも安心して抱っこされるはず。いつでも「ママがいい~~!」にならないために、パパの抱っこは早めにスタートしていきましょう。 1-2. 育児がパパの自分ごとになる 赤ちゃんは抱っこ紐で抱っこされるとウトウト眠ってしまう傾向にあります。安心しきって眠っている寝顔を間近で見ていられるのは、何とも幸せな気持ちになります。親冥利に尽きると言っても過言ではないですね。 この感覚を生まれて間もなくからパパも体感できるのが抱っこ紐のいいところ。子供との距離が心身ともにぐっと近づいていくものです。 こういった体験が積み重なることで、ママができない時だけのお手伝いではなくて、自然と子育てが自分ごとになっていくのではないでしょうか。 1-3. 抱っこ紐姿のパパはカッコイイ! 「イクメン」という言葉が出てきたころから、抱っこ紐姿のパパを見かけるようになりました。赤ちゃんが生まれたら抱っこ紐で歩きたい!と憧れるパパも増えているようです。それでもまだ抱っこ紐に抵抗のあるパパは多いのが現実。 きっと恥ずかしいと思うのかもしれませんが、抱っこ紐しているパパの姿を見て、世の中のママたちはカッコイイ!と思っているんです。その姿に憧れを抱く若い人たちもたくさんいます。 そう!抱っこ紐姿のパパはカッコイイんです! 1-4. ママの心と体の負担減 男性の育休取得も少しずつ増え始め、男性の子育て意識もあがってきていますが、それでも日本社会の子育ては、まだまだ女性が主体でママの負担が大きいというのが現実。 何をしたらいいかわからない、というパパがいたら、まずは積極的に抱っこ紐で子守りをしてください。家の中でも外でも、赤ちゃんをあやすことができて、寝かしつけまでできたなら、どれだけママが楽になることか。 特に授乳中は睡眠をしっかり取れず、体力的にも精神的にも苦しい日々が長く続きます。...
室内遊びマンネリ化解消!2歳児も楽しめる今を乗り切る遊び方を紹介
新型コロナウイルスが流行し、ウイルスと共に生活する日々もあっという間に1年を越えました。 色々なことが制限される今、お子様と一緒に自宅で過ごす時間が増えた方は多いのではないでしょうか? 外に出かけたくても出かけられない、こんな状況でもエネルギッシュで遊ぶことが大好きな子供たち。 自宅での時間が長引くことで『この遊びは飽きた』『違う遊びがしたい!』『つまらないから外に行きたい!』と言われパパやママは困ってしまいますね。 子供との時間が増えることは親にとって喜ばしいこと。しかし、ずっと一緒となると話は別です。 我が家も突然の休校、保育園の入園延期で、三人の子供たちと一緒に長い自粛期間を過ごしました。 簡単に外出ができない日々は現在も続き、休みが近づくたび『今週は自宅で何しよう』『次はこれかな』『次はこんなことしてみたらどうか?』と試行錯誤です。 室内遊びといえば、折り紙やねんど、ぬりえ、お絵描き、積み木、パズル、カードゲーム等いろいろ思いつきますね。これらの遊びは、雨や暑くて外に出られない日の定番かと思います。 楽しい遊びであることは確かですが、代り映えのない毎日が続くことで、刺激もなくつまらなくなり『またそれ~?』となってしまいます。実際、我が家がそうでした。 『いかにマンネリ化してしまった室内遊びを楽しくすることができるか』 今回は、2歳前後の子供にも十分に楽しめる遊び方の工夫やこんな時だからこそ使ってみていただきたいおもちゃ(アイテム)を、我が家の体験談も含めて紹介します。 お子様に合う合わないもあるかと思います。我が家も失敗と成功の連続です。 少しでも楽しい時間を過ごすための参考になればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. いつもと違う環境で子供の好奇心をくすぐる できればお金をかけず、アイテムも増やさずに室内遊びを楽しく出来たらいいですよね。 我が家では、年齢関係なく子供たちに楽しい!と思ってもらえた方法が『家の中で遊ぶ部屋・場所を変えてみる』ことでした。これが一番手っ取り早く簡単でとてもおすすめです。 住環境、生活環境によっては実践できない場合もあるかと思いますが、参考にしてみてくださいね。 1-1. 【浴室】お風呂タイムで水遊びを満喫 昼間の浴室は子供にとって魅力がたっぷり。夜とは違う雰囲気でなんだかワクワク♪ さらに、昼間のお風呂は時間にも余裕があり『いつまで入っているの!』と大人が怒ってしまうことがありません。子供たちも思う存分お風呂タイムを満喫できます。 ★ お風呂遊びのおすすめ ★ ・湯船に物を浮かべてすくう ・プリンカップやケチャップの容器をおもちゃ代わりにして遊ぶ ・お風呂用のクレヨンで思いっきり浴室内にラクガキ ・貼りつくおもちゃをペタペタ ・浴槽にボールや風船を入れてみる ・泡風呂...
【2023年】月齢と成長度合いで選ぶ!B型ベビーカーおすすめ12選
長く使うつもりで購入したベビーカーだけど、使いにくさを感じ始めていませんか? ベビーカーは使用する赤ちゃんの成長度合いにより、使いやすいタイプが変わってくるもの。何台か乗り換えをしている方が多いのも事実です。 「A型ベビーカーを使っていたけど、赤ちゃんもしっかりしてきたのでB型に乗り換えたい」 「A型ベビーカーは大きくて使いにくさを感じ始めてきて、コンパクトなベビーカーがほしい」 「抱っこ紐でお出かけしていたけど、重たくなってきたのでベビーカーが使いたい」 このような理由でB型ベビーカーの購入を検討している方、多いかもしれません。 B型ベビーカーは、生後7ヵ月以降、腰がすわってから使えるタイプを指します。機能もデザインも様々、価格もピンキリで、その幅広いラインナップから1台を決めるのは至難の業とも言えるでしょう。 B型ベビーカー選びで重要なのは、赤ちゃんの月齢や成長に応じて、より必要な機能や装備を見定めていくこと。生後7ヵ月の赤ちゃんと1歳半の赤ちゃんでは必要な機能も変わってきます。また、ママパパの使いやすさの面でも違いがあります。 そこで今回は、赤ちゃん月齢を目安にしたB型ベビーカーの選び方を伝授。赤ちゃんの成長度合いにより必要な機能・装備を徹底解説します!さらに、月齢別に国内外のベビーカーの中から、2023年版のおすすめB型ベビーカーを厳選して紹介していきます! この記事を参考に、赤ちゃんにとって安心安全でママパパにとって使いやすいものを選んでほしいと思います。では、早速見ていきましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. ベビーカーの種類についての基礎知識 まず最初にベビーカーの種類についておさらいしておきます。 ベビーカーの種類とは、日本国内ではSG基準に基づいて分類されています。以下のように、使い始めの月齢とリクライニング角度について「A型・B型」の違いが明記されています。 A型 背もたれをしっかりと倒すことができるので、生後1ヵ月から使えるタイプ。 小さい赤ちゃんを振動から守るクッションや赤ちゃんの顔が見れる機能がついているタイプもあります。 B型 赤ちゃんの月齢が「7ヵ月から」且つ「腰がすわってから」使える軽量タイプ。 成長した赤ちゃんを連れて外出する時、赤ちゃんを乗せて押すだけでなく、たたんで持ち運ぶことも想定したコンパクトなベビーカーが主流です。 AB型 A型の軽量ベビーカーのことを差し、A型とB型の特徴を兼ね備えたタイプ。 2004年以前にA型に属さない進化系B型ベビーカーでリクライニングする軽量タイプの俗称。現在のSG基準では、A型の分類になっていますが、今でもあえてAB型と表記する販売店もあるようです。ベビーカーの必要な期間を1台で済ませたい方に人気です。 バギー B型のベビーカーの中でもさらに単機能になり、より簡素化されたタイプ。 簡易な構造になっているため低価格で販売されているものが多く、耐久性には注意が必要です。歩くことがメインになるころには重宝します。 A型とB型ベビーカーは使い始め時期が違う!AB兼用、バギーも解説 店頭やネットショッピングではいろんな種類のベビーカーが並んでいます。かっこいいデザインからカラフルでかわいいものまで、見ているだけでワクワクしますよね。でも、はじめてベビーカーを選ぶうえで必ず出て... ナイスベビーラボ [参考]一般財団法人製品安全協会SG基準...
ベビーベッドはサイズ選びがカギ!大小それぞれのポイントを徹底解説
これから生まれてくる赤ちゃんの為にベビーベッドを準備しようと思っているママやパパ。 ベビーベッドにはいろいろなサイズがあることを知っていますか? ベビー用品の販売店などに置かれているベビーベッドを見かけても、特に大きさを気にしたことがない人も多いかと思います。 でも出産準備でベビーベッドを用意することとなれば、どのくらいの大きさなのかすごく気になりますよね。 当然、設置する場所や空きスペースなど考えて検討しなければいけないのですが、そもそもベビーベッドのサイズを知らないと、実際に置けるかどうかの判断ができず困ってしまいますよね。 今回はベビーベッドのサイズについて詳しくお伝えしていきます。 サイズごとのメリット・デメリットをしっかりと確認して、自分の用途に合った最適なベビーベッドを選ぶ事ができればいいですよね。 さらに、サイズ選びで注意するポイントもお伝しますので最後までお付き合いください。 それではベビーベッドの色々なサイズを見ていきましょう! 1. 要チェック!ベビーベッドのサイズはいろいろ 一口にベビーベッドと言ってもいろいろなサイズが存在します。 現在市場で多く販売されているサイズは「標準サイズ」と「ミニサイズ」になります。 ベビーベッドの布団もこの2サイズのものが一般的ですね。 しかし、実際には他にもいろいろなサイズのベビーベッドがあります。 例えばナイスベビーでは、標準サイズとミニサイズの中間に当たる「小型サイズ」という分類があります。 また、ミニサイズよりもさらに小さい「タイニーサイズ」と、計4種類のサイズ展開になっています。 メーカーや販売店によっては他にも様々なサイズがありますが、今回はナイスベビーで取り扱いのあるこの4種類のサイズをご紹介していきます。 1-1. 【標準サイズ】一番長く使えてポピュラーな大きさ ベビーベッドのなかで最も一般的なのが「標準サイズ」です。 販売店によってはレギュラーサイズやスタンダードサイズと呼ばれていることもありますね。 標準サイズは内寸が120×70cmと、ベビーベッドの中で一番大きいサイズです。 サイズが大きいので使用期間も長く、目安として誕生から2歳頃まで使うことができます。 市販されているベビー布団もこちらのサイズが最も多く、好きなベビー布団を選べることも標準サイズのメリットです。 標準サイズのベッドを見る 1-2. 【小型サイズ】標準とミニの中間の大きさ 次は小型サイズです。 こちらはナイスベビーのオリジナルサイズで、一般的に市販はされていないサイズになります。 小型サイズは内寸が100×63cmと、標準サイズよりも一回り小さくなります。 サイズが小さくなる分使用期間は少し短くなって目安は誕生から1歳頃までです。 標準サイズだと大きすぎてお部屋に置けない。でもミニサイズよりは長く使いたい…。といった人におすすめのサイズです。...
【2023年】便利な機能が満載!おすすめのA型ベビーカー10選!
出産準備を始めると、外出先で見かけるベビーカーをついつい目で追ってしまいますよね!カラフルな色やおしゃれなデザインなどいろいろな種類があって、見ているだけでも楽しい気持ちになりますね♪ ベビーカーには、A型、B型、AB型、バギーなどと呼ばれるいくつかのタイプがあります。赤ちゃんの成長に合わせたベビーカーを選ぶ必要があり、値段やデザイン、軽さだけで選んではしまってはダメ! まずは、ベビーカーの基本となるA型とB型の違いをしっかりと理解しておきましょう。 A型 B型 ・1ヵ月から使える ・月齢の浅い赤ちゃんを守る機能が充実 ・両対面式が多い ・大きい、重い ・価格が高め ・AB型=軽いA型 ・軽くてコンパクト ・価格が安め ・7ヵ月頃まで使えない ・リクライニングできないタイプがある ・対面式なし ・バギー=さらに軽いB型 ここでは、A型ベビーカーを選ぶ際に外せない5つの条件について解説、全ての条件をクリアしたおすすめA型ベビーカー10選【2023年版】を紹介します。 また、進化し続けるベビーカーの便利機能についても解説していきますので、自分にとって必要かを見定めてくださいね。 これから始まるベビーライフをエンジョイするために、この記事が参考になれば嬉しいです。 A型とB型ベビーカーは使い始め時期が違う!AB兼用、バギーも解説 店頭やネットショッピングではいろんな種類のベビーカーが並んでいます。かっこいいデザインからカラフルでかわいいものまで、見ているだけでワクワクしますよね。でも、はじめてベビーカーを選ぶうえで必ず出て... ナイスベビーラボ 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 赤ちゃんに優しいA型ベビーカーは5つの条件が最重要! A型のベビーカーを選ぶ際に必ずチェックしてほしいポイントが5つあります。 首すわり前の赤ちゃんを安全に快適にベビーカーに乗せるために必要な項目です。注意して見ていきましょう。 1-1. ほぼフルフラット!首すわり前でも安心なリクライニング SG基準ではリクライニング150度以上が条件となっていますが、170度以上倒せるベビーカーが主流です。フラットに近い状態なら生後1ヵ月の赤ちゃんでも安心して乗せることができますよね。 1-2. 路面から遠ざける!熱やホコリから赤ちゃんを守るハイシート...
新生児用チャイルドシートにキャリータイプを一押しする5つの理由!
新生児の赤ちゃんを乗せるチャイルドシートをお探しですか? 産院からの退院時に車を使うご家庭であれば、チャイルドシートの使用は必須! 生まれたばかりの赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるのは何だかかわいそう...と思う方も多いようですが、生後すぐの赤ちゃんも例外ではなく、チャイルドシートの着用は義務となっています。 最近の産院では、確実に車にチャイルドシートが付いていない場合は、退院させてもらえない!という話を聞きました。ママの抱っこではいざという時赤ちゃんを守ることはできません。赤ちゃんを守ってくれるのはチャイルドシートなのです。 それでは、どんなチャイルドシートを選べば安全に車移動できるのか?という疑問にお応えすべく、この記事では新生児の赤ちゃんのチャイルドシート選びについてまとめました。 はじめてチャイルドシートを使うご家庭に一番におすすめしたいのは、持ち手が付いた「キャリータイプ乳児用チャイルドシート」且つ「ISOFIX固定」のタイプです。その理由については、詳しく記事の中で徹底解説していきます。 また、新生児のチャイルドシート乗車の体験談、新生児を車に乗せる時のポイント、レンタル活用法と買い替え予想時期についても解説します。事前に知っておくと得する情報も紹介しますので、是非、最後までお付き合い下さい。 1. はじめてのチャイルドシート基礎知識 まず最初に、一般的なチャイルドシートについて知っておいてほしい2つこと、1つは、車体への固定方法の種類について、2つ目は新生児期に使えるチャイルドシートの種類について解説していきます。 1-1. チャイルドシートの固定方法2タイプ 固定の方法については、基本的に2種類あり、車本体にチャイルドシートを固定する「ISOFIX(アイソフィックス)固定」という方法と、車本体の座席のシートベルトでチャイルドシートを固定する「シートベルト固定」があります。 基本的に、2004年7月以降に販売された乗用車には、ISOFIX対応になっていますが、チャイルドシートと車本体がしっかり適合するかどうかを事前に調べておく必要があります。 使いたいチャイルドシートがあれば、適合品であるかどうかインターネットで検索して調べることができます。また、チャイルドシートの販売店やレンタル会社、乗用車のメーカーに聞いて調べることもできますので、わからない際は問い合わせてみましょう。 1-1-1. ISOFIX(アイソフィックス)固定 シートベルトを使わずに取り付け可能な、国際規格のチャイルドシート固定方式。車に装備されたISOFIXアンカーにチャイルドシートのコネクターを直接ドッキングして固定するので、装着ミスが少なく、誰でも簡単確実に取り付けできます。 1-1-2. シートベルト固定 シートベルトを使用して座席にシート本体を取付けるタイプの固定方法。従来から一般的な固定方法でしたが、近年では、アイソフィックス固定と両方兼用できるものも増えています。 1-2. 新生児期に使えるチャイルドシートの種類2タイプ 次にチャイルドシートの種類について、新生児が使えるものを2タイプ紹介します。 チャイルドシートは、赤ちゃんの身体が外からの事故の衝撃に耐えられるように、外側は頑丈な素材でつくられています。赤ちゃんが触れるシートは、優しく包み込むようなクッション素材になっています。特に新生児限定のチャイルドシートは生まれたばかりの赤ちゃんの体にフィットする設計が施され、安心や使いやすさの面でもおすすめしたい商品です。 1-2-1. 「座席固定タイプ」乳幼児兼用チャイルドシート 一般的に多くのご家庭で購入する最初のチャイルドシートが「座席固定タイプの乳幼児兼用チャイルドシート」です。 回転式や横型ベッド式などの大型製品ではありますが、新生児期から3~4歳まで長く使えるため、これを選ぶ方の割合が多くなっています。 このタイプは、幅広い月齢に対応し、赤ちゃんの成長に合わせた座り心地を実現するために、多くの機能が搭載されているのが特徴です。構造が複雑で重たいので、一定の座席に固定したまま、チャイルドシートの乗せ換えのないご家庭におすすめです。 1-2-2. 「キャリータイプ」乳児用チャイルドシート もう一つのタイプは、持ち手が付いた「キャリータイプの乳児用チャイルドシート」。1歳頃までの小さな赤ちゃんに特化した構造のチャイルドシートです。 使用期間が短いためにその後は幼児用チャイルドシートへの乗り換えが必要となります。 車を持たずレンタカーやカーシェアリングを利用するご家庭が増える昨今、軽量でコンパクトな使いやすいさで需要が高まっています。また、赤ちゃんを乗せたまま家と車を移動できる手軽さ、家の中ではロッキングチェアとして使える多機能性も人気の理由です。 2. 新生児に『キャリータイプ』をおすすめする5つの理由 首のすわらない小さな赤ちゃんのためのチャイルドシートにおすすめしたいのは「キャリータイプ」の乳児用チャイルドシード。さらに、ISOFIX固定専用ベースがあれば、はじめての方でも簡単・確実に取り付けできるため安心です。ここでは、その理由を解説していきます。...