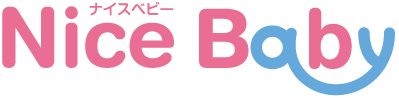ベビー用品
【比較検証】沐浴できる色々な場所に置いてみた!おすすめベビーバス5選!
ベビーバス選びにお困りですか? 赤ちゃんが生まれる前に想像して、自分に合ったタイプのベビーバスをたくさんある種類の中から選ぶのって迷ってしまいますよね。生後~1か月過ぎるころまでの短い使用期間ですが、できればママパパが使いやすく、赤ちゃんにも優しいおすすめのタイプを選びたいですよね! ここでは、ライフスタイルに合わせたベビーバス選びのポイントとおすすめの商品を厳選して紹介していきます。使用する場所やシチュエーションなどを考慮して、ママやパパが使いやすいかお手入れがしやすいかなど、安全に快適にお世話のできるものを選びましょう。ぜひ購入の際に参考にしてくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. ベビーバスのおすすめはこの3タイプ! ベビーバスは、床に置く昔ながらのプラスチック製の「床置きタイプ」と空気を入れて膨らませる「エアータイプ」、折りたたんで省スペースでしまえる「折りたたみタイプ」の3タイプがおすすめです。 1-1. 初めての沐浴は安定感のある安心「床置きタイプ」で! ★ おすすめのポイント ★ ● 初めてのママパパでも扱いやすい ● 床やテーブルの上でも安定する ● 汚れをすぐに洗い落せる 初めての沐浴をする場合、用意しておけば、すぐに使える形になっているので、準備の手間がなくスムーズに沐浴ができます。洗いやすさが一番のおすすめポイントです。また、劣化しにくいので、第二子、第三子まで保管しておく場所があれば購入もおすすめです。 1-2. ママ一人の沐浴は軽くて使いやすい「エアータイプ」で! ★ おすすめのポイント ★ ● 赤ちゃんが当たっても痛くない ● 少量のお湯ですむ ● 使用期間が終わったらコンパクトにしまえる たたんで持ち運びが簡単なので、帰省や旅行に適しているため、移動が多いママパパにはおすすめです。ふわふわなクッション素材なので、赤ちゃんの身体をやさしく包んでくれます。 1-3. 省スペースの沐浴はコンパクトな「折りたたみタイプ」で! ★...
これで全てわかる!ハイローチェアレンタルの全貌&先輩ママの体験レポ
初めてのハイローチェア(ベビーラック)レンタル。いいものを使いたい期間だけ、お得に使いたいけどどうやって選んでいいか迷っていませんか? そんなママパパ必見!失敗しないハイローチェアのレンタル方法全てをご紹介します。 ハイローチェアをレンタルで用意するなら間違いなく「電動タイプ」を選び、レンタル開始時期は「新生児から」、レンタル期間は「6ヵ月」を選んで下さい。 それは電動タイプのハイローチェアは購入すると5万円以上する商品もレンタルなら半額以下で使用することができ、手動タイプよりもママの負担がぐっと減るからです。 さらにハイローチェアは使用頻度が一番高い時期がお誕生から生後6ヵ月ごろまでのためその時期だけをレンタルで済ますと無駄なくお得に使うことができます。 レンタル料金についてはハイローチェアをレンタルしているショップ主要13社を徹底比較したところ、選ぶ機種によって最安値ショップが異なることが分かりました。ハイローチェアの申込をする時期にあたる妊娠後期から出産直後は何かと忙しい時期。その時期に10社以上あるレンタルショップの中で最安値を見つけ出すことは容易ではありません。 そのため、ここでは2020年3月時点での価格ランキングトップ5をご紹介しますが、値段だけにとらわれないことを強くお勧めします。 それはレンタルは購入する場合と違って、ショップによって品質にかなりの差があるからです。新品を選ばない限り1度以上は別の赤ちゃんが使ったものが届きます。そのためメンテナンス技術や品質管理が重要なポイントになります。 赤ちゃんにはより一層品質にこだわったものを使ってあげたいですよね。でもコストはなるべく抑えたい。そんな相反する願望を叶えるのが品質にこだわったレンタルショップを選ぶことです。 ここではそんな願望を叶えた先輩ママのレンタル体験談も一緒にご紹介します。 この記事を読んで頂ければ間違いなく失敗せずにハイローチェアのレンタルをすることができます。ハイローチェアはママの子育てを助けてくれる魔法のチェア。ママに余裕がありいつも笑顔でいられるなら赤ちゃんも笑顔。笑顔で溢れるHAPPYな毎日。そんな素敵な毎日が過ごせるように最後まで読んでみて下さいね。 1. レンタル前に絶対に知っておきたい3つのポイント 初めてハイローチェアをレンタルする前に絶対に知っておいて頂きたいのが「選ぶタイプ」「使用開始時期」「レンタル期間」の3つ。この3つのポイントを押さえておくのと押さえないのでは便利さ・お得さが断然違います。 購入する場合は予算に応じてタイプを選び、いつ早めに買っておいても問題ないですし、もちろんレンタル期間についても考える必要すらありません。 しかしレンタルの場合は早めに用意してしまっては使っていない期間にも料金が発生してしまうことや、長すぎるレンタル期間はハイローチェアの存在自体が邪魔になってしまうことも。ぜひこの記事を読んで頂いているママパパには便利に無駄なく、そして賢くハイローチェアを使って頂きたいので徹底的にご紹介します。 1-1. お得でママの負担を減らす電動タイプを選ぼう! ハイローチェアをレンタルするならママの負担をより減らし、さらにお得さに差がでる電動タイプを選びましょう。 手動タイプはママがハイローチェアで寝ている赤ちゃんに付きっきりで常に揺らしてあげる必要がありますが、電動タイプならママが少し離れていても自動でゆらゆら揺れて赤ちゃんの寝かしつけをしてくれます。 ママの両手が空けばその間に家事を済ませて済ませてしまうことやホッと一息ティータイムを楽しむこともできますね。 電動タイプをおすすめする理由はこちら 更に電動タイプは購入するよりもレンタルの方がお得さが全然違います! 同じ時期に発売されたコンビのハイローチェアで電動タイプ、手動タイプの6ヵ月レンタル料金と通常購入価格を比べてみました。電動タイプの方が高価なためレンタルで済ませた方が約3万円もお得になることがわかりました。 1-2. レンタル開始時期は必要度が最も高い新生児から! お誕生~6ヵ月頃 ★★★ 最もハイローチェアが大活躍する時期。この時期はまだ赤ちゃんも小さいため寝かしつけに、ちょっとした赤ちゃんの居場所にハイローチェアが必要とされるシーンは沢山あります。 7ヵ月~18ヵ月頃 ★☆☆ 肩ベルトと腰ベルトがついているため家事をしている間の赤ちゃんの安全な居場所として、お食事用チェアとして使用することができます。 19ヵ月~48ヵ月頃...
搾乳器を上手に活用して、無理なくスムーズな母乳育児を実現しよう!
母乳は赤ちゃんの成長のため、赤ちゃんを守るために必要な栄養素が全て含まれる完全食。赤ちゃんの成長と共に母乳の成分も変化し、常に今の赤ちゃんにとってベストな栄養素が作られています。母乳に含まれる成分については、世界中の研究者たちによる研究が日々続けられ、成分の多くは複製することができないとも言われています。 赤ちゃんは完全母乳で育てたいと考えていても、なかなか思うような母乳育児ができないケースも多々あります。特に母乳分泌が少ないという悩みを抱えてる方は多いのではないでしょうか。 母乳は飲んだ分だけ新しく作られる仕組みとなっているため、母乳量を増やすにはできるだけ出してあげることが理想的。分泌が少ない場合は、赤ちゃんが飲む以外にも搾乳器を使ってみることをおすすめします。はじめは少量かもしれませんが、続けるうちに少しずつ搾乳量もアップしていきます。 逆に、母乳分泌が多く乳腺炎などを起こす危険性がある場合にも、搾乳器を使うことでトラブルを未然に防ぐことができます。 不安やストレスのない母乳育児をスムーズに実現するために、おすすめしたいのがメデラの搾乳器。赤ちゃんがおっぱいを飲む自然なリズムを再現し、まるで実際に授乳しているかのように感じることができます。医療機関でも使われている高性能なMedela(メデラ)搾乳器の魅力とラインナップについてたっぷりと紹介していきます。 母乳育児にお悩みのママ、ぜひ最後まで読んでくださいね。 1. 母乳育児を応援するメデラの搾乳器をオススメする理由 メデラの母乳育児用品は、20年以上にわたる研究に基づいて開発されています。徹底した母乳育児への熱い思いを掲げているメーカーであることも、ママたちに絶大な支持を得る理由なんだと思います。 実際に、多くの産院でも使われている信頼性の高い搾乳器で、授乳室などで目にした方も多いと思います。産院で使われている医療機関用の搾乳器は、レンタルもできるので退院後も同じものが使えるという点で、初めての育児にはとても安心ですね。家庭用では、コンパクトでありながら搾乳機能はしっかりと高性能、ラインナップも豊富なのでニーズに合わせて選ぶことができます。また、搾乳器以外でも、授乳時のおっぱいトラブルのケア製品なども充実しているのもうれしいポイントです。 1-1. 母乳育児支援に対する熱い思いと信頼性の高い搾乳器 ママと赤ちゃんの健康へのコミットメント 「Medela(メデラ)は、熱意を持って母乳育児支援に取り組んでいます」 「Medela(メデラ)の目的は、母乳を与えるお母さまをできる限りサポートし、お母さまが母乳育児に関して十分な情報に基づいた判断を下せるよう詳細な情報をご提供することです。」 母乳育児を目指すママたちの心に響く熱い思いですね。このポリシーを元に、ママと赤ちゃんの健康へのコミットメントすることが原動力となって製品開発に尽力しているのがメデラ。実際にオフィシャルサイトでは母乳育児に関する細かな情報がびっしりと提供されています。 研究の旅を続ける 熱意のみならず、長年に渡り研究を続け「研究に基づく」ことが活動の核心。この研究に対するコミットメントもゆるぎないもので、未来に向けた研究の旅を継続していくことを宣言し続けています。 ここまでの熱意とこだわりを持った人たちが開発する搾乳器をおすすめしない理由はありません。 1-2. 病院でも使われている高性能な搾乳器が家庭でも使用できる! 1-2-1. 病院と同じ環境が家庭でも実現できてママも安心!レンタル搾乳器シンフォニー シンフォニーは世界中の産院で採用率No.1の電動搾乳器です。入院先の産院でも目にする方も多いかと思います。母乳の分泌を促すために使用したり、直接授乳ができなかったり難しい場合に使用したりなど、さまざまシーンでの母乳育児をサポートします。全ての方が搾乳器が必要ではありませんが、産院で利用できる場合は、一度使用してみるのもいいかと思います。退院後に授乳トラブルが発生することも多々ありますので、搾乳器を事前に体験しておくと安心かもしれませんね。 病院用の搾乳器のため、一般家庭用としてはレンタルのみでの利用が可能。病院で使い慣れた搾乳器が退院後も自宅で使えるのはとても安心ですね。 1-2-2. 搾乳スタイルに合わせて選べる高性能でコンパクトな搾乳器 退院後にご自宅用として使えるコンパクトな搾乳器。電動タイプと手動タイプとありますので、搾乳頻度やシチュエーションに合わせて選んでいただくことができます。退院直後はレンタルで、その後ご家庭での搾乳スタイルが確率できてから購入を検討してもいいですね。 電動タイプは一度に多く搾乳したい方、常に母乳をストックしたい方、手動タイプは必要な時だけ使う方、母乳量の調整をしたい方など、ご自身の搾乳スタイルに合わせて選んでください。 2. 搾乳器を使うべきか悩んだ時は迷わず使いましょう! 母乳量を増やしたいけど搾乳器はどうなんだろう、母乳育児はできているけど預ける時のために搾乳器を使った方がいいのかな、など、搾乳器を使うべきか悩んだ時は、まず使ってみることをおすすめします。母乳育児が順調であっても、ある時突然必要になることもあるとても重要なアイテムです。搾乳器を使うことで母乳育児がマイナスになることはありません。上手に活用することできっとママも安心して母乳育児を継続していくことができますよ。 2-1. 搾乳器が必要かな?と思うシチュエーションはこんな時 搾乳器が必要なシチュエーションは色々とあります。誰もが必要なものではないのですが、きっと母乳育児のママ誰もが出会うシチュエーションかもしれませんね。例えばこんな場合、という例をいくつかみていきましょう。 赤ちゃんorママが入院しているとき...
新米ママと赤ちゃんのお風呂デビューをスムーズにするための入浴方法
赤ちゃん一緒にお風呂って、どうしたらいいのか・・・不安に思っていませんか? 生まれてすぐは、「沐浴(もくよく)」で赤ちゃんの身体をきれいにすることを、母親学級や産後の沐浴指導で教わったママがほとんどだと思います。「入浴」となると、教わってなーい!ですよね。一体どのように沐浴から、ママと一緒のお風呂スタイルへ移行したらいいか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。 筆者の場合、慣れないお風呂タイム、足りないものを取りに裸のままで慌ててリビングを横切る。なんて、こともたびたびやらかしていました。今になって大変だったこともいい思い出となっています(笑)。ゆっくり自分のボディケアができるなんて、そのころの私には考えられなかったことです。 初めてのお風呂タイムを効率よく終わらせるためには、まずは事前準備がとっても肝心! そこで今回は、赤ちゃんとの初めてのお風呂デビューの方法と注意点、便利なお風呂アイテムと成長に合わせたお世話のポイントを体験談を交えご紹介していきます。初めてのママの不安を解消しつつ、この大変だけど愛おしい赤ちゃん期のお風呂タイムを乗り越えましょう。参考にして頂ければうれしいです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 赤ちゃんとママの入浴手順 一か月健診の診察で、赤ちゃんが順調に成長していれば、「ママと一緒にお風呂に入って大丈夫ですよ~」と、お医者さんから入浴許可がおります。ベビーバスを卒業して、ママと一緒にお風呂に入る時の入浴方法について解説していきますね。 1-1. 入浴前の事前準備をしましょう まずは、入浴の準備をしましょう。準備を怠ると、ママが家中を裸で走り回ることになってしまいます(笑)しっかりと準備して、イメージトレーニングをすれば、ママも慌てなくて済みますね。毎日、同じ時間帯にお風呂に入れてあげましょう。 1-1-1. 浴室・バスタブをきれいに洗います 浴室・バスタブはきれいに掃除をし、お湯を張ります。お湯の温度は38~39度位を目安にしましょう。ここで、注意したいのは追い炊き機能。赤ちゃんと一緒の場合は追い炊きは使用せず、お湯を取り替えてくださいね。 1-1-2. 赤ちゃん用とママ用に着替えなどを用意します お風呂セットを準備しておきましょう。赤ちゃん用に、ベビーソープ(ベビーシャンプー)、ガーゼ2枚、赤ちゃんの着替え、オムツ、バスタオル、ベビーローション(ベビーオイル)ママ用に、バスローブや着替えなど。脱衣所ですぐ着替えさせられるように座布団や大きめのタオルを敷いておきましょう。 1-1-3. ママが先に洗います ママが先に身体や髪を洗います。慣れるまでは先にするのが賢明です。脱衣所で赤ちゃんを待たせておいて、浴室ドアを半分開けてササッと洗うようにします。しっかりお座りができるころには、一緒にお風呂場で遊ばせておきながら、ママが身体を洗えるようになっていきます。 1-2. 入浴の手順を確認しましょう 赤ちゃんをお風呂に入れる手順を確認しましょう。赤ちゃんの洗い方は、沐浴と同じ順番でOKです。おさらいしていきますね。 1-2-1. 赤ちゃんの身体を洗います まずは、赤ちゃんの着ている洋服とおむつを外し、赤ちゃんを仰向けにして抱っこします。滑らないよう気を付けながら、浴室の床にママが座った状態で、赤ちゃんを向かい合う状態で縦抱きにします。この時、直に座ると床がひんやりしますし、万が一のけがの予防に、バスマットを敷いておくと安心ですよ。 肌に優しいベビーソープで身体を洗います。また、髪の毛の量が多く絡まりやすくなってきたらベビーシャンプーを使うようにしましょう。 赤ちゃんの顏→頭→おなか→手足→背中→おしりへ洗います。 洗い終わったら、お湯で流します。この時、シャワーを直接かけてびっくりしてしまう赤ちゃんもいますので、ゆっくりと手桶や洗面器を使って流してあげましょう。 1-2-2. バスタブに3分程度つかって温まります 赤ちゃんを抱っこしてゆっくりとお湯につかります。はじめは、びっくりして泣いてしまう赤ちゃんも、何度か試すうちに慣れてきますよ。 ママの身体に密着させたり、沐浴用ガーゼ(大きめのガーゼ)で赤ちゃんのおなか周りを包むと安心して落ち着くこともあります。 1-3. お風呂から出て服を着せましょう お風呂から上がって、バスタオルで水分をふき取ります。ここで、赤ちゃんが寒さを感じないよう気をつけてあげましょう。ママも体をふき、バスローブを着てしまうと後がラクですよ。 そのあと、赤ちゃんのスキンケアをしてあらかじめ用意しておいた服を着せてあげましょう。 1-4. 水分補給...
月齢別チャイルドシートの失敗しない選び方とおすすめの買い替えパターン
こちらの記事にたどり着いた方、きっとチャイルドシート選びでお悩みですよね。 「何を選んでいいのかわからない!」「必要な機能って何?」「うちの子にはどのタイプが合う?」など、まずはおすすめのチャイルドシートを知りたい!という方も多いのかもしれません。 チャイルドシートは乳児用、幼児用、学童用の他に兼用タイプやブースターシートなど種類が豊富。価格帯もピンキリで幅広く、多くのママパパが商品選びで悩まれるアイテムです。機能性が高く利便性の良いモノが理想ですが、もちろんその分価格は上がるため、どこまで予算をかけるかも悩ましいところです。 まずは、お子さまの安全を守るというチャイルシート本来の目的を果たすための、正しい商品選びの知識が重要となります。今のお子さまの月齢にとって必要な機能を兼ね備えた商品の中から、ご予算も鑑みた上でチョイスしていく、この流れが商品選びのポイントとなります。 そこで当記事では、チャイルドシート選びに重要なポイントを月齢別に徹底的に解説、買い替えのパターンも合わせて紹介していきます。こちらの記事を読んで頂ければ、チャイルドシートの全貌が明らかに!お子様にぴったりな商品が見つかると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 月齢別チャイルドシート選びのポイント チャイルドシート選びに重要な条件としてあげられるのが「安全基準をクリアしている」「子どもの体型にぴったり」まずこの2点。購入の際は国内の安全基準を満たしている商品がどうかを必ず確認しましょう。大切な赤ちゃんを守る第一歩です。次にお子さまの体型に合う商品を選ぶこと。体型に合わないチャイルドシートの使用は、万が一の時にお子さまの命を守ることができないどころか、逆に危険な目に遭わせてしまう可能性が高いのです。 上記の2点は絶対条件とする商品選びのポイントと、それを踏まえたおすすめチャイルドシートを月齢別に紹介していきます。 1-1. 【新生児】小さな体をしっかり守る安全性の高いモノを選ぶ 生まれたばかりの新生児は、まだ首が据わっていなく体の骨なども未熟なため怪我をしやすい時期です。だからこそ、安全性の高いチャイルドシートを選ぶことが重要です。 ◎ Point1:誰でも簡単に確実に設置できる「ISOFIX固定」 チャイルドシートの取付方法は、ISOFIX(アイソフィックス)と車のシートベルトで固定する2パターンがあります。 ISOFIX固定式の場合、ISOFIXバーを座席の差し込み口に差し込むだけで、誰でも簡単に確実にチャイルドシートを設置することができ、取り付けミス(ミスユース)を防ぐことができます。 しかし、シートベルト固定タイプの場合、チャイルドシートの固定方法が複雑なためミスユースが多く発生しています。警察庁/JAF合同の2019年度全国調査によると、全体の57.8%が正しく取り付けができていないという結果も発表されています。(詳しくはこちらをご覧ください) 日本では、2012年7月1日から法令により、車の座席にISOFIX対応の取付金具の設置が義務付けられました。 それにより、2012年7月以降に新車で販売された全ての国産車はISOFIX対応しています。それ以前の車は対応していない場合もありますので、必ず事前に確認しましょう。 ◎ Point2:小さな体をしっかり包み込む「乳児専用タイプ」 新生児から使えるチャイルドシートは、使用期間の短い乳児専用タイプや、大きくなっても使える乳幼児兼用タイプなど様々な種類があります。その中でも新生児時に使用するチャイルドシートとしてオススメしたいのは「乳児専用タイプ」です。 目安の使用月齢は1歳頃までと短いのですが、新生児の体にピッタリと合う設計で必要な機能が備わっています。シートは赤ちゃんの背骨の形になっていて、やさしく包み込む安心のかたち。全身をしっかり守るクッションも備えられ、衝突安全性との兼ね合いも考慮された理想的なシート形状とされています。 乳幼児兼用タイプは新生児期から長い期間使用できますが、大きめシートの中に分厚いクッションを入れ補正して使う仕様になっています。そのため、万が一の衝撃に対しては、分厚いクッションの沈み込みも大きくなり、小さな体にかかる衝撃も大きくなります。 未熟な小さな体を守るためには、より安全性の高い「乳児専用タイプ」をおすすめします。 タイプ別診断でわかる!あなたにぴったりなチャイルドシートの選び方 Joie i-Level ジョイー アイレベル【カトージ】 使用月齢...
手づかみ食べに使いたい!離乳食から使えるひっくり返らないベビー食器
生後5~6ヵ月頃からスタートする離乳食。ママに大人しく食べさせてもらう時期はあっという間に過ぎ、すぐに遊び食べがはじまります。 手でぐちゃぐちゃぐちゃ、スプーンはポイっと投げる、手に届くものはぜ~んぶ触る倒す、せっかく用意した小さく可愛いベビー食器もポイポイされて台なし。 食事のたびに「はぁ~~~」とママのため息が聞こえてきそうな、そんな様子が目に浮かびます。 手づかみ食べ期の「遊び食べ」は赤ちゃんの成長の証であり、それはママも重々承知のこと。だけど、食事のたびにひっくり返ったお皿を片付けて、目も離せない状況はとってもツライですよね。 そんなママにおすすめしたいのが、イージーピージーのひっくり返らないベビー食器! テーブルにピタッとくっついて動かないんです! 赤ちゃんがポイポイしたくても、お皿が動かないから、赤ちゃんんも食事に集中できて、ママの負担も大幅に削減できます。 それだけじゃない! 高品質のシリコンを使用した、耐久性の高い安心安全な食器。電子レンジや食洗器ももちろん使えます。トレーとお皿の一体型だから後片付けもお皿洗いも簡単なのも嬉しいポイント。 そして機能性のみならず、なんと言ってもおすすめなのは、この見た目の可愛さ!おしゃれなデザインに豊富なカラーバリエーション、サイズや形も色々あるのでお気に入りが必ず見つかるはず。 また、お皿の形やトレーも上手に利用してフードアートにもチャレンジ!抜群に映えるプレートはSNSでも注目されること間違いなし! 贈り物にも絶対喜ばれる、イージーピージーの魅力をたっぷりとお伝えします。 1. これはすごい!離乳食から使える革命的ベビー食器「イージーピージー」 小さな赤ちゃんがいたら、絶対に買ってます、私。次に出産祝いを贈る時には、イージーピージーを贈ると決めています。これをもらったら絶対に喜んでもらえる自信があります! 革命的ベビー食器という言葉が正にぴったり。周りにオススメするだけでは事足らず、とうとうブログにまでつづってます(笑) そんなイージーピージーの特長をポイントごとにまとめて紹介していきますね。 1-1. ママのストレスがゼロになる!ひっくり返らないお皿 まず一番の特長である「ひっくり返らないお皿」。テーブルに置くとピタッとくっついて動かなくなります。赤ちゃんがお皿をポイっとしようとしてもできません。マット部分のフチをめくれば簡単にはがれますが、上に引っ張っても動きません。プラスチックなどの軽いお皿でよく起こる、簡単に持ち上げたり、ずれ落ちたりすることが起こりません。 また、お皿とマットが一体化しているため、食べこぼしもマットでキャッチできるし、マットの上に食べ物を置くことだっててきます。こぼすたびに駆け寄ってお片付けすることもなくなるので、ママのストレスもぐぐっと削減できるはずですよ。 1-2. 電子レンジも食洗器もOK!安心安全の高品質シリコン素材 赤ちゃんの食事で使うグッズのため、高品質で安全性が高い素材を使用しています。人体に有害な可能性があるとされているフタル酸・BPA・PVCは不使用。FDA承認の高品質シリコンを使用した、衛生的で耐久性の高いベビー食器です。 耐熱温度は-25度~220度と、耐熱性・耐寒性共に優れ、電子レンジや食洗器にも使えてとっても便利。耐久性も高く長い期間使っていただけます。汚れを寄せにくい性質なので衛生的、トレーとお皿が一体型なのでお皿洗いが一度にできるのも助かりますね。 1-3. カラーやデザインも豊富!インテリアにマッチするおしゃれなベビー食器 機能性バツグンのイージーピージーは、見た目の可愛さも大きな特長のひとつ。豊富なカラーバリエーションからキッチンやリビングのイメージに合うカラーがきっと見つかります。食器棚やキッチンに重ねて置いてもインテリアを邪魔しないおしゃれなベビー食器です。色違い、デザイン(形)違いで色々ほしくなって目移りしそうですが、楽しく選んでくださいね! 1-4. 可愛くて楽しいフードアート!映えるベビー食器でママも遊んじゃおう! 見てください!このキュートなフードアート!見てるだけでもワクワクしちゃいますね! イージーピージーは機能性だけではなく、食事の楽しさも教えてれる食器。こんな楽しいプレートだったら、お子さんのテンションもぐぐっとアップ!楽しいフードアートにはまるママたちも続出するかも?!ハッピーなお食事タイムになること間違いなしですね♪ フードアートはSNSにアップして幸せのシェアをしましょう!映えるプレートは周囲をざわつかせる投稿になりますよ! 2. くっついて動かないベビー食器を動画でみてみよう!...
【画像付き】赤ちゃんと初めての沐浴を成功させるための方法を解説!
初めての出産の大仕事を終えて、赤ちゃんが退院してすぐ初めてのお風呂、沐浴(もくよく)がお世話に加わります!初めてのことで、少し不安になっているママやパパも多いはずです。筆者自身、ベビーバス我が子の沐浴のときは、まだ2500gほどの小さい身体を支えるのに、緊張して身体がガチガチ、腕や腰が痛かった記憶があります(笑) だんだんと、回数をこなしてくると必ず慣れてきますが、はじめてベビーバスでの沐浴が、赤ちゃんを抱き慣れないママやパパにって難しく感じることがあると思います。 この記事を読んでいただければ、初めてでもスムーズに沐浴を行うことができます。赤ちゃんとの毎日が、よりよいものとなりますように。参考にしていただけると嬉しいです。 1. 初めての沐浴をスムーズに行う方法 沐浴に必要なものをあらかじめセットしておくと、スムーズに沐浴をすることができます。順を追って沐浴の流れを解説していきますね。 1-1. 沐浴の手順 手順1:着替え、バスタオル、ケア用品を準備する バスタオルを広げ、肌着と服を重ねて両腕を通しておき、おむつも広げておくと湯上がりにサッと拭いて着替えさせることができます。あらかじめしっかり準備をしておけば、ママもあせらずに入れられますね。 手順2:お湯の温度を確認する お湯の温度の目安は、夏場は37~38度。冬は39~40度です。熱すぎずぬるすぎない温度が適温です。湯温計で測るだけでなく、必ず大人が触って確認します。 手順3:お湯に入れる 赤ちゃんを驚かせないようにお湯に入れます。赤ちゃんの後頭部に手のひらで差さえ、耳の後ろに、親指と人差し指を添えるようにします。利き手でおしりを支えて抱っこが一般的な抱っこスタイルです。仰向けに抱っこして体にガーゼをかけ、足からお湯に入れます。いきなりジャボンとつけるとビックリするので足からゆっくり入れましょう。 手順4:全身を洗う 洗い方の基本は、「上から下、きれいなところから汚れているところへ」5分ほどで洗います。 [1]絞ったガーゼで顔を拭く やさしく目頭から目じりへ、3を書くように、おでこ→ほっぺた→あごへ、おでこから鼻先へ、口周りをぐるっと、やさしくぬぐいます。 [2]ガーゼで頭を洗う ベビーソープを使って、利き手に泡を付けて、おでこの周り→耳の後ろ→頭部へやさしく洗いましょう。 [3]首、胸、おなか、腕、手、足を洗う 首やワキ、手のひらなどは汚れや垢がたまりやすいので、指を入れて汚れを落とします。 [4]背中を洗う 赤ちゃんのワキの下に手を入れて手首に赤ちゃんのアゴがのるようにして、赤ちゃんを裏返して背中やおしりを洗いましょう。ここで、大きく体勢が変わるので動きか激しくなる赤ちゃんは多いと思います。手早く済ませるようにしましょう。 [5]性器を洗う 再び、赤ちゃんを仰向けにさせて、性器を洗います。排便回数も多い時期なので、汚れが残ってしまうと肌が荒れてしまうことも。見えにくい部分をよく洗ってあげましょう。 手順5:上がり湯をかける 清潔な手おけや洗面器を使って、上がり湯をかけてあげましょう。 手順6:バスタオルで全身を拭く バスタオルにくるんで、そっと水分をふき取ります。首やワキなどくびれが多い部分も、しっかり拭きましょう。 1-2. 入浴後のケア 入浴後は赤ちゃんの身体をケアしましょう。その後、服を着せて水分補給を。...
3歳はジュニアシート?体型別おすすめのチャイルドシート10選
3歳頃になるとチャイルドシートの買い替えを検討される方が多いようですね。その理由としては、今まで使用していたチャイルドシートが窮屈になってきたり、下の子が生まれるなどがあげられます。 3歳頃に使用できるチャイルドシートは主に 1:幼児学童用『チャイルドシート』 2:学童用『ジュニアシート』 3:ブースターシート の3タイプに分けられます。 チャイルドシートとジュニアシートは、ぱっと見の違いが分かりにくいですよね。 ジュニアシートも「3歳~」となっている物がほとんどのため、3歳児はチャイルドシートかジュニアシートか、どちらを選ぶべきか迷われる方が多いようです。 買い替えの商品選びで最も重要なポイントは「子どもの体型に合わせた商品選び」です。 どんなにデザインや機能が優れている物でもお子様の体型に合っていなければ、安全を確保することができません。対象年齢はあくまでも目安。年齢で決めるのではなく、必ず体型に合わせて決めることが大切です。 そこで今回は、体型別のおすすめチャイルドシートや使用する前に知っておくべき基礎知識など、商品選びに役に立つ情報を紹介します。 こちらの記事を読んで頂ければ、お子様にぴったりなチャイルドシートが見つかります。ぜひ参考にしてみてください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 3歳から使えるチャイルドシート3タイプ まずは、3歳から使えるチャイルドシート3タイプについて概要を解説していきます。 1-1. タイプ1『幼児学童用:チャイルドシート』 ■5点式ハーネス&背もたれ付き ■使用月齢:約1才~11才頃まで チャイルドシートの付属する5点式のハーネスでしっかりとお子さまをホールドします。ジュニアシートの基準身長に達するまでは必ずインナークッションを使用して小さな体を守りましょう。 1-2. タイプ2『学童用:ジュニアシート』 ■ハーネスなし&背もたれ付き ■使用月齢:約3才~11才頃まで 車のシートベルトを使ってお子さまをホールドします。対象月齢になっても体の小さなお子様は使用できません。必ず基準体型を超えてから使用しましょう。 1-3. タイプ3『ブースターシート』 ■ハーネス&背もたれなし ■使用月齢:約3才~11才頃まで ブースターは3歳から使用可能としている事が多いですが、基本的には身長140cm以上にまだ満たない子どもが座席の高さをカバーするためのアイテム。安全のためにはできるだけ背もたれ付きを使用しましょう。 2. ジュニアシートは身長100cm体重15kg以上から使用しましょう ジュニアシートは、一般的に身長100cm以上、体重15kg以上の子どもを対象に作られています。その基準を満たしていなければ、本来の機能を発揮することも安全の確保もできず、万が一のときに大切なお子様を守ることができません。 チャイルドシートからジュニアシートへ移行するタイミングは、年齢ではなくお子様の体型に合わせる事が大切です。...
赤ちゃんが快適に車移動できるリクライニング式チャイルドシート8選
赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるときに、背もたれを倒した状態で座らせられるチャイルドシートはないか、お探しではないですか? ナイスベビーでチャイルドシートをご利用されているお客様の中でも、首がぐらぐらしているから、背もたれを倒せるチャイルドシートはないですか?と、ご相談を受けることがあります。 後部座席で後ろ向きで座っていると運転中のママからは、赤ちゃんの様子をすぐ確認することができないため、不安に思うこともあると思います。 赤ちゃんを守るために設計されているチャイルドシートは、万が一の事故を想定して、従来は座面に対して45度の角度で固定するというのが常識でした。最近では、リクライニングでシートの角度を調整できて、かつ、安全性も兼ね備えた商品が改良され発売されるようになってきています。 ここでは、シートを倒したり起き上がらせたり、リクライニングできる機能を備えたチャイルドシートのおすすめと選び方をご紹介します。ご家庭のライフスタイルに合ったチャイルドシート選びの参考にして頂ければ幸いです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. リクライニング機能の要不要を月齢別に解説! リクライニングの機能は、月齢によってあった方がいいかどうか分かれます。安全を考慮した上で、リクライニングが必要かどうかを詳しく解説していきます。 1-1. 誕生~5か月頃 首のすわらない赤ちゃんに、リクライニング機能は必須ではありません。 リクライニングしないチャイルドシートは、一見、窮屈そうに見えてしまうかもしれませんが、赤ちゃんは苦しくはありませんのでご安心下さい。シートは赤ちゃんの背骨の形になっていて、やさしく包み込む安心のかたちです。さらに衝突安全性との兼ね合いも考慮された理想的なシート形状とされています。 リクライニングするチャイルドシートは、一般的に座面が動いて角度を変えられるタイプが多いですが、最近では、背もたれを倒して使用できるシートや、ベッドのようにフラットにできる商品も出てきています。安全の為にも、リクライニングの角度を調整した後は、しっかりと固定されているかハーネスが適切かどうか確認して下さい。 適切に正しく使用すれば、いずれの形も安全基準を通過していますので、パパやママは安心して使用できるシートです。製品のグレードによって値段も大きさや重さも異なりますので、ご家庭のライフスタイルで選ぶようにしましょう。 1-2. 生後10か月頃~ 腰がしっかりしてきた赤ちゃんには、リクライニング機能があると便利です。 このころの赤ちゃんは、仰向けの姿勢を嫌がり、体を起こしたがりぐずってしまうことも多いと思います。例えばベビーカーで言うと、セーフティーバーに手をかけて前のめりの姿勢をとる赤ちゃんは多いのではないでしょうか。腰がしっかりすわってきたら、背もたれを起こしてあげられるような角度調整機能があるとぐずり防止にもなり便利です。 このとき、赤ちゃんのおしりの位置ずり落ちないようにして、適正位置に座ってハーネスをしっかり締めるようにしてください。 1-3. 1歳半頃~ 移動中寝てしまったら背もたれを倒せるリクライニング機能があると便利です。 チャイルドシートに座ったまま、よく眠ってしまうことがよくあるお子様には特におすすめできます。車内で寝落ちしてしまった赤ちゃんは、背もたれを倒してあげることができます。製品によっては、座ったままリクライニングできるものとそうでないものがありますので購入前に確認しておきましょう。 筆者の経験ですが、子どもが寝おちして頭が垂れ下がった姿を見ると「背もたれを倒してあげたい」と思うより「やっと寝たのに、起こしたくない」と思うことの方が勝ってしまい、そっとしておくことが多かったです(笑)。ナイスベビーでは、こんなうたた寝をサポートできるアイテムをご紹介しています!リクライニングしないチャイルドシートをお持ちの場合は、買い替えるよりお得ですね! Nap Up うたたねサポート(日本育児) 2. リクライニング式チャイルドシート3つの確認ポイント! リクライニング式のチャイルドシートは、商品によって扱い方が異なります。次の3つのポイントを確認してから購入を検討しましょう。 2-1. 操作が簡単か確認しましょう! リクライニングの操作方法は、赤ちゃんを乗せたままワンタッチで角度を変えられるタイプがとくに簡単です。赤ちゃんを乗せたままリクライニング操作できないものもあり、チャイルドシートを固定する前に角度調整するタイプの場合、赤ちゃんを一度降ろしてからリクライニング操作をするものも。各メーカー、商品やグレードによっても異なりますが、簡単に操作できるものかどうか確認しておきましょう。 2-2. どのくらい角度を調節できるか確認しましょう!...
2歳で買い替えるならこれ!チャイルドシートを選ぶための4つの条件
最近、使用しているチャイルドシートが小さくなってきた?窮屈そう?とお悩みではないでしょうか? 現在日本で1番売れているチャイルドシートのタイプは「乳幼児兼用タイプ」。使用期間は新生児~4歳頃までとされるものが多く、長期間に渡り使えることが人気の理由です。しかし、実際には2~3歳頃で窮屈に感じるようになり「思っていたよりも長く使えなかった」と予定よりも早めの買い替えを検討する方が多いようです。 コストが抑えられること、コンパクトで使い勝手の良さなどから、買い替えのタイミングでジュニアシートやブースターシートを使い始める方もいます。しかし、ジュニアシートの利用基準は身長100㎝以上、体重15㎏以上(目安年齢は3歳~4歳頃)が一般的。2歳児の平均的な体型ではこの基準には達していないため、早めの使用はおすすめできません。体型に合わないチャイルドシートの利用は、万が一の時のお子さまの身を守ることができません。安全性を第一に考え体型に合ったチャイルドシートを選ぶことがもっとも重要です。 今回は、2歳児のためのチャイルドシートの選び方について、選ぶ際のポイントとおすすめ商品、意外と見落としがちな買い替える前の注意点も紹介していきます。この記事を読んでいただければ、2歳児にぴったりの理想的なチャイルドシートに出会えるはずです。最後まで是非読んでくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 2歳からのチャイルドシートを選ぶための4つの条件 2歳といえば、段々と自分でできることも増え、イヤイヤの自己主張も強くなってくる頃ですね。日々成長し身体もしっかりしてきますが、思考能力はまだまだ未熟。走行中はチャイルドシートにきちんと座わらないといけないという理解はなかなか難しいですよね。簡易的なチャイルドシートの場合、ベルトを外してしまったり抜け出してしまう事も多々あると思いますが、まずはこの時期に「きちんと座る」という事をしっかり教えてあげましょう。 この章では、2歳からのチャイルドシート選びにおいて、安心して使用できる4つのポイントを解説していきますので参考にしてください。 1-1. 5点でしっかりと体を守る5点式ベルト 車のシートベルトではなく、チャイルドシート本体についた5点のベルトでお子様を守るのが5点式ベルト。左右の鎖骨、骨盤、股下の5カ所をハーネスでしっかりと支え、衝撃を分散・吸収させることができます。未熟な小さな体を5点式ベルトがしっかりと守ってくれます。また、股ベルトがあることで、姿勢が崩れてもお尻が前にずれることがなく、安全な姿勢を保つことができるので、万が一の時のリスクも大きく軽減できます。 4歳頃まではこの5点式ベルトを使用し、それ以降に3点式ベルトに移行しましょう。体の小さなお子様はジュニアシート利用の基準体型に達するまでは5点式ベルトを使用することをおすすめします。 1-2. 高さ調節ができるヘッドレスト 強い衝撃から小さな子どもの頭を守れるようにヘッドレスト付きのものがおすすめです。クッション性のあるシートで前後左右の揺れや横倒しになってしまうことを防ぐことができます。さらに日々急成長する子どもの体型にいつでも適切な位置で使用することができるよう、ヘッドレストの高さを調節できるものを選びましょう。 1-3. 身長140㎝まで長く使える 車のシートベルトは身長140㎝以上の体型に合わせた設計となっています。チャイルドシートの着用義務は6歳未満ですが、身長140cmになるまではチャイルドシートを着用し続けることを推奨します。 体型に合わせてこまめに買い替えることは理想的ですが、コストもかかるため現実的ではありません。長い期間使用できるタイプとして、2歳のチャイルドモードからジュニアモードへ、そして大きくなったら背もたれを取り外しブースターシートとしても使用できるものがおすすめです。 1-4. 安全基準をクリアしている チャイルドシートを選ぶ条件として最も重要なことが「国の安全基準をクリアしていること」です。日本の販売店で売られている製品は全て安全基準を満たしており、必ず安全基準に適合されている事を示すマークが記載されています。しかし、インターネット通販においては条件を満たしていない「未認証チャイルドシート」や安全基準マークの記載がない状態で販売されているケースもありますので注意が必要です。安全が保障されていない製品は絶対に使用してはいけません。メーカー公式HPには必ず記載がありますので、事前に確認するようにしましょう。 安全基準について詳しくみる 新生児から使えるチャイルドシートには座面の角度を変えたり、リクライニング機能のついているものが多いですが、進行方向を向いて座るタイプのほとんどはリクライニングすることができません。基本的には車のシート自体を倒すことでチャイルドシートの背もたれも一緒に倒します。ただし、倒し過ぎは安全性が低くなるため要注意!安全が確保できるチャイルドシートの角度を守りながら調整するようにしましょう。 2. 全ての条件をクリアした究極のチャイルドシートはこれ! 前章で紹介したチャイルドシートを選ぶための4箇条をすべてクリアした究極のチャイルドシート4つを紹介します。 ジョイトリップ エッグショックGH【コンビ】 超・衝撃吸収素材搭載!快適性も安全性にもこだわったシート ・たまごも割れない超・衝撃吸収素材「エッグショック」搭載!衝撃から子どもの頭を守ります。 ・長時間のドライブでも快適!風が通る3Dメッシュシート採用。小さい身体にしっかりとフィットします。 ・洗濯機で丸洗いOK!汚れやすいシートがいつでも清潔に保てます。 ・成長に合わせて子どもの肩の位置でベルトを合わせることができる「ベルトポジショナー付き」 ・省スペース設計で車内も広々!家族みんながゆったり座れます。...
タイプ別診断でわかる!あなたにぴったりなチャイルドシートの選び方
赤ちゃんにとって居心地が良く安全。さらにママにとっては使いやすいベストなチャイルドシートを選びたいけど、種類が沢山あってどれを選んでいいかわからないと悩んでいませんか? ここで紹介する流れの通りにチャイルドシートを選んで頂ければ、赤ちゃんが快適なだけではなくご自身のライフスタイルにあったものを選ぶことができます。 毎月300台以上のチャイルドシートをお客様の元にお届けしているベビー用品のプロが紹介する最低限外せない3つのポイントを押さえ、そこからご自身の生活に合わせて機能の取捨選択を! 機能の取捨選択がしやすいように1クリックでわかるタイプ別診断もご用意しました。 あなたに近い生活スタイルのタイプをクリックすれば、手軽に簡単にぴったりなチャイルドシートがみつかります。 ベストな1台をみつけるために! まずはチャイルドシートの種類やそれぞれの特徴について知っておきましょう。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 安全なチャイルドシートを選ぶ際に絶対に外せない3つのポイント チャイルドシートを選びには、デザイン・サイズ・予算・リクライニング・機能など選ぶポイントはいくつかありますが、その中でも絶対に外せない最も大切なものは、以下にあげる3つのポイントです。 [1]チャイルドシートのタイプ [2]車への取付方法 [3]安全基準 まず最初に考えて頂きたいことは、チャイルドシートは「大切なお子様の命を守る安全装置」であるということ。万が一の際にその力を発揮できなければ車に取付している意味が全くありません。 そこで今回は、チャイルドシート選びに絶対に外せないポイントを詳しく紹介していきますので、ご自身にぴったりの安全で使いやすいチャイルドシートを選ぶ参考にしてください。 1-1. チャイルドシートのタイプを選ぶ 1-1-1. チャイルドシートの「機能」を知ろう! 新生児から使用できるチャイルドシートは大きく分けて3つのタイプがあります。 1:キャリータイプ 赤ちゃんを乗せたまま持ち運びができる 2:座席回転タイプ シートが360度回転し、赤ちゃんの乗せ降ろしがラク 3:座席固定タイプ 上記1・2の機能がない一般的なもの まずはそれぞれの機能について知って頂き、その上でご自身が一番必要とする機能を選んで下さい。それぞれ3タイプの詳細は3章・4章・5章でご紹介し、どうやって選ぶかは2章でタイプ別診断でご紹介します。 1-1-2. チャイルドシートの「使用期間」を知ろう! 機能を選ぶと自然と使用できる期間が決まってきます。機能と使用できる期間を照らし合わせて総合的にみたときにどのタイプのチャイルドシートを選ぶか決めましょう。 使用できる期間については大きく分けて2つのタイプがあります。 1:専用タイプ 誕生後すぐから生後15ヵ月まで...
眠った赤ちゃんと一緒にお出かけOK!憧れのトラベルシステム徹底解説
初めてのチャイルドシート選び、どんなタイプがいいかたくさん種類があって、本当に悩みますよね。 リサーチを重ねるうちに、ベビーカーにセットして移動できるチャイルドシートの存在に出会ったのではないでしょうか。 この画期的なシステムは「トラベルシステム」と呼ばれています。 欧米では生活に浸透しているシステムで特に新生児期に多く利用されています。日本国内でもここ数年で、おしゃれなママパパの間で話題となり人気で上がってきています。 乳児専用チャイルドシートは、ベビーシートとも呼ばれており、車で移動する時だけでなく、ベビーキャリーやロッキングチェア、ベビーチェアとしてマルチに使用できる様につくられています。 これをトラベルシステム対応のベビーカーにドッキングさせることで、赤ちゃんを乗せたまま移動できるのが一番の魅力です。 とっても便利そうなトラベルシステムですが、ご家庭のライフスタイルによっては、向き不向きもあり、選ぶ前には注意が必要なんです。 ここでは、トラベルシステムの便利な5つの機能と合わせて事前に知っておきたい注意ポイントを詳しく解説していきます。また、国内外のトラベルシステムの取扱いメーカー、実際使ってみたママの体験談も紹介します。 トラベルシステム対応のチャイルドシートを検討中のママやパパに、この記事が参考になればうれしいです。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. トラベルシステムの便利な5つの機能 トラベルシステムは、アクティブに外出の多いご家庭におすすめのベビー用品! 1台で5役(ベビーカー、チャイルドシート、ベビーチェア、ロッキングチェア、ベビーキャリー)こなせる大変便利なモデルです。 赤ちゃんとのお出かけの多いご家庭で活躍が期待されるトラベルシステムの5つの機能をご紹介します。 1-1. 退院時、病室からそのままチャイルドシート 赤ちゃんとの出産退院時に、まだ首のすわらない赤ちゃんにシートベルト(ハーネス)をするのは、緊張もすると思いますが、病室でゆっくりチャイルドシートに乗せて、そのまま車にシートベルト固定することができます。実家の車やタクシーでの移動にも使用できるので便利です。車にあらかじめ専用のベースを取り付けておけば、さらに簡単確実に取付できるのでより安全です。 1-2. 眠ったまま移動OKのベビーキャリー 赤ちゃんが車の中で眠ってしまっても、無理に起こさずそのまま家の中まで運ぶことができるのは本当に便利です。 特に、首のすわらない赤ちゃんを抱っこするのは気を使いますし、子育て中はママパパにとっても赤ちゃんがすやすや眠っていてくれる時間は本当に貴重。なるべく起こしたくないし、この隙に、ホッと一息入れたいですよね!持ち手のついたベビーキャリーならそれが叶います。 1-3. リビングでゆらゆら揺れるロッキングチェア 外出時以外でも家の中で多機能に使うことができます。 ご機嫌な時も寝入る直前も、シートのそこが湾曲しているので、ゆらゆら揺れてあやすことができます。家事をするときもママのお風呂待ちの時も目の届く場所に赤ちゃんを寝かせておくことができます。使用期間の短いクーファンやバウンサー代わりにもなるので、結果的に経済的で省スペースなのも魅力的ですね。 1-4. 外出先でも赤ちゃん特等席のベビーチェア 外出の時にも赤ちゃんのお座りスペースを確保できます。 腰がすわっていない赤ちゃんと抱っこしながら外での食事は大変ですよね。レストランなどに常備されているベビーチェアは腰がしっかりしてから使えるタイプがほとんどです。そんな時、ベビーチェアとしてソファー席や座敷にも持ち込むことも可能です。 赤ちゃんを座らせたまま持ち運びできるので、実家やお友達の自宅に遊びに行くときなども大活躍してくれます。 1-5. 新生児から乗せられるベビーカー チャイルドシートを乗せる専用ベビーカーを用意すれば、対面式のベビーカーに早変わり。駐車場と自宅が離れている場合、荷物をもって赤ちゃんを抱っこして。。と大変な苦労も、赤ちゃんをベビーカーに乗せ換えの手間が少なく移動できるのでママの負担が軽減しますね! メーカーによっては、背面式の専用ベビーカーに取り付けできるものもあります。チャイルドシートは生後1歳ごろまでのものが一般的ですが、ベビーカーとして3歳ごろまで使えるのでとても経済的ですね。 2. トラベルシステムを選ぶ前に知っておきたい4つのこと...