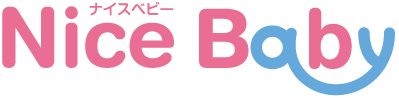ベビー用品
ベビーサークルいつからいつまで?必要期間と使いこなすコツ【体験談あり】
ハイハイが始まり赤ちゃんが自分で動けるようになると、知らぬ間に危険な場所へ近づいてしまったり、危ないものを口に入れてしまったり、ハッとする場面に出くわすことが多くなります。 ベビーサークルは、目の離せない時期の赤ちゃんの安全が確保でき、ママパパが一人で育児をするときに特に役立つ子育てアイテムです。 しかし、買ったはいいけど、赤ちゃんが嫌がって使えなかった...と失敗談を聞くことも多いベビーサークル。そのまま押し入れ行きとなり眠ったままになっているのでしょうか>< 実は、諦める前にやってみる価値ありの「使いこなすコツ」もあるようです! 今回は、先輩ママパパが実践し成功したサークルを使いこなすコツについて、口コミを元にその技を紹介します。また、サークルの使用時期や卒業のきっかけなどについて聞いたアンケート調査の結果も公開、参考になる体験談も紹介していきます。 この記事を読んで頂ければ、ベビーサークルの使用期間と、はじめに知っておきたい有効的な活用方法が分かります。お得に賢くベビーサークルを使うために、是非最後まで読み進めてくださいね! あわせて読みたい! 【先輩ママ体験談】ベビーサークルが必要な3つの理由と便利な使い方 赤ちゃんが一人遊びができるようになると、赤ちゃんの遊び場として部屋にキッズコーナーを作ってあげたいな~と思いますよね。大好きなおもちゃを置いて楽しく遊べてお昼寝もできる安全な空間があるって、いいで... ナイスベビーラボ 2024.06.09 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 先輩ママパパに聞いた!ベビーサークルの体験談 ベビーサークルを使用したことのある先輩パパママ100人に「ベビーサークルの使用期間について」アンケート調査を実施!使用期限は商品ごとで差がありますが、いつからいつまで使うのか、いつ撤去したかなどについて聞きました。それでは、ベビーサークルユーザーの体験談をみていきましょう。 1-1. ベビーサークルはいつから使い始めましたか? ベビーサークルの使い始めの時期についてのアンケートでは、全体の74%が生後6ヵ月~9ヵ月未満という結果になりました。ハイハイや伝い歩きができたころからの必要になって準備することが多いようです。 1-2. ベビーサークルは、いつまで使いましたか? 1歳以上2歳未満までに、ベビーサークルの使用を終了しているというママパパが56%以上と過半数。1歳未満で終了のご家庭も22%と早めに終了を迎えるケースもあるようです。3歳以上使えるご家庭はごく少数との結果に。大型のベビーサークルは、2歳になるころまでには終了の時期が来るようですね。 1-3. ベビーサークルを終了する時のきっかけはありましたか? 「上の子がちょっかいを出さなくなったのでサークルの使用を終了しました。」 「1歳5か月になったころ、力がついてくると中でサークルを押すように・・・。形が変形してしまってサークルの役目がなくなってしまったから。」 「引越しのために、ベビーサークルは使わなくなりました。」 「子どもの身体が大きくなり、サークルが狭く感じられるようになってきたから。」 「自我の芽生えか、ベビーサークルに入るのをとにかく拒否するようになったため。」 「ベビーサークルに入っていることに飽きて、おもちゃを踏み台にして脱走してしまうようになったため。」 「子どもが大きくなってきて、乗り越えてきそうで危なかったから。」 「大人の言うことや危ない場所がわかるようになったから。」 やはり終了の目安としては、身体が大きくなったことで柵を越えてしまったり、大人の言うことを理解し始めるころににきっかけがあるようです。 1-4. ベビーサークルがあってよかった点、エピソードを教えてください。 「やんちゃな兄弟がいる我が家では、大活躍でした。上の子供からのいたずらから赤ちゃんを守ることができました。」...
新生児に安心♪横抱き抱っこ紐の魅力を徹底解説!おすすめ8選も紹介
さまざまな種類が発売されている新生児から使える抱っこ紐。 各メーカーが研究を重ね開発され、抱っこ紐は日々進化を遂げています。新生児でも安心して縦抱きもできる魅力的な商品は多々あるものの、実際、首座り前の縦抱きに不安を感じる方も多いようです。そんなママパパの不安を解消するのが「横抱き抱っこ紐」。生まれてすぐの赤ちゃんを横にしたままキャリーできる安心の抱っこ紐です。 産院からの退院時からすぐに使用でき、その後の首座りまでの期間、赤ちゃんをしっかりホールドしてくれるアイテム。1ヶ月検診、ご家族の行事ごとなど、小さな赤ちゃんを連れて外出しなければならない時、また、寝かしつけの時にも大活躍します。中には「抱っこ紐の横抱き機能が欠かせない」という方もいるほど。 赤ちゃんを寝かせた姿勢で抱っこできる横抱き抱っこ紐は、赤ちゃんもママパパも快適に安心して使用することができます。 今回は、横抱き抱っこ紐について、その特徴や種類を解説、おすすめ商品も紹介!横抱き抱っこ紐の魅力をたっぷりとお伝えしていきます。ご自身に合うアイテム選びの参考に、是非最後までお付き合いくださいね。 それでは早速みてきましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 新生児から安心して使える横抱き抱っこ紐 新生児から使える「縦抱き」抱っこ紐でも、長い期間使えるタイプは人気のアイテムです。メーカーにより仕様は異なりますが、長い期間使えるタイプは新生児が使うには大きすぎて、使えないことも多いのが現状です。購入したはいいけど新生児には使えず、別のものを購入したという声も多く聞こえます。実際、今この記事を読んでいただいている方の中にも、いらっしゃるかもしれませんね。 小さな赤ちゃんにフィットするのはやはり新生児専用のタイプ。ここでは、横抱き抱っこ紐の気になる使用期間や縦抱き抱っこ紐との違いについて解説していきます。 1-1. 横抱き抱っこ紐最大のメリットは「安心」 新生児期のお出かけは少ないものですが、1ヵ月検診を過ぎたころから徐々に外出の場面も増えてきます。 首すわり前の赤ちゃんとのお出かけに、赤ちゃんの体に負担のかからない姿勢の横抱きは、ママパパも安心。移動はもちろんのこと寝かしつけの際にも利用できます。1日の多くを寝て過ごす新生児にとって横抱き抱っこ紐は、うってつけの抱っこ紐といえるでしょう。 横抱き抱っこ紐の多くは縦抱き抱っこ紐としても使用することができます。赤ちゃんの成長に合わせて使い分けることができるのは嬉しいポイントですよね。 縦抱き抱っこ紐には、赤ちゃんの頭や首をしっかりと支える専用クッションが付属しているものなども多く販売されています。赤ちゃんの自然な姿勢を保てる抱き方ができて、首すわり前でも安心して使える構造の商品を慎重に選びましょう。装着方法が誤っていれば赤ちゃんの首やカラダに大きな負担がかかることもあります。説明書をよく読んで、取り扱いには十分に注意しましょう。心配な方は、安定感のある横抱き抱っこ紐がオススメです! 1-2. 生後6ヶ月頃まで使える!横抱き抱っこ紐の使用期間 一般的に抱っこ紐の横抱き期間は、新生児~6ヶ月頃までが目安。首がすわり始める3~4ヵ月頃には横抱きは卒業、赤ちゃんもずっしり重たくなるこの時期に、縦抱きやおんぶに移行するママが増えます。 首がしっかりとしてきて、横抱きが使いにくくなったら「縦抱き」や「前向き」「おんぶ」など多機能でその後も長く使えるタイプの抱っこ紐の購入を検討するとよいでしょう。 生まれて初めての行事「お宮参り」にも横抱き抱っこ紐が便利! 生後31日、32日で行うお宮参りにも横抱き抱っこ紐が活躍します。 お宮参りは一般的に赤ちゃんを抱っこして、その上から和装をかけます。神社への移動や参拝、ご祈祷中など長時間の抱っこが必要です。横抱き抱っこ紐を使用すれば、赤ちゃんも抱っこしている人にとっても負担が軽減されます。 お写真を撮るときは抱っこ紐を外して、ご祈祷などは横抱っこ紐を活用するとよいでしょう! > 簡単・綺麗に着られるお宮参り着物の着せ方 2. タイプで選ぶ自分に適した横抱き抱っこ紐 縦抱き抱っこ紐に比べ、横抱きできる抱っこ紐は、各社から発売されてはおらず種類も限られています。 種類としては主に「キャリータイプ」と「ベビースリング」の2タイプ。ここでは、それぞれどのような特長があり、どのようなご家庭にオススメなのかタイプ別にご紹介していきます。 2-1. 安定感抜群!これ1本で長い期間使えるキャリータイプ ★ こんなママにおすすめ...
ベビーサークルはいつまで?赤ちゃんの成長で見る止め時と卒業体験談
この記事にたどり着いたのは、ベビーサークル撤去のタイミングについて疑問を持たれている方ではないでしょうか?一般的にいつごろまで使ってるものなのか、他のご家庭の様子も気になりますよね。 忙しいママパパにとって、ベビーサークルは心強い子育てお助けアイテム。家事を効率よく安心して進められることが最大のメリットですね。しかし、部屋を占拠するアイテムなので、生活上の動線の障害になるというデメリットもあります。さらに、赤ちゃんがぐずって大泣きしている時は、心苦しくも思える場面も出てきたり...。 便利だけど、撤去できたらスッキリするだろうな~、なんて思いが頭をよぎりますよね。卒業のサインや具体的なタイミングも知ることができたら、モヤっとした思いもなくなるかもしれません。 そこで今回は、ベビーサークルの撤去時期は一体いつなのか、ベビーサークル使用経験者のパパママへ、卒業時期についてのアンケート調査を実施、使用を止めるきっかけとなったエピソードも集めました。 また、赤ちゃん成長に伴う行動範囲の広がりやいやいや期などの情報をもとに、終了の目安について徹底解説、サークル撤去後の家の中の安全対策についても紹介していきますので、ベビーサークルの使用終了を検討中のママパパは是非参考にしてくださいね。 ベビーサークルが必要となるこの時期は、ハイハイからひとりで歩けるようになるまで、ほんの数カ月間に驚くほどの成長を遂げます。しっかり歩けるころには、意思疎通も少しずつできるようになっていきます。大人の言うことを徐々に理解し、危険な物事も実際の経験と共に覚えるころ、ベビーサークルの役目も終わりを迎えるのかもしれませんね。 あっという間に大きく成長する赤ちゃんを見守りつつ、ママパパも安心して子育てのできる環境を整えていきましょう。是非最後まで読み進めてくださいね! 1. ベビーサークルの使用終了は1~2歳未満が過半数! ベビーサークルを使用したことのある先輩パパママ100人に「ベビーサークルの使用終了時期について」アンケート調査を実施!使用を終了した時期、また、終了したきっかけについて聞きました。では、結果を見ていきたいと思います。 1-1. ベビーサークルは、いつまで使いましたか? 1歳~2歳未満までに、ベビーサークルの使用を終了しているというママパパが56%以上と過半数を超えました。少数ですが、1歳未満で終了のご家庭も22%と早めに終了を迎えるケースもあるようです。2歳~3歳以上使えるご家庭も20%と少ない結果に。 1-2. ベビーサークルを終了したきっかけを教えてください。 「上の子がちょっかいを出さなくなったのでサークルの使用を終了しました。」 「1歳5か月になったころ、力がついてくると中でサークルを押すように・・・。形が変形してしまってサークルの役目がなくなってしまったから。」 「引越しのために、ベビーサークルは使わなくなりました。」 「子どもの身体が大きくなり、サークルが狭く感じられるようになってきたから。」 「自我の芽生えか、ベビーサークルに入るのをとにかく拒否するようになったため。」 「ベビーサークルに入っていることに飽きて、おもちゃを踏み台にして脱走してしまうようになったため。」 「子どもが大きくなってきて、乗り越えてきそうで危なかったから。」 「大人の言うことや危ない場所がわかるようになったから。」 やはり終了の目安としては、成長して身体が大きくなったことで柵を越えてしまったり、大人の言うことを理解し始めるころににきっかけがあるようですね。 2. 赤ちゃんの成長でみるベビーサークル終了の目安 前章では、先輩ママパパのアンケートの結果を紹介しましたが、実際の成長ペースは月齢で区別されることではなく、お子様によって個人差があります。これからお子様の成長の段階において、目安となる行動や心理、人とのかかわりについて参考資料をもとに解説していきますので参考に見ていきましょう。 2-1. 1歳前後から2歳未満までの発達過程の例 0歳児の発達(9ヵ月頃から12ヵ月頃) ・「いないいないばぁ」をすると喜ぶ。 ・褒めてもらうと喜んだり、叱られたことが分かったりする。 ・つかまり立ちをしたり、伝い歩きをしたりする。 ・はいはいや高ばいで階段の上り下りをする。 ・はいはいからお座りが自由にできるようになる。...
『子育て本音トーク vol.7』使ってみた!抱っこ紐編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第7弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第7弾は「抱っこ紐」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 たばち「今回は抱っ紐編です。新生児から使えるタイプや人気のエルゴベビー、ベビービョルンなど4種類を使っていただきました。」 ととママ「同じエルゴベビーでも、上の子の時に使っていたものとはバージョンが違うので、変化も楽しみながら使ってみました。」 たばち「体験してもらった以外の新しいアイテムも用意したので、一緒にあれこれトークしていきましょう!」 ととママ「別のアイテムもあるんですね!それは楽しみです!」 たばち「今も絶賛抱っこ紐使用中のママとして、今回もリアルなお話を聞かせてくださいね。」 1. 抱っこ紐4種類を使い分けした時期について たばち「今回使っていただいた抱っこ紐は、アップリカ コランハグと専用新生児シート、ベビービョルン ベビーキャリアONE+Air、エルゴベビー OMNI360クールエアーとアダプトの4種類でしたが、それぞれ、どのようなタイミングで使われたのか教えてください。」 ととママ「生後1ヵ月頃から首が座るまでは、コランハグに新生児シートを取り付けて使用しました。その後、季節も暑くなってきて、首もだいぶしっかりしてきた頃に、メッシュ素材の2種類を使いました。」 たばち「同じメッシュ素材のベビービョルンのONE+AirとOMNIクールエアーの2つを比較するには、ちょうどいい季節でしたね。」 ととママ「メッシュ素材を使用したあと、寒さを感じるようになった頃からエルゴのアダプトに切り替えました。アダプトは今でも引き続き使用しています。」 たばち「なるほど!わかりました。では、時系列で順に具体的なお話を伺っていきますね。」 2. アップリカ コランハグと専用新生児シートを使ってみた! 新生児シートが赤ちゃんをしっかりホールドしてくれる たばち「まず最初はアップリカのコランハグについて伺いますが、新生児シートをセットされて使用したそうですね。」 ととママ「1ヵ月検診が過ぎた頃から、上の子供達のことで出かけなければならない事も出てきて、まだ縦抱きは不安だったので横抱きできる抱っこ紐を選びました。」 たばち「外出に不安はなかったですか?」 ととママ「新生児シートが赤ちゃんをしっかりホールドしてくれるので、全く不安はなかったですね。」 たばち「見た感じの安定感はしっかりありそうですね。」 ととママ「本当は離しちゃダメだけど、両手を離しても大丈夫くらい安定します。」 たばち「新生児シートの装着はどうでしたか?」 ととママ「最初はかなり手間取りました。ここが難点なんですが、装着方法が複雑なので取説をきちんと確認しないと難しいです。」 たばち「そうなんですね~。でも生後間もない赤ちゃんを乗せるならしっかり確認して正しく装着する必要がありますね。」 ととママ「でも、毎回やるわけではないので、一度装着してしまえば、あとは使うたびの微調整だけで問題なかったですよ。」...
抱っこ紐の種類を徹底解説!選び方のポイントとタイプ別おすすめ20選
子育て必需品の抱っこ紐。 出産準備のために!そろそろ赤ちゃんとの外出ができそう!今使っているものとは別のタイプがほしい!など、抱っこ紐を探している理由はそれぞれありますよね。 抱っこ紐には、大人気エルゴベビーのような長期で使えるキャリータイプ、スリングやベビーラップといった布で赤ちゃんを包み込むタイプなど、機能もデザインも異なるさまざまな種類があります。 妥協はしたくないけど、ここから1つを選び出して決めるのも一苦労。使用用途やお子さまの月齢、使う方の体型などによっても選び方が変わってきます。 そこで今回は、抱っこ紐選びをスムーズに進めるために、抱っこ紐の種類について解説していきます。 抱っこ紐タイプ別の特長、月齢別抱っこパターンの解説、商品選びで押さえてほしいポイント、おすすめ抱っこ紐20選を種類別に紹介します。 目的に合うベストな抱っこ紐選びの参考に、是非最後まで読んでくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 抱っこ紐のタイプ4種類を知ろう 抱っこ紐は大きく分けて4種類に分けられます。機能、素材、利便性、対象月齢など、種類により異なる上に、使い勝手にも個人差があります。 みんなが使っているから、流行っているから、という理由だけで判断せずに、まずはどのような種類があり、自分の希望にフィットするかを見極めることが大切。抱っこ紐選びの第一歩をここから一緒に進めていきましょう。 1-1. 安定感抜群!人気のキャリータイプ ・抱き方のバリエーションが豊富 ・新生児から3歳頃まで長く使えるものが多い ・肩や腰への負担が少ない ・しっかりした造りで安定感抜群 ・両手が自由になる ・サイズが大きい ・価格が高め ・脱着が難しく面倒なものが多い 街中でよく見かける「キャリータイプ」。多くのママパパに支持されている抱っこ紐です。 対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ、などさまざまな抱っこスタイルが可能。多機能で赤ちゃんの成長やシチュエーションに合わせた使い方ができること、新生児~3歳頃まで長期間使用できるものが多いことも人気の理由です。 両肩と腰で赤ちゃんを支える構造で、体への負担が軽減される設計が施されています。 しっかりとした造りなのでサイズ感は大きめ。抱っこ頻度が下がる時期の持ち歩きには不向きです。また、多機能な分、脱着が難しいものも多く、慣れない人は使いにくこともあります。種類が豊富で商品によって使い勝手がかなり異なりますので、よく見極めてから購入しましょう! 1-2. コンパクトで持ち運びが楽なスリング ・ヨコ抱きができ新生児から使用できる ・抱き方のバリエーションが豊富 ・授乳時の目隠しとしても使用できる ・お手入れが簡単 ・コンパクトに持ち運べる...
『子育て本音トーク vol.6』使ってみた!セーフティグッズ編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第6弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第6弾は「セーフティグッズ」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも…など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「今回はセーフティグッズ編、ベビーモニター、ベビーゲート、ベビーサークルの体験談を聞かせていただきます。3人目のお子さんで使用していただきましたが、里帰り出産ではなかったですよね?」 ととママ「里帰りはしなかったのですが、実家の母が来てくれて、1ヵ月検診が終わるまでサポートしてもらいました。」 あゆなママ「その間の家事はおばあちゃんがメインで?」 ととママ「そうです。がっつり頼らせていただきました!」 あゆなママ「そうなると、おばあちゃんが帰った後から今回のアイテムが登場することになりそうですね。では、その頃からのお話を詳しく聞かせていただきますね。」 1. ベビーモニターが便利だったシチュエーション 赤ちゃんの様子が確認できれば、落ち着いて家事に取り組める。 あゆなママ「1ヵ月検診を終えておばあちゃんが帰った後、どんなタイミングでモニターの使用をスタートしましたか?」 ととママ「実際にヘビーユースしたのは母が帰った後なんですが、モニターは生後間もなく使用を開始していました。」 あゆなママ「確かに。おばあちゃんがいても赤ちゃんのそばから離れることもありますよね。」 ととママ「基本的には夜に2Fで寝かせた時に使うことが多かったですね。カメラに赤ちゃんの顔が写るようにセットとして、私はリビングに降りてあれこれやることをこなす。」 あゆなママ「赤ちゃんの様子が手元で確認できれば、寝室にちょくちょく見に行く必要がないですもんね。」 ととママ「何かやってても赤ちゃんの様子が気になって集中できないじゃないですか。モニターがあることでものすごい安心感があって、自分もやることが落ち着いてできるのがよかったです。」 あゆなママ「夜でもしっかりと確認できましたか?」 ととママ「暗視モードはとても便利でした。暗闇でも表情がクリアに確認できました。」 あゆなママ「日中は使わなかった?」 ととママ「日中はリビングで寝かしていたので、母か私の2人の目があったから必要なかったのですが、母が帰った後は時々使いましたよ。ベッドで寝ている時は、モニターをセットして、2Fで洗濯物を干したり、掃除したりしてました。」 あゆなママ「離れて家事する時に赤ちゃんの様子が確認できれば、落ち着いて家事に取り組める。これはモニターの最大のメリットですよね。」 ととママ「そう!これがあるとないでは、安心感が全然違う!一度使ったママは手放せなくなるんじゃないかと思いますよ。私がそうでしたから(笑)」 2. ベビーモニター2種を使ってみた! 家事は水回りが多いから防水機能付きは安心 あゆなママ「今回2種類のベビーモニターを使っていただきましたが、まずは、防水ビデオモニターについて聞かせてください。」 ととママ「ちょっと大きくて今っぽくないんですけど、シンプルで使いやすいんですよ。多機能だと私には使いこなせないのでむしろ使いやすかった(笑)」 あゆなママ「わかる!取説をしっかり読み込むってシンドイ。しかも産後間もないママはそんなことしてられないし。機会音痴のママでも簡単に使えるのはいいですね!」 ととママ「あとは何と言っても防水機能!家事は水回りが多いから防水機能付きは安心。」 あゆなママ「お風呂でも使いました?」 ととママ「私は使わなかったけど、一人で湯舟に浸かりたい時はすごくいいと思う。」...
どこよりも詳しく解説!ベビーゲートをお得に賢くレンタルする方法!
レンタルできるベビーゲートをお探しですか? 昨今の環境問題、断捨離やミニマリストのブームもあり、モノを増やさない努力をして、すっきりとした生活を心がけるママやパパが多くなってきています。どうしても増えてしまうベビー用品も、使用期間の短いものはレンタルを活用するなど工夫されているようです。 レンタルは、必要な期間だけ使うことができ不要になったら返却するだけ、収納や処分の悩みもありません。購入前にご家庭に合うのかまずはレンタルで試してみる、という活用方法もあります。 ここでは、ベビーゲートのレンタルを検討しているママパパに向けて、お得に賢くレンタルを活用する方法を紹介します。 「数あるレンタルショップの中からお得なショップを探すのは大変だけど、損はしたくない!」という忙しいママパパに代わり、レンタルショップ13社を徹底調査、最安値ショップベスト5を大公開! また、レンタル前に絶対に確認してほしい3つのポイント、レンタルショップの選び方のコツ、先輩ママパパのレンタルしてよかった口コミも紹介していきます。 今回の比較調査でpickupした日本育児のロングセラ―商品「スマートゲイト2」「おくだけとおせんぼ」「キッズパーテーション」は、ナイスベビーでも大人気のレンタル商品です。そして、ワイドタイプ「木製パーテーションFLEX」は、ベビーゲートの中でも特にレンタルの需要が高い商品。レンタルできるのはナイスベビーだけという必見のアイテムです! こちらの記事を読み進めていただければ、赤ちゃんの安全と家事育児のしやすい環境づくりにきっと役立てていただけるはずです。それでは早速、レンタルベビーゲートについて見ていきましょう。 1. レンタル前に知ってほしい!設置場所の3つの確認ポイント 「レンタルした後に取り付けできないことに気が付いた!」 ナイスベビーでベビーゲートをレンタルされたお客様から、お届け後に相談を受けることがよくあります。 ベビーゲートは、事前準備がとても重要なセーフティグッズ。設置場所の幅や高さ、取付位置などの確認が不十分であると、このような事態を引き起こすことになります。 商品選びのための事前準備には、いくつかのポイントがあります。このポイントをしっかり押さえておけば、壁が破損してしまったり、壁紙がはがれてしまうような悲劇が起こることはありません。ご家族とも相談して一緒に確認しながらベストなベビーゲートを選んでいきましょう。 1-1. 取付幅を正しく採寸しましょう! 設置したい場所が決まったらしっかり採寸しましょう。 おくだけタイプのものであれば幅のサイズが合えば簡単に設置できます。 しかし、突っ張り式のベビーゲートのレンタルする場合は注意が必要です。特に、手すりや幅木がある場合は、レンタルする商品の突っ張り部分がしっかり合うか確認してください。メーカーによっては、様々な幅に対応できるように拡張フレームが同梱されていたり別売りのパーツがあります。事前にしっかり採寸してから商品選びを行ってくださいね。 1-2. 取り付けたい壁面の強度を確認しましょう! 突っ張り式のベビーゲートは、取り付けたい位置が柱でなく壁面の場合、中が空洞だと正しく設置ができません。桟のない場所に取り付けると壁面が破損することもありますので、注意してください。 壁面に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機を使うと簡単に探すこともできますが、壁をノックをして音の違いで空洞かどうかが簡易的に判別できることもあります。しっかり取付のできる壁かどうかを家族と一緒に確認するようにしてください。 固定する接地面に傷が残る場合がある 『突っ張り式=傷が付かない』と思っていても、壁紙の素材によっては傷が残ることもあります。凹凸のある柔らかい壁紙だと、突っ張り部分に圧がかかるためつぶされたような跡が残ってしまう可能性も。こちらは、実際、突っ張りタイプのベビーゲートをはずした後の壁紙の剥がれた跡です・・・傷が付かないとは言い切れない。 ※傷の付かないものをお探しの場合、置くだけで設置OKのベビーゲートがあります。 1-3. 階段上はネジ止めでしっかり固定!階段上専用は購入がおすすめ! 階段下では一般的なベビーゲートを使用できますが、階段上については「階段上専用」と明記されいてるベビーゲートの使用が必須です。階下への転落を防止するためには、動くことがないようネジ止めで固定する必要があります。階段上に設置するベビーゲートは、一部のレンタルショップでレンタルができますが、ネジでしっかり固定するものなので、中古のレンタルより購入か新品のレンタルをおすすめします。 階段上に設置できるベビーゲート 赤ちゃんがひとりで下りないよう階段上にゲートを設置する際は、完全な固定式、ネジでしっかり止める必要があります。階段上専用ベビーゲートか、設置場所スペースや壁・柱に取り付けられるかを購入前に必ず確認してください。 ▼ 購入を検討するなら ▼...
満足度がぐんと上がる!2本目の抱っこ紐が必要な理由とおすすめ5選
初めての抱っこ紐選び、様々な種類の中から自分のお気に入りを見つけてやっと購入!日々の生活でもすっかり必需品として定着してきた頃に... 「もう少し手軽も使えるものがあったらいいな」 「コンパクトに持ち運べるものほしいけど...」 「安くていいものはある?」 まさか、2本目が必要になるなんて、思いもしなかったですよね。 そうなんです! 抱っこ紐は1本だけだと、何かと不便を感じることが多くなってくるのです! 外出時の持ち歩き、洗い替え、季節が変わって使いにくい...など、これまで使っていた抱っこ紐とは別用途で使えるセカンド抱っこ紐の必要性を感じてくるものです。 実際に、抱っこ紐を2本、3本使っているという方は多く、むしろ、それが普通といってもいい現状。 生活スタイルによって最適なタイプも異なるため、メインとサブの2本を購入して、用途に合わせて使い分けるご家庭が大多数。使い分けすることで小さな子供とのお出かけや暮らしに対する満足度がぐーーんとアップします。 そこで今回は、先輩ママパパが2本目の購入に至った理由や抱っこ紐選びで失敗しないためのポイントを詳しく紹介します。また、セカンド抱っこ紐にぴったりなオススメの抱っこ紐の紹介、3つの抱っこ紐を使い分けしていたママの実体験レポートも合わせて公開します。 抱っこ紐の追加購入を考えているママパパは必見!自分にぴったりなセカンド抱っこ紐探しにきっと役に立つはずです。是非最後まで読み進めてくださいね! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. セカンド抱っこ紐「あってよかった」シチュエーション そもそも抱っこ紐は複数必要なのでしょうか?! まずはその実態を調査すべく、ママパパ100人に「抱っこ紐はいくつ持ってますか?」のアンケートを実施しました。 結果はご覧の通り、35%が2個、23%が3個以上と全体の58%もの方が複数使用していました。多くの方がセカンド抱っこ紐を必要だと感じているということがわかりますね。 では、実際にセカンド抱っこ紐が「あってよかった」と思ったのはどのようなシチュエーションなのか、体験談を交えて紹介していきます。 1-1. コンパクトに持ち歩きたい!お出かけのとき 「歩くようになり抱っこ回数が減ったので、持ち歩き用でコンパクトになるタイプを購入しました。」 「抱っこ紐を持っていかないのも不安だけど、持ち歩くのはすごく邪魔。折りたたみタイプを外出時に使うようになってから、ストレスがなくなりました!」 ファースト抱っこ紐は、機能重視のがっちりタイプを購入する方が多いと思います。 ヨチヨチ歩きが始まると、抱っこ紐を付けたり外したり面倒な事態も発生、がっちりタイプの抱っこ紐を装着してぶらんとさせているママパパもよく見かけます。 ただでさえ小さな子供とのお出かけは荷物が多いのに、このタイプは畳んでも大きく、外出時の持ち歩きに向いてるとは言い難いものです。 でも、抱っこ紐を持ち歩かないのは不安、それでもできるだけ荷物はコンパクトにしたいということで、畳めるコンパクトな持ち歩きタイプを追加購入された方は多いようです。 長時間の抱っこや家事中の使用には、がっちりしたメイン抱っこ紐。お出かけには、コンパクトなサブ抱っこ紐を使い分けるのがオススメです。 1-2. いつでも清潔を保てる!洗い替えのとき 「家でも外でも使いっぱなし。洗濯した時は一日大変なことになったので洗い替え用で購入しました。」 「汚れたら困る時に限って洗濯が必要になったり、子育ては予測不可能なことが起こる。サブ抱っこ紐を購入してからは慌てることがなくなりました。」 抱っこ紐は外出時の他にも、家事を行うとき、寝かしつけのときなど自宅で使用されている方も多いのではないでしょうか。...
スゴカルSwitchはタイヤが劇的進化!実際に動かしてみて感動したこと
国内ベビーカーメーカー大手「コンビ」のスゴカルシリーズは、数あるベビーカーラインナップの中でも赤ちゃんを守る機能と軽量化を追求した人気モデル。 スゴカルシリーズから最新機種として「スゴカルSwitch(スゴカル スイッチ)」が登場し、ナイスベビーで取り扱いを開始しました。 「おでかけが変わる、超・安定感」というキャッチフレーズのとおり、走行時の安定感の高さが特徴のベビーカーです。 今回実際にスゴカルSwitchを動かしてみたところ・・・ その走行性能の進化に驚きました! 今まで様々なコンビ製ベビーカーを触ってきましたが、他と一線を画す押しやすさです。 従来のスゴカルシリーズと比べても走行性能が格段に向上したスゴカルSwitchは、いったいどのようなバージョンアップをしたのでしょうか。 旧モデルと比べてみた実体験とあわせて、特筆すべき赤ちゃんを守るための最新機能や、ママにとっての便利機能などその魅力に迫ります。 1. スゴカルスイッチはタイヤが劇的に進化! スゴカルSwitchの最大の特徴は「タイヤ」です。 旧モデルと比べタイヤが格段に進化しています。この進化が走行性能の向上に大きく影響しているのです。 こちらは旧モデルとの比較写真。何と言っても目を引くのがスゴカルSwitchの片側の大きなタイヤですよね。よく見ると大きい方のタイヤは2輪(ダブルタイヤ)になっていて、小さい方のタイヤは1輪(シングルタイヤ)になっていることが分かります。 旧タイプはどちらのタイヤも2輪になっています。 ダブルタイヤとシングルタイヤには、路面状態によって役割があります。 前輪と後輪の形状を変えたことによるメリットと、それぞれのタイヤの特徴を詳しく見てきましょう。 1-1. ダブルタイヤの安定性とシングルタイヤの走行性能を兼ね備えたすごいベビーカー ベビーカーは前輪で舵を取って進むので、進行方向側のタイヤによって走行のしやすさが変わります。(基本的に後輪は固定された状態になります。) スゴカルSwitchは対面と背面を切り替えることによって、ダブルタイヤとシングルタイヤのどちらを進行方向側のタイヤにするか選ぶことができます。 これがスゴカルSwitchのポイントなんです。 では、18cmのダブルタイヤと14cmのシングルタイヤを切り替えることでどのようなメリットがあるのでしょうか。 進行方向側がダブルタイヤの場合 ・2輪タイヤでしっかり車体を支えるから、バランスが取りやすい。 ・シングルタイヤと比べ、デコボコ道で赤ちゃんの頭に伝わるヨコ揺れを約50%もカット。産まれたての頭をしっかり守る。 ・18cmと大型になり安定性がさらに増した。 ※コンビでは「ダブルタイヤ」のことを、「バランスタイヤ」としています。 進行方向側がシングルタイヤの場合 ・走行性能重視。スイスイスムーズに走る。...
ベビーサークルレンタルショップ最安値!失敗しない選び方とおすすめ4選
ベビーサークルは使用期間の短い大型のベビー用品。 導入を検討する中で、価格面、保管場所、処分問題など、いくつかの課題にぶつかっている方も多いのではないでしょうか。とはいえ、目が離せない月齢になった赤ちゃんとの生活にはとても便利な子育てアイテム。その魅力にはどうしても惹かれてしまいますよね。 そんな時は、迷わずレンタルを利用しましょう! レンタルであれば、必要な時期だけ使って、不要になれば返却するだけ。保管スペースの確保や処分の心配もなく安心です。また、赤ちゃんに合うかどうか試してみたい方にもおすすめ! しかし、いざ、ベビーサークルをレンタルしようと調べても、送料や手数料などもレンタルショップによって違うため、判断が難しいところ。品質やサービス内容なども気になりますよね。それに、忙しいママパパは、ショップ比較にとことん費やす時間も手間もないですよね。 そこで今回は、そんなママパパに代わり、人気のベビーサークル2商品について、お得にレンタルできるショップを徹底調査しました。また、失敗しないベビーサークルレンタルのために、知っておきたい3つのポイントの解説、おすすめのレンタルベビーサークルも紹介していきます。 この調査ではレンタルショップ13社を徹底比較。レンタル価格ランキングで当社「ナイスベビー」は、1位と2位という結果に!価格をできるだけ抑えて、商品自体にもご満足いただけるよう日々のメンテナンスや迅速なお客さま対応を心掛け企業努力をし続けています。 おかげさまで、超ロングセラーベビーサークル『キッズランド』の出荷数は年間なんと300台!たくさんのご家庭へお届けしているナイスベビーのレンタルサービスについて、その全貌も紹介いたします。 この記事の最後には、ベビーサークルレンタルの体験談もご紹介!有効的な活用法も是非参考にしてください。 レンタルベビーサークル上手に利用して快適な赤ちゃんとの生活を楽しんで下さいね。 1. レンタル前に知っておきたい3つのポイント 「はじめてレンタルする」というママパパへ、レンタル前に知っておいてほしいポイントを解説します。 ベビーサークルは、実際使える期間が短く、使わなくなった後の収納場所を考えると、必要な時期だけレンタルで使用するのがピッタリなアイテムです! ベビーサークルをしっかり活用してもらうためにも事前確認が大切!レンタルする商品を選んで、サイズと置く場所のスペースをしっかりチェックしてから注文すれば安心ですよ。それでは早速、確認していきましょう! 1-1. レンタルベビーサークルの種類と選び方 レンタルショップで多く取り扱われているベビーサークルには、木製タイプ・プラスチックタイプ・メッシュタイプの3タイプがあります。素材によって使い勝手も変わってきますので、まずはその特徴を見ていきましょう。 木製タイプは、しっかりとした造りの安定感が特長。木製はインテリアを選ばずリビングに置いても違和感なく生活に馴染んでくれます。 プレスチックタイプは、組み立てが簡単でママ一人でも楽に設置ができます。汚した時のお手入れもサッと拭くだけで、気兼ねなく使える点も魅力です。カラフルなデザインも多いので赤ちゃんも興味を持ってくれるようです。 メッシュタイプは、折りたたみ式のものも多く、設置と収納が手軽にできるのが最大のメリット。使わない時は片付けたい、色々な場所で使いたいなど、一定の場所に設置を予定しない方におすすめです。 素材と使い方でタイプを絞り込んだら、設置場所を検討しサイズを決めましょう。 設置場所に、新聞紙や荷造りロープを使ってスペースを形どり、そのサイズを測ってみるのがオススメの採寸方法。実際に確保できるスペースを購入前にしっかりと確認してから、サークルのサイズを決めましょう。 「ベビーサークルが大きすぎて導線がふさがれてしまい、洗濯を干しに行くのが大変になってしまった。」「常設のベビーサークルをテレビの前に置いたら、画面下のテロップが見えなくなった...」などの失敗談も耳にすることがあります。一番重要なのは、選んだサークルが自宅の設置場所に合うかということ。必ず事前にベビーサークルの大きさをイメージしておきましょう。 1-2. レンタル開始時期の目安は、生後6カ月ごろから! ベビーサークルは生後6ヶ月からのレンタル開始がおすすめです。 まだ自我が強くない月齢の低い時に使い始めると、サークルに対する拒否反応が出にくい傾向にあります。 後追いが始まった頃から使い始める場合、サークルから大人が離れると泣いて出たがる、ということがよく見られます。「サークルに入る=一人で置いていかれる」と思うのでしょう。サークルを嫌がって入らない事態に陥いることもあります。 そんな時は、初めの1週間は、大人もそばで一緒に遊んであげて、楽しい場所だと認識するようになるまで付き添ってあげてください。場所慣れをさせる意味でも効果的な方法です。サークル内にいることに違和感を感じず、日常として捉えることができれば、その中で大人しく遊んでくれるようになるでしょう。 月齢別赤ちゃんの発達の様子とサークルの必要度 生後6~9カ月頃 ハイハイを始めて自分で行きたいところに移動できるようになると、赤ちゃんにとって危険なものに、わからずに手をかけてしまうことがあります。熱いポットや尖ったものでけがをしたり、薬やボタン電池などの小さいものを口に入れてしまうなんてことも。...
ママパパ200人に大調査!抱っこ紐はいつまで?卒業時期とその理由
赤ちゃんとのお出かけ必需品「抱っこ紐」 使い始めの頃は小さかった赤ちゃんも、気が付けばずっしりと重たくなり...。10kg前後の重さを抱えて歩く重労働に限界を感じ始めているママも多いはず。赤ちゃんの成長と共にママの肩や腰が悲鳴をあげはじめていませんか?「抱っこ紐って、いつ頃まで使うものなの?」という疑問も頭をよぎりますよね。 そこで今回は、抱っこ紐はいつまで使う?!という疑問にフォーカス! 先輩ママパパ200人に抱っこ紐の卒業時期についてアンケート調査を実施し、抱っこ紐使用期間の現実に迫ります。また、実践した抱っこ紐卒業後の「抱っこ」対処方法や、体の負担を軽減する正しい抱っこ紐の使用方法についても詳しく解説していきます。 この記事を読んで頂ければ、抱っこ紐卒業時期の見極めができ、その後も楽しいお出かけを叶えることができます。是非最後まで読み進めてくださいね! 1. 1~2歳頃!ママパパ200人に聞いた抱っこ紐の卒業時期 まずは、リアルな使用期間を知るために、先輩ママパパ200人に「抱っこひもの卒業時期」についてアンケート調査を実施しました。その結果は、なんと「1~2歳頃」が最も多い回答に! 過半数の方が使用期間よりも早くにやめている事がわかりました。もちろん赤ちゃんの成長スピードや商品によって異なり、長い人では3歳以上になるまで使用していた方もいました。ただし、赤ちゃんの成長と共に、ママパパのカラダの負担が増すことは間違いありません。 まずは2歳頃の卒業を目安に、赤ちゃんの成長とママパパの負担が大きくならない時期を見計らって、タイミングを選んでくださいね。 2. 2歳未満で抱っこ紐の使用をやめた理由 手軽に場所を選ばず使える便利さと、俄然抱っこが楽になるだけに、できるだけ長く使用したいと考えている方は多いようです。しかし、過半数以上が「2歳になる前」に使用をやめている結果を見ると、思ったより長く使わなかった、というのが現実でしょう。 そこで、なぜ2歳未満で使用をやめたのか、卒業した理由についてママパパのリアルな声を集めました。抱っこ紐の卒業時期の参考にしてみてください! 2-1. 重たくなって肩や腰に負担がかかるようになったから 平均体重(kg) 男児 女児 6ヵ月 7.67 7.17 1歳 9.28 8.71 2歳 12.03 11.39 3歳 14.10 13.59 ※参考:平成22年度 厚生労働省「乳幼児身体発育調査報告書」...
プレママ必見!ネムリラの全てがわかる徹底比較と先輩ママの体験談
赤ちゃんのお世話がぐーんと楽になるアイテムとして、先輩ママたちからの経験談を聞き、ネムリラについて調べるママパパが多いのではないでしょうか。なんとなくいいのだろうな~と、漠然と思っているだけではありませんか? 先輩ママたちが大絶賛する通り!ネムリラを使用した場合と使用しなかった場合ではママの子育て負担が全く違うのです! 今回はそんなママパパに向けて年間5000台以上のネムリラを赤ちゃんの元にお届けしているナイスベビーラボがネムリラの全てを徹底解説します。 なぜ「ネムリラ」が選ばれるのか? ネムリラシリーズは発売されて以降、大人気商品のため様々な機種がでていますが、どのネムリラを選べば失敗しないか。先輩ママが実際にネムリラを使用したリアルな体験談から、さらに高級ベビー用品でもあるネムリラを安くお得に用意するコツまで隅々まで紹介していきます。 ぜひネムリラの良さを知って頂いた上で、ご自身にぴったりなネムリラを見つけて下さいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. ハイローチェアの代名詞ともいうべき「ネムリラ」 ネムリラはベビー用品メーカー「コンビ」の揺れるハイローチェアのブランド名です。 ネムリラは爆発的なヒット商品のため、ネムリラという名前の方が先行してしまい、世のママたちには、ハイローチェアをネムリラと呼ぶ人が続出するほど、知名度の高いブランドです。もはやハイローチェアの代名詞と言っても過言ではない商品なのです。 そもそもハイローチェアが開発されたのは、コンビの営業マンがお客様の自宅に訪問した際、家の中にベビーカーを入れてゆらゆら揺らして赤ちゃんの寝かしつけをしているママをみたことがきっかけだったとか。確かにベビーカーや車の中だと良く寝てくれる赤ちゃんの話を沢山聞きますよね。 そこで自宅の中でも心地よい揺れを赤ちゃんに与えることで、ママの代わりに寝かしつけをしてくれるベビー用品として登場したのがハイローチェアでした。 ネムリラは、1980年代後半に開発された「スウィングラック」が前身。* 手動式のスウィングラックにオプション品のモーターを取り付けることで電動ラックにもなるという、一台二役を担う商品でした。当時はベビーラックと呼ばれるゆりかごタイプのものが主流だった中、脚は固定でチェア部分のみが平行にスウィングするこの「スウィングラック」は画期的商品だったそうです。今でもハイローチェアはスウィングラックとも呼ばれるのは、この名残なのかもしれません。(*当社調べ) 「スウィングラック」発売以来、その人気は年々上昇。開発に開発を重ね、現在の形へと変貌を遂げています。 ネムリラは、赤ちゃんの快適性を徹底的に追求し、揺れ方や動作音、クッションに至るまで些細な部分までこだわりぬき、常に進化し続けています。 コンビのチャイルドシートやベビーカーにも採用されているコンビ独自開発の超・衝撃吸収素材「エッグショック」をネムリラのシートにも搭載しています。「エッグショック」を使用したクッションは、ママにだっこされているような寝心地と安心感を与え、心地よい揺れとともに赤ちゃんを眠りに導いてくれます。赤ちゃんの全身をしっかりと守る安心のシートなのです。 ▼ ハイローチェアの使い方について詳しくはこちらの記事で ▼ 「使い方がわからない」を解消するハイローチェアの操作法Q&A 2. ママたちにネムリラが圧倒的に支持される3つの理由 ネムリラは「寝かしつけ抱っこの代わりに」「赤ちゃんの安全な居場所として」「お食事用チェア」としてこの3つの理由から先輩ママたちから絶大な人気を集めています。 もちろんネムリラがなくても赤ちゃんは日々すくすくと成長していきますが、ママのちょっとした気持ちの余裕のためにもネムリラを使用することをおすすめします。 2-1. 寝かしつけ抱っこの頼もしい代役ネムリラ ママがちょっと手が離せないとき、ネムリラがママに代わって寝かしつけをしてくれます。 どうしても生後間もない赤ちゃんは眠りに入る前に泣いてしまうことが多いと言われ、それは私たち大人にとって「眠い」という当たり前の感覚が、赤ちゃんにとっては初めてで戸惑い、それを不安に感じているのではないかと一部では考えられています(諸説あり)。 そのため、ママが優しく抱っこをし揺れてあげることで赤ちゃんはママをそばに感じ不安が和らぎ、いつしかスヤスヤと眠ってくれます。やっぱり、何といっても赤ちゃんが最も眠りに入りやすい状況はママに抱っこしてもらっている時です。 だからといって、ママが1日中赤ちゃんにつきっきりで寝かしつけ抱っこをし続けるのはとても大変です。 妊娠中に大きなお腹を支え続けたことで腰を痛めてしまうママや、産後まだ体調が戻りきらないママ、帝王切開のママにいくら新生児とはいえ1日中抱っこをするのはとても大変なことです。...